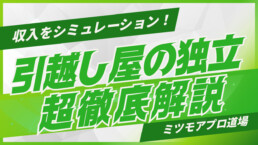「孫請けは違法」は誤解?本当のリスク「偽装請負」の見分け方を解説
孫請けという契約形態は、それ自体では違法ではありません。建設業やIT業界で広く採用されている業務専門分化の仕組みです。しかし、働き方の実態が「偽装請負」に該当する場合、厳重な罰則の対象となります。
孫請けとは具体的にどのような立場で、法的に何が問題になるのか。請負や派遣といった他の契約形態とどう違うのか。解説します。
- 孫請けという契約形態そのものは法律違反ではありません。業務の専門分化のために一般的に採用されている仕組みです。
- 違法となる最大の原因は「偽装請負」です。契約は請負なのに、実態として元請けから指揮命令(具体的な作業指示や時間管理)を受けていると違法と判断されます。
- 請負と派遣の決定的な違いは「指揮命令権」の所在です。請負の指揮命令権は「受注者」にありますが、派遣は「派遣先(元請け等)」にあります。この違いが違法性を見抜く鍵です。
そもそも孫請けとは?
孫請けとは、元請けから仕事を受けた下請け(二次請け)が、さらに別の業者に仕事を再委託した際の受注者(三次請け)を指します。
仕事の発注者から直接仕事を受ける会社が「元請け(一次請け)」です。元請けが仕事の一部を別の業者に発注すれば、その受注者が「下請け(二次請け)」、さらにその下請けが別の業者に発注すれば、その受注者が「孫請け(三次請け)」となります。
構造を図にすると以下のようになります。
発注者
↓
元請け(一次請け)
↓
下請け(二次請け)
↓
孫請け(三次請け)
このように、複数の会社が階層的に一つの仕事に関わる構造を重層下請け構造と呼びます。これは建設業やIT業界などで、専門分野ごとに作業を分担するために広く採用されている仕組みです。
孫請けとして働くこと自体は、違法ではありません。
しかし、孫請けという契約であっても、働き方の実態が法律の定めるルールから逸脱した場合、「偽装請負」として明確に違法と判断されるケースが非常に多いため、注意が必要です。
違法か適法かを見分ける最大のポイントは、働き方と契約の中身が一致しているか、特に元請けから直接仕事のやり方について指示(指揮命令)を受けていないかという点にあります。
出典:国土交通省「重層下請構造の改善に向けた取組について」
請負・派遣・準委任はどう違う?
| 契約形態 | 指揮命令権 | 報酬の対象 |
|---|---|---|
| 請負契約 | 受注者にある | 仕事の完成(成果物) |
| 準委任契約 | 受任者にある | 業務の遂行(時間・工数) |
| 労働者派遣 | 派遣先(元請け等)にある | 業務の遂行(時間・工数) |
仕事の契約形態は、主に「指揮命令権(誰が作業の指示を出すか)」によって明確に区別されます。
孫請け契約は通常、「請負契約」または「準委任契約」のどちらかです。
どちらの契約も、プロの事業者として仕事を引き受ける形態であり、仕事の進め方や時間の使い方は、基本的に受注者(あなた)の裁量で決めることができます。元請けから作業の手順について細かく指示(指揮命令)を受けることはありません。
しかし、この「指揮命令権の所在」が曖昧になり、契約と実態が食い違ってしまうと、法的な問題が発生します。
出典:公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」
孫請けが違法となる「偽装請負」とは?
偽装請負とは、契約書上は「請負契約」であるにもかかわらず、実態として元請けや発注者から「労働者派遣」のように直接の指揮命令(作業指示や時間管理)を受けて働いている状態を指します。
なぜ、このような偽装請負が横行するのでしょうか。
背景には、発注者側の「社会保険料の負担や労働時間の制限といった、労働者を守る法律のコストから逃れたい」という動機があります。そのために、実態は労働者と変わらないのに、意図的に「請負」という形式を悪用するケースが後を絶ちません。
ご自身の働き方が偽装請負に当てはまっていないか、以下のチェックリストで現場を振り返ってみてください。
偽装請負チェックリスト
- 作業の指示に関する項目:元請けや発注者の担当者から、作業の進め方や手順について具体的な指示を受けている
- 時間の管理に関する項目:元請けや発注者から始業・終業時間、休憩時間、休日などを指定・管理されている
- 代わりの人に関する項目:病気や急用で休む場合、代わりの人間を自分の判断で立てることができない
- 道具や材料に関する項目:業務に必要な機材や道具、材料をすべて元請けが無償で提供している
上記は、厚生労働省が示す基準に基づいたチェックリストです。プロの事業者であるはずの裁量権が、どれだけ侵害されているかが明確になります。複数の項目に心当たりがある場合、請負事業者ではなく実質的に労働者として扱われている可能性があります。
孫請けの立場でこのような状態にある場合、契約上は請負でありながら元請けから直接指揮命令を受けている「偽装請負」に該当し、違法となります。
出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」
偽装請負以外に孫請けが注意すべきポイント
取引や報酬の面でも、孫請けという弱い立場になりがちな構造ゆえの問題があります。
一括下請負(丸投げ)への加担
建設業の場合、孫請けが「一括下請負(丸投げ)」という違法行為に加担させられるリスクがあります。
建設業法では、元請けが発注者から請け負った工事を、実質的に何も関与しないまま下請けにそっくりそのまま流すことを原則として禁止しています。
主に元請け側の違反ですが、孫請けが実質的に「丸投げ」だと知りながらその仕事を引き受けた場合、行政処分の対象となるリスクがあります。
出典:国土交通省「建設工事における一括下請負の判断基準を明確化しました」
親事業者の不当行為
孫請けという弱い立場を利用し、親事業者が不当な減額や支払遅延といった不当行為を働くことがあります。こうした被害から守るために、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が存在します。孫請けという立場であっても、発注した会社(親事業者)と受注側(あなた)の資本金の組み合わせ条件を満たせば、下請法が適用されます。
下請法が適用される条件例
- 発注した会社(親)の資本金が1,000万円超
- 受注側(あなた)の資本金が1,000万円以下(個人事業主・フリーランスは全員該当)
下請法で禁止される親事業者の主な行為
- 書面の不交付:仕事を発注する際、発注内容、金額、納期などを明記した書面を交付しないこと(口約束だけでの発注は違法)
- 不当な減額:発注時に決めた金額を、発注後に一方的に減額すること
- 不当な支払遅延:成果物を納品してから60日以内に代金を支払わないこと
- 不当な買いたたき:通常の相場より著しく低い価格を一方的に押し付けること
これらの行為は法律で禁止されているため、心当たりがあれば泣き寝入りする必要はありません。
出典:中小企業庁「下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」
孫請けのトラブルを回避する3つの方法
契約書を必ず確認する
口約束だけで仕事を進めるのは最も危険です。必ず書面(PDFや電子契約でも可)を取り交わしてください。
契約書や注文書を受け取ったら、最低でも以下の点を確認しましょう。
- 業務の範囲:具体的に何をどこまでやるのかが明確になっているか
- 成果物:何を納品すれば仕事の完成となるのか、認識が合っているか
- 報酬と支払条件:金額、支払日、支払方法は納得できる内容か(特に支払日は納品から60日以内か)
- 責任の範囲:不具合が出た場合、いつまで無償で修補する責任があるか記載されているか
指示ややり取りの証拠を残す
万が一、元請けとの間でトラブルになった際、証拠はあなたを守る最も強力な武器となります。日々のやり取りを意識的に記録に残しましょう。
- 具体的な作業指示が書かれたメール、LINEなど
- 始業終業の管理をされていることがわかるタイムカードや業務日報
- 元請けと交わした契約書、注文書、発注書、請書
おかしいと思ったら公的機関に相談する
一人で抱え込むのが最も危険です。無料で匿名でも相談できる公的な窓口が多数あります。
偽装請負(働き方)の疑いがある場合
- 相談先:最寄りの労働基準監督署、または都道府県の労働局
- 働き方の実態が労働者に近いと判断されれば、労働基準監督署が調査し、発注者に行政指導を行う場合があります。
下請法違反(不当な減額・支払遅延など)の場合
- 相談先:中小企業庁 下請かけこみ寺
- 下請かけこみ寺は全国にあり、取引上のトラブルについて無料で専門家(弁護士など)に相談できます。
出典:中小企業庁「下請かけこみ寺」
孫請けに関するよくある質問
Q1:そもそも孫請けとは何ですか?
A1:元請けから仕事を受けた下請け(二次請け)が、さらに別の業者に仕事を再委託した際の受注者(三次請け)を指します。建設業やIT業界で専門分野ごとに作業を分担するために広く使われている商習慣であり、孫請けという立場自体が違法なわけではありません。
Q2:孫請けは、それ自体が違法なのですか?
A2:いいえ、孫請けという契約形態自体は違法ではありません。業務を専門分野ごとに分担するための合理的な仕組みです。ただし、働き方の実態が「偽装請負」(契約は請負なのに実態は派遣)になると違法と判断されます。
Q3:偽装請負かもと思ったら、まず何をすべきですか?
A3:まずは証拠(元請けからの具体的な作業指示がわかるメールやチャット、時間管理の記録など)を日々記録・保存してください。その上で、最寄りの労働基準監督署や都道府県の労働局に匿名で相談することから始めましょう。
まとめ
孫請けに関する法的な不安は、正しい知識で対処することができます。報酬の問題に関しては、法律で対抗する道もありますが、そうした悩みを根本的に解決するもう一つの選択肢が、元請けとして顧客から直接受注する働き方です。
Web集客プラットフォーム「ミツモア」を活用し、直接受注という新しい働き方に挑戦した事業者がたくさんいます。
事例:YDKリノベーション
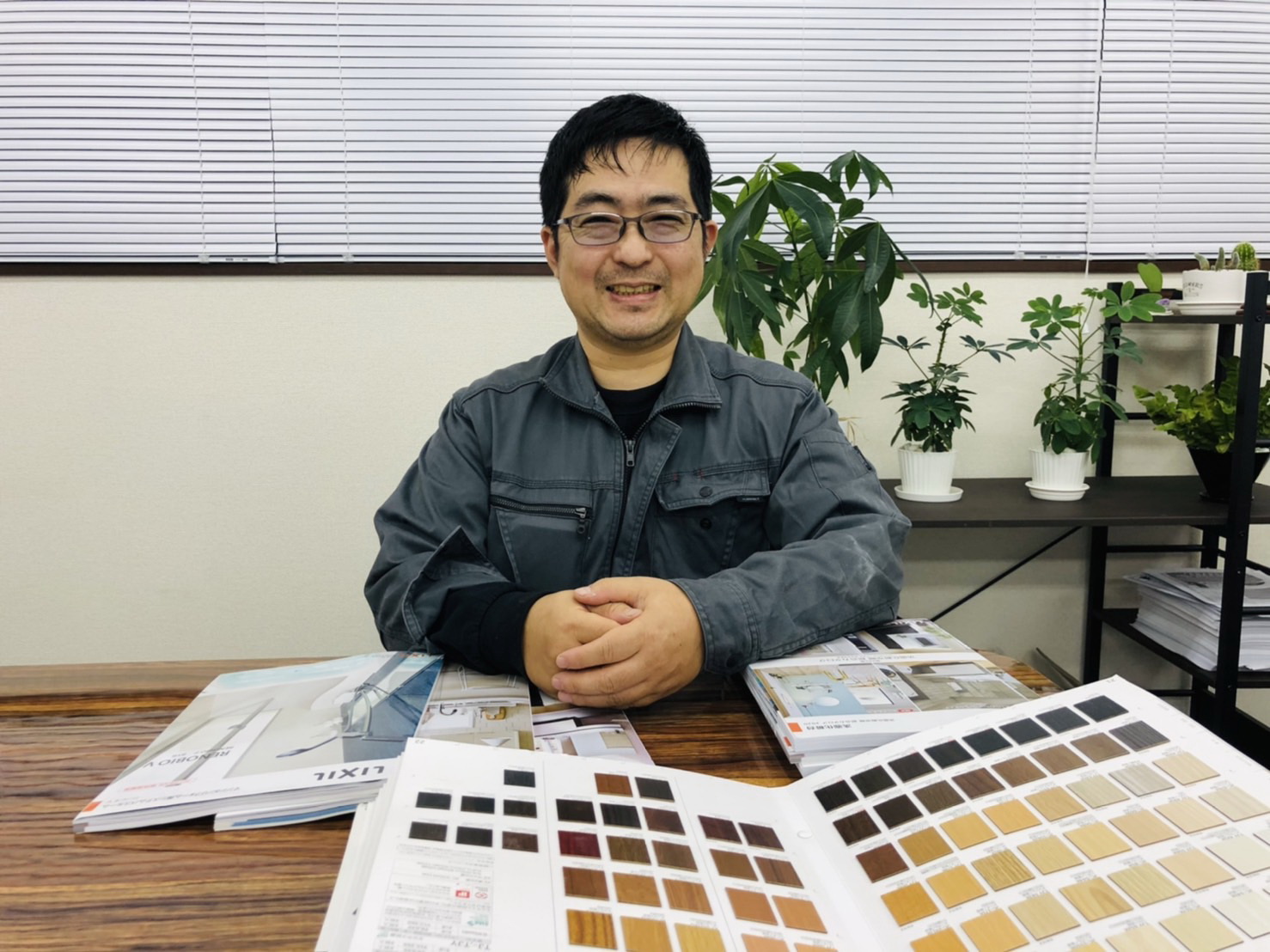
登録前の状況
もともと建設業者から受注する形で建物の内装、障子や襖など建具の製作・取り付け、クロスや水道設備配管、フローリングといった現場仕事を請け負っていました。これまでは建設会社から直接請負う仕事が大半で、web上で個人のお客様に対して営業すること自体、未経験でした。
登録後の変化
登録したその月に20件近く成約。ネット上にドアの修理や取り替えの案件を扱う専門の職人さんの数が少ないため、かなりの件数を成約できるのかなと想像しています。以前は大手の集客サイトも使ってみましたが、今ではミツモアがメインになっています。ミツモアは案件が多くて、しかもお客様が本気でプロを探しているんですよね。だからすぐに成約までいける。その意味で、web集客ツールのメインに使わせていただいています。
関連記事:「Web集客未体験のベテラン建具職人がドア修理の稼ぎ頭に。初月から二桁成約を継続する秘訣を公開」
ミツモアへの登録は完全無料です。今の仕事と両立しながらミツモアの案件を隙間に入れる。そんな活用方法もあります。
関連記事
Stickyハウスクリーニング
【フジテレビ newsイット!取材】月間成約250件! 最大5社から見積もりが届くミツモアは依頼者が比較して選びやすく、事業者にもメリットになっています
ミツモアは見込み顧客と出会える集客プラットフォームです。