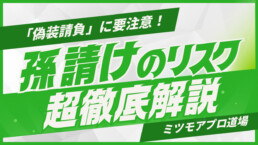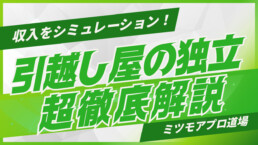元請けがお金を払ってくれない!!未払い金を回収する4ステップと無料相談先を紹介
元請けからの未払い代金は、正しい手順を踏めば回収できます。証拠を集め、内容証明で催促し、交渉が決裂すれば法的措置に移行する、というステップが一般的な回収手順です。しかし、証拠不足や時効により、タイミングを逃すと回収が困難になることも事実です。元請けとの関係悪化を懸念する方も多いことでしょう。
未払い代金はどのような手順で回収するのか。関係を壊さずに回収する方法はあるのか。将来のトラブルを防ぐにはどうすればよいのか。解説します。
この記事の要約
- 元請けの未払いは、「元請けによる不当な取引慣行」「書面契約の不徹底」「元請けの経営悪化」という3つの要因が複合的に絡み合って発生する。国土交通省の調査では、92.3%の元請けが何らかの不適正な取引を行っている。
- 未払い回収は「証拠収集」「内容証明」「交渉」「法的措置」の4ステップで進めるのが確実。
- 工事代金の請求権には時効があり、知った時から5年で消滅するので早めの対応が必要。無料の公的機関(建設工事紛争審査会など)も活用できる。
そもそも元請けの未払いが起こる原因は?
元請けの未払いは、「元請けによる不当な取引慣行」「書面契約の不徹底」「元請けの経営悪化」という3つの要因が複合的に絡み合って発生します。
元請けによる不当な取引慣行
元請けが優越的な立場を利用し、不当に低い金額での契約や価格転嫁の拒否を行うことで、未払いや不当な低額での支払いが発生します。
国土交通省の令和4年度「下請取引等実態調査」によると、調査対象の9,261業者のうち、すべての項目で適正な取引を行っていると回答した業者はわずか7.7%でした。つまり、92.3%の元請けが何らかの不適正な取引を行っている実態が明らかになっています。
具体的には、以下のような不当な取引が行われています。
- 資材価格高騰への協議拒否:資材価格が高騰しても、請負代金の変更協議に応じない
- 一方的に低い金額での契約:下請けの見積もりを無視し、元請けの言い値で契約を強要する
- 労務費の価格転嫁拒否:人件費の上昇を請負代金に反映させない
- 追加工事の未払い:追加工事を指示しながら、「契約にない」として支払いを拒否する
元請けの立場が強い建設業界では、下請けは「次の仕事がもらえなくなる」ことを恐れ、不当な条件でも受け入れざるを得ないケースが多く見られます。
公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、労務費や資材価格のコスト上昇分を下請価格に反映しない行為は、優越的地位の濫用や下請代金支払遅延等防止法上の「買いたたき」に該当する可能性があるとして、監視を強化しています。
出典:国土交通省「下請取引等実態調査」
出典:公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」
書面契約の不徹底
書面による契約や証拠の管理が不十分だと、未払いが発生した際に「言った言わない」の水掛け論となり、回収が困難になります。
建設業法第19条では書面による契約が義務付けられています。しかし実際には、以下のような不備が見られます。
- 契約書の不備・未作成:口約束や簡略化された契約書で工事を開始してしまう
- 追加工事の口約束:現場判断で追加工事を口頭で合意し、書面化しない
- 証拠書類の未整備:作業日報、現場写真、完成報告書などの記録が不足している
工事内容、請負代金の額、支払期日、遅延損害金の規定などが不明確だと、未払いが発生しても客観的に証明できません。書面不備による立証の困難性は、建設工事紛争審査会でも多くの事例が報告されています。
出典:国土交通省「建設工事紛争審査会」
元請けの経営悪化
元請けの資金繰りが悪化すると、下請けへの支払いが突然滞ります。建設業界では、経営悪化による未払いが頻発している実態があります。
帝国データバンクが2025年1月に発表した「建設業倒産動向調査(2024年)」によれば、2024年の建設業倒産件数は1,890件に達し、過去10年間で最多を記録しました。2023年の倒産件数は前年比38.8%増という急増であり、2000年以降で最大の増加率です。
倒産の内訳を見ると、従業員10人未満の小規模事業者が全体の92.2%を占めています。業種別では、職別工事(大工、とび、内装など)が879件、設備工事(電気、管工事など)が411件となり、いずれも過去10年で最多です。専門工事業者、つまり下請けの倒産が大半を占める構造が明確になっています。
倒産の主な要因は、資材価格やエネルギー価格の高騰による「物価高倒産」が250件、従業員の退職や採用難による「人手不足倒産」が99件です。建設業の価格転嫁率(コスト増を販売価格に反映できた割合)は43.7%にとどまり、コスト増の半分以上を元請けまたは下請けが自社で吸収している実態が明らかになっています。
元請けが施主への価格転嫁に失敗し、同時に下請けへのコスト転嫁も不十分な場合、元請けの資金繰りは直接的に悪化します。下請けへの支払いは後回しにされ、最悪の場合は倒産により回収不能となります。
元請けの経営体力に起因するため予測が困難ですが、こうした兆候を見逃さないことが重要です。
出典:帝国データバンク「建設業倒産動向調査(2024年)」
元請けの未払いを回収する方法
未払い代金の回収は、「証拠収集」「内容証明」「交渉」「法的措置」という4つのステップを着実に進めることが確実な道筋です。
建設業法第24条の5では、特定建設業者が下請代金を工事引き渡し日から50日以内に支払う義務を定めています。違反時には年14.6%の遅延損害金を請求できます。法的根拠に基づき、以下の手順で回収を進めましょう。
ステップ1:全ての証拠を集める
回収の成否を分ける最も重要な準備は、工事の事実と未払いを客観的に証明する証拠を集めることです。
交渉や法的措置のいずれでも、証拠がなければ主張は認められません。以下の証拠を徹底的に集め、整理してください。
- 契約書、発注書、請書
- 見積書、請求書、領収書
- メールやビジネスチャット
- 作業日報、作業報告書、現場写真
- 完成引渡証明書、工事完了報告書
- 会計帳簿、銀行口座の取引履歴
証拠は、訴訟時に立証困難になるリスクを低減します。
出典:国土交通省「建設工事紛争審査会」
ステップ2:内容証明郵便で支払いを催促する
証拠を集めた後、内容証明郵便を送付し、支払いを催告した事実の証拠を残すことが法的な第一歩となります。
内容証明郵便は、郵便局が「いつ、どのような内容を、誰が誰に差し出したか」を公的に証明する書面です。単なる催促状とは異なり、法的な効力を持ちます。
内容証明郵便の主な目的は以下の3点です。
- 催告の事実を証拠化:後の裁判で「催促したが支払われなかった」ことを客観的に証明できます。
- 時効の完成猶予:内容証明による催告は、時効の進行を一時的に止める効果があります。
- 心理的プレッシャー:弁護士名義で送付すれば、元請けに強い心理的圧力を与え、支払いを促せます。
記載すべき内容は、未払い代金の金額、支払期日、遅延損害金、指定期日までに支払いがない場合の法的措置の可能性などです。法的な不備をなくすため、弁護士に依頼して作成・送付することを推奨します。
ステップ3:交渉と合意形成を目指す
内容証明送付後に元請けから連絡があった場合、まずは交渉による解決を目指すことが、時間や費用、今後の関係性を考慮すると有効です。
交渉の際は、一括払いが難しい場合、分割払いを提案するなど現実的な落としどころを探ることで回収の成功率が上がります。
ステップ4:法的措置に移行する
交渉が決裂した場合、最終手段として「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」といった法的措置に移行し、裁判所の強制力を伴う解決を図ります。
| 項目 | 支払督促 | 少額訴訟 | 通常訴訟 |
|---|---|---|---|
| 対象金額 | 制限なし | 60万円以下 | 制限なし |
| 費用 | 比較的安い | 安い | 高い |
| 期間 | 短い(異議なしなら1〜2ヶ月) | 短い(原則1回で結審) | 長い(数ヶ月〜数年) |
| 手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 比較的簡単 | 複雑(専門知識必要) |
| 回収の強制力 | 確定すれば強制執行可能 | 確定すれば強制執行可能 | 確定すれば強制執行可能 |
| 相手の異議 | 通常訴訟に移行 | 通常訴訟に移行 | 継続して審理 |
ケース別の推奨手段は以下の通りです。
- 60万円以下で相手が争わない見込み:少額訴訟が最適です。原則1回の審理で解決し、時間と費用を抑えられます。
- 証拠は揃っているが関係性を壊したくない:支払督促が有効です。書面手続きが中心で、出廷する必要がありません。ただし異議が出れば通常訴訟に移行します。
- 高額で争点も複雑:通常訴訟が最終手段となります。時間と費用はかかりますが、弁護士の力を借りて確実な回収を目指せます。
- 相手が支払いを拒否:通常訴訟が適切です。弁護士と密に連携し、長期戦も視野に入れて準備を進めます。
いずれの方法も、まずは弁護士に相談し、自身の状況に最適なアドバイスを受けることが重要です。
未払い工事代金の回収に時効はある?
工事代金の請求権には時効があります。2020年4月の民法改正により、時効期間は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」に統一されました。
工事代金の未払いを回収する上で、時効は特に注意すべき要素です。2020年4月1日施行の改正民法により、工事請負代金のような債権の時効は、以下のいずれか早い時点で完成します。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間
- 権利を行使できる時から10年間
なお、2020年3月31日以前に発生した債権には、改正前の民法が適用され、時効は3年です。
期間が過ぎると、元請けが時効を主張した場合、請求は法的に認められなくなります。
ただし、時効の完成を猶予・更新する方法があります。
- 催告:内容証明郵便を送付することで、一時的に時効の完成を6ヶ月間猶予できます。
- 裁判上の請求:訴訟を提起することで時効は更新され、判決確定日から新たに時効が進行します。
- 債務の承認:元請けが未払い代金の存在を認めたり、一部を支払ったりすることで、時効は更新され、承認時点から新たに時効が進行します。
時効が迫っている場合は、特に迅速な対応が必要です。早めに専門家へ相談し、適切な措置を講じてください。
元請けの未払いを無料で相談できる公的機関
未払いに関する相談は、まず無料で利用できる「建設工事紛争審査会」や「建設業駆け込みホットライン」といった公的機関を活用することが初期段階として適しています。
建設工事紛争審査会
裁判外での迅速な解決を目指す準司法的な機関です。建設工事の請負契約に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁で解決を支援します。法律や建築の専門家が委員を務め、公正な解決を促します。
未払い代金のほか、工事の欠陥、工期の遅延など建設工事全般の紛争が対象です。裁判に比べて費用や時間を抑えられ、実際に調停等で回収に至った事例もあります。
出典:国土交通省「建設工事紛争審査会」
国土交通省「建設業駆け込みホットライン」
建設業法違反の疑いのある行為について、匿名での情報提供や相談が可能です。元請けからの不当な要求や未払い、その他建設業法違反行為全般が対象です。
法令違反の疑いがある場合、国土交通省や都道府県が立ち入り検査や指導・監督処分を行います。
出典:国土交通省「建設業駆け込みホットライン」
将来の未払いを防ぐ方法
将来の未払いを防ぐには、「契約書の徹底」「追加工事の書面化」「取引先の与信管理」といった予防策をあらかじめ講じておくことが不可欠です。
契約書で確認すべき5つのチェック項目
契約書の不備は未払いトラブルの最大の原因です。「工事内容」「請負代金と支払期日」「遅延損害金」「契約不適合責任」「紛争解決条項」の5項目を契約時に必ず確認してください。
建設業法第19条で書面契約が義務付けられていますが、実務では口頭の約束や不完全な契約書が使われがちです。以下の5項目を確認し、必要に応じて修正を求めましょう。
- 工事内容の明確化:工事の範囲と内容を詳細に記述してください。曖昧な表現は避け、図面や仕様書を添付することも有効です。
- 請負代金の額と支払期日:総額、各工程の支払額、具体的な期日を明記します。
- 遅延損害金の規定:支払いが遅れた場合の遅延損害金(年14.6%)を明記し、請求根拠を確保してください。
- 契約不適合責任の範囲:工事に不具合があった場合の補修責任の範囲や期間を明確にします。
- 紛争解決条項:紛争発生時の裁判所や協議のプロセスを定め、スムーズな解決につなげます。
国土交通省が推奨する「建設工事標準請負契約約款」を参考にすることで、より適正な契約書を作成できます。契約書作成に不安がある場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼してください。
追加工事・仕様変更は書面で合意する
追加工事や仕様変更は、金額や内容に関わらず、必ず書面で合意を交わすことが未払い防止の鍵です。
建設現場では追加工事や仕様変更が頻発します。しかし現場の緊急性や取引先との関係性を優先し、口約束で進めてしまうことが多く見られます。口約束のまま作業を進めた結果、後のトラブルの原因となります。
- 追加工事合意書の作成:元の契約書とは別に、追加工事の内容、追加料金、納期への影響、支払い条件を記載した合意書を都度作成してください。双方で署名・捺印を行います。
- メールやビジネスチャットの活用:書面作成が間に合わない場合でも、追加工事の内容や料金の合意をメールやチャットで記録します。やり取りも法的な証拠となります。
口約束で済ませる業界慣習が、トラブルの温床です。書面で残す習慣に変えるだけで、未払いリスクは大幅に低減できます。
資金繰りが怪しい元請けの危険なサイン
取引先の経営状況を把握し、危険なサインを見逃さないことが予防につながります。
以下のようなサインが見られた場合は注意が必要です。
- 支払遅延の頻発:何度も支払いが遅れる、または催促で初めて対応するケースは要注意です。
- 担当者の交代が激しい:優秀な人材の離職や社内の混乱を示すサインです。
- 業界内での悪評:仕入れ先への支払い遅延などの情報が入ったら警戒してください。
- 急な追加発注の増加:手元資金を増やすための無理な受注の可能性があります。
- 手形払いの増加や長期化:現金払いを避けようとする兆候です。
危険なサインが見られたら、新規の大型案件は慎重に検討するか、手形取引の条件を見直してください。帝国データバンクなどの信用調査会社を活用し、定期的に与信管理を行うことも有効です。
元請けの未払いに関するよくある質問
元請けが倒産したらどうなる?
回収は非常に困難になりますが、裁判所への債権届提出により配当を受けられる可能性があります。早急に弁護士に相談し、状況を確認してください。
60万円以下の少額でも回収できる?
60万円以下の場合、1日で審理が終わる「少額訴訟」を利用できます。費用も比較的安く、ご自身で手続きすることも可能です。
関係を悪化させずに回収するには?
まずは感情的にならず、支払遅延の理由を丁寧に確認してください。交渉が難しい場合は弁護士を代理人に立てることで、直接的な対立を避けつつ解決を目指せます。
まとめ
元請けの未払いは、正しい手順を踏めば回収できます。証拠収集から法的措置まで、段階的な方法で対処することが可能です。しかし、そうした問題を根本的に防ぐもう一つの選択肢が、不当な取引を行う元請けではなく、公正に取引できるプラットフォームで仕事を受けることです。
Web集客プラットフォーム「ミツモア」を活用し、透明性のある取引で安心して働く建設業者がたくさんいます。
事例:二幸自動車

登録前の状況
ディーラーや修理工場の下請けとして30年程経験を積んできました。しかし、作業代から何割か紹介料が引かれてしまい、元請け側の都合やスケジュールに合わせる大変さもありました。下請け依存ではなく独自に営業・集客したいと考えていた時、ミツモアに出会いました。
登録後の変化
2021年9月に登録してから、月10件程の成約をコンスタントに得られています。ミツモアの一番のメリットは、大阪市近辺だけでなく、奈良や神戸など近畿圏の広い範囲で顧客を探せることです。地域の同業者との兼ね合いが難しかったという悩みが無くなりました。条件を設定しておけば、あとは自動で見積もり提案がお客様に届くので便利です。月額固定費ではなく成約に対する課金という点も経営に有利です。
関連記事:「固定費無料で見積もりが自動化できるミツモア。反響営業で月平均10件の成約&広域の集客力も魅力」
ミツモアへの登録は完全無料です。今の元請けからの仕事と両立しながら、ミツモアの案件を組み合わせることで、不当な取引や未払いのリスクから解放されます。
関連記事
Stickyハウスクリーニング
【フジテレビ newsイット!取材】月間成約250件! 最大5社から見積もりが届くミツモアは依頼者が比較して選びやすく、事業者にもメリットになっています
ミツモアは見込み顧客と出会える集客プラットフォームです。