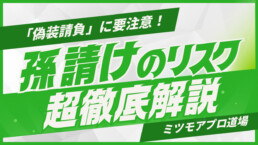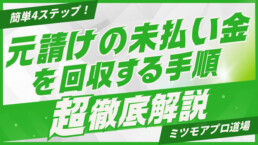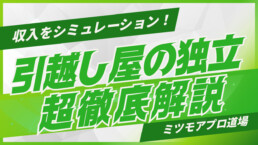リスクや資金ゼロで下請けから脱却する方法は?成功事例と元請けの仕事を続けながら始める全ノウハウ
価格を自分で決められず、元請けの都合でスケジュールが決まり、突然仕事がなくなるリスクを抱えながら働く。多くの下請け事業者がこのような状況に置かれています。「営業力を強化する」「ホームページを作る」といった一般論は脱却できません。しかし、資金も人も時間も限られた一人親方でも実践できる段階的な脱却方法は存在します。この記事では、初期費用ゼロで始められる集客方法、適正価格の決め方、そして段階的な脱却の手順を解説します。
この記事の要約
- 初期費用ゼロで始められる集客方法が7つあり、マッチングサイトなら営業経験がなくても登録3ヶ月で月120件の成約を実現した事例があります
- 料金設定のポイントは「最低限のコスト」「相場」「あなたの強み」の3つで決まり、最安値でなくても受注できます
- 下請けを続けながら直接受注を10〜20%から始め、段階的に比率を高めることでリスクを抑えて脱却できます
そもそも下請けとは
下請けとは、元請け企業から仕事の一部または全部を受託して業務を行う事業形態であり、価格や納期などの条件は元請けによって決定されます。
元請けと下請けの違いは、受注先、価格決定権、スケジュール調整権、リスクの種類にあります。
| 項目 | 元請け | 下請け |
|---|---|---|
| 受注先 | エンドユーザー | 元請け企業 |
| 価格決定権 | あり | なし |
| スケジュール | 自分で調整可能 | 元請けの都合に従う |
| リスク | 集客リスク | 契約終了リスク |
| 顧客との関係 | 直接構築 | 元請けを通す |
具体例として、エアコン設置では家電量販店が元請け、実際に現場で作業する電気工事業者が下請けです。顧客は量販店に依頼し、料金も量販店が設定しますが、設置作業は下請け業者が担当する仕組みとなっています。
下請けのメリットとデメリット
下請けには仕事の安定というメリットがある一方、利益が出ない、スケジュールを自由に決められない、特定の元請けへの依存により経営が不安定になるというデメリットが存在します。
下請けのメリット
仕事が安定する
元請けから継続的に仕事をもらえるため、営業活動なしで一定の収入を確保できます。技術力が評価されている場合、長期的に仕事量が見込めます。
営業をしなくてよい
集客、見積もり対応、顧客との交渉にかかる時間と労力を省けます。技術や作業に集中できるため、効率的に働けます。
下請けのデメリット
利益が出ない
多重下請け構造では中間マージンが何度も差し引かれ、実際に受け取る金額は大幅に減少します。価格決定権がないため、原材料費や人件費の上昇分を価格に転嫁できません。
公正取引委員会は下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づき、買いたたき、支払遅延、受領拒否など11の禁止行為を規制しています。とはいえ、年間数千件の違反疑いが報告されており、不当な取引は依然として存在します(出典:公正取引委員会, https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html)。
精神的プレッシャーがかかる
元請けに迷惑をかけてはいけないという大きなプレッシャーがあります。施工失敗時の最終責任は元請けにあるため、この状況が精神的な負担になります。
スケジュールを拘束される
仕事の予定を自分で選べません。元請けから案件を詰め込まれ、休みを取りにくい状況に陥ります。
経営リスクが集中する
売上の大部分を特定の元請けに依存している場合、経営方針変更や業績悪化により、長年続いた取引が突然打ち切られるリスクが存在します。コロナ禍では、発注停止により経営危機に陥った企業が多数発生しました。
下請けから脱却できない理由
下請けから脱却できない理由は、営業方法がわからない、営業活動をする資金・人・時間が足りないという2点です。
営業ノウハウがない
元請けから仕事をもらっていたため、自分で顧客を獲得する方法がわかりません。
ホームページを作るのか、チラシを配るのか、SNSをやるのか。情報は溢れていますが、自分の業種・地域・状況に合った方法を見つけるのは簡単ではありません。会社員から独立した人や、異業種からフランチャイズに加盟して技術を学んだ人は、営業経験がないケースがほとんどです。
顧客との交渉、ヒアリング、仕事前の調整といった営業活動を一度もやったことがない状況から、営業を始めるのは大きなハードルとなります。
資金・人・時間がない
営業活動をするためのリソースが不足しています。
ホームページ制作には10〜50万円、Web広告には月数万円の費用がかかります。フランチャイズでは手数料が40〜70%も取られていた経験から、初期投資や固定費への抵抗感が強い人も多くいます。一人親方の場合、営業担当を雇う余裕はありません。
自分が現場に出ている間は営業活動ができないという物理的制約もあります。下請けの仕事で毎日現場に出ており、集客活動に時間を割く余裕がないという状況です。
下請けから脱却する方法【集客編】
下請けから脱却するための集客方法は、マッチングサイト、友人への声かけ、チラシ、SNS、営業担当の雇用、ホームページ、Web広告の7つがあり、必要な資金・人員・時間によって取り組みやすさは大きく異なります。
マッチングサイトに登録する
マッチングサイトは、初期費用やWeb知識が不要で、成約時にのみ手数料を支払う仕組みであるため、資金、人員、時間といったリソースが限られる個人事業主から組織まで、最もリスクなく元請け集客を試せる方法です。
サイトによって特徴は異なりますが、多くは顧客の依頼や案件が通知され、それに対して見積もりを提案する仕組みです。広告費の前払いや固定費が不要で、仕事が決まった時だけ、相場として成約額の10〜20%程度の手数料を支払うため、集客コストをかけられない方でも安心して始められます。下請け時代よりも利益率の高い仕事を獲得できることが何よりのメリットでしょう。
ミツモアのようなサイトでは、登録直後で実績がなくても最大5社の競合と並んで見積もりを提案できるため、新規参入者でも平等に案件獲得のチャンスがあります。
友人・親戚・近所に声をかける
友人・親戚への声かけや地域の掲示板投稿は、金銭コストゼロで最初の1〜2件の実績作りに繋げられますが、その成果はどれだけ手間や時間をかけたかに大きく左右されます。
この方法は、コストがかからない反面、時間をかけることが成果に直結します。例えば、友人や親戚にLINEで一斉送信するだけでなく、可能な限り直接会う時間をもらい、なぜ独立したか、どんな仕事ができるかを丁寧に説明する手間が、信頼を生み紹介に繋がります。
また、地域の掲示板やジモティーも、投稿して終わりにするのではなく、定期的に内容を更新・管理する時間をかけることで反響の可能性が高まります。ただし、継続的な集客にはならず、知り合いとの金銭トラブルを避けるため、他人相手以上に契約書などを交わす覚悟が必要です。
チラシ・ポスティングをする
チラシ・ポスティングは、印刷、デザイン、配布といったコストをかけて特定エリアの住民に能動的にアプローチできるため、商圏を絞って地域内での認知度を高めたい場合に最適な手法です。
まず、A4サイズのチラシをデザインします。自分で作成するか、外注する場合は1〜3万円程度の費用がかかります。次にネット印刷などで印刷し、配布します。自分でポスティングするか、業者に外注する場合は1枚3〜10円程度の費用がかかります。
反響率は1万枚で数件程度と低いですが、Webが届きにくい高齢者層にもアプローチできるのが強みです。いきなり大部数を刷るのではなく、500〜1000枚の少量から始め、配布エリアやデザインの反響をテストしながらその地域での勝ちパターンを見つけ出すことが成功の鍵です。
営業担当を雇う
営業担当の雇用は、月給20〜30万円以上の固定費を払える事業者が、待ちではなく攻めの集客を組織的に行いたい場合に最適な選択肢です。
この方法が最適なのは、人件費を払える、かつ、社長自身が現場作業と見積もり対応でパンクしており、営業活動がボトルネックになっているような事業者です。自分が現場に出ている間も営業活動が継続できるため、売上の天井を突破できる可能性があります。
ただし、案件が取れるか不明な人件費に加え、営業担当者をマネジメントするコストも発生します。売上が安定し、固定費を払える事業規模になってから検討すべき方法です。
ホームページ・SEO対策
ホームページ・SEO対策は、成功すれば広告費ゼロで集客し続ける資産となるため、即効性よりも長期的な仕組みを構築したい場合に最適な投資です。
上位表示されれば継続的に問い合わせが来ますが、制作費として10〜50万円程度の初期投資と、成果が出るまで半年から1年ほどの期間がかかります。
Web知識がある人は、自分で制作・運用できますが、成果が出るまで自分の時間を膨大に投下する覚悟が必要です。外注費がある人は、時間を買うことができますが、本当にSEOに強い業者を見極める目利きがないと、費用をドブに捨てるリスクがあります。
Web広告を出す
Web広告は、SEOと違って成果が出るまで待つ必要がなく、今すぐ客が欲しいというニーズに対して、予算を使って最速でアプローチできる即効性が最適な手法です。
Google広告やSNS広告は、月数万円の予算からでもターゲットを絞ってアプローチできます。広告費を止めると集客も止まるという依存性はありますが、裏返せば、予算の蛇口をひねれば、いつでも集客をコントロールできるのが強みです。
継続的な広告費を払える人は、自分で運用知識を学ぶだけでなく、運用代行の外注に任せて時間を買い、自分は本業に集中するという選択も可能です。
下請けから脱却する方法【価格設定編】
適正価格は、コスト、相場、付加価値の3要素を踏まえながら設定します。見積もりの内訳を明確にし価格以外の価値を伝えることで価格競争を避けることができます。
適正価格の決め方
適正価格を決める際の3要素は、最低限かかるコスト、同業他社の相場、そしてあなたならではの付加価値です。
下請け時代は元請けから指値で発注されていたため、仕事の価値という感覚が育ちにくい環境だったかもしません。
- コスト:材料費、交通費、人件費など最低限かかる費用を算出します。これを下回る価格設定は事業の継続性を損ないます。
- 相場:同業他社がどれくらいの価格で提供しているかを調査します。相見積もりの仕組みがあるサイトでは、他の事業者が提示している金額がわかるため、料金設定の参考になります。
- 付加価値:丁寧さ、スピード、アフターフォローなどの強みを加味します。
なお、ミツモアの成約データでは、最安値ではなく中程度の価格帯が最も選ばれやすいことが分かっています。極端に安い価格は品質への不安を与えます。一方で、極端に高い価格は割高感を与えます。相見積もりで自社より安い業者がいるにもかかわらず受注に至るケースもあり、これは口コミ評価や地元の安心感が理由です。
(出典:ミツモア, https://pro.meetsmore.com/posts/all/79595)。
見積もりの作り方
わかりやすい見積もりは、内訳の明確化、作業内容の具体化、複数オプションの提示という3要素で構成されます。
内訳を分けて記載することで、顧客は価格の妥当性を理解しやすくなります。曖昧な表現は避け、具体的な作業項目を列挙します。予算に応じた複数のプランを用意することで、顧客の選択肢を広げ成約率が向上します。
価格競争を避けるコツ
価格競争を避けるには、アフターサービス、保証期間、迅速な対応、丁寧な説明、地元密着、追加提案という価格以外の価値を明確に伝えることです。
複数の案を提示し、顧客の予算や状況に応じて選べるようにすることも有効です。不要な作業を排除した明朗会計により、価格の透明性が高まり顧客の信頼を獲得できます。
下請けから脱却する方法【顧客対応編】
顧客対応において、口コミの蓄積とリピート客の獲得が継続的な直接受注を実現する鍵となります。
口コミを集める
口コミは新規顧客があなたを選ぶ最大の判断材料であり、作業後の依頼と丁寧な返信により蓄積できます。
ミツモアでは口コミ投稿がサービス体験の一部として組み込まれているため、他のサイトよりも集まりやすくなっています。
実際の口コミから、顧客が評価するポイントがわかります。例えば、酷暑の中、ありがとうございました、来て下さった方のお人柄も良く仕事も丁寧で、とても綺麗にクリーニングしていただきました、という評価からは、技術力だけでなく人柄と配慮が印象に残ることが読み取れます。
実際に、このような顧客視点の姿勢がリピートや紹介につながっています。(出典:ミツモア, https://pro.meetsmore.com/posts/all/79600)。
リピート客を増やす
リピート客を増やすには、作業後のフォロー、定期点検の提案、メンテナンス情報の提供という3つの方法があります。
一度仕事をした顧客に再度依頼してもらうことが、最も効率的な集客方法です。技術的な施工だけでなく予防方法など追加情報を提供することで、顧客教育を行い高評価を獲得できます。
返信スピードを速くする
問い合わせ直後は顧客の熱意が最も高く、他社と比較検討しているため、迅速な返信が成約率を大幅に高める鍵となります。
顧客はスマートフォンなどから複数の事業者に同時に問い合わせ、即座に比較検討しているケースが一般的です。返信が遅れると、その間に熱意が冷めたり、先に返信があった他社に決めてしまう可能性が高くなります。
ミツモアでも問い合わせから30分以内に返信することで、成約率は2.6倍に上昇することがわかっています。
| 返信時間 | 成約率の変化 | 顧客の心理状態 |
|---|---|---|
| 30分以内 | 2.6倍 | 熱意が最高潮 |
| 1時間以内 | 1.8倍 | 複数社を比較 |
| 3時間以降 | 基準値 | 他社に決定済み |
※出典:ミツモア, https://pro.meetsmore.com/posts/all/81185
現場作業中などで、すぐに見積もりや詳細な回答ができない場合でも、例えば「お問い合わせありがとうございます。現在作業中のため、〇時頃に改めてご連絡いたします」といった一次返信を迅速に行うだけで、顧客に安心感を与え、他社への流出を防ぐことができます。
下請けから脱却する方法【実践ステップ編】
下請けからの脱却は、いきなり元請けの仕事をゼロにするのではなく、直接受注の売上比率を段階的に高める3つのステップを踏みながら、収入の不安や集客の失敗リスクを最小限に抑えることがポイントです。
STEP1:下請けを続けながら直接受注を始める
この最初のステップでは、下請けの仕事を安定収入として維持しつつ、週末や閑散期を利用して直接受注に挑戦します。売上の10〜20%を目標に、まずは3〜6ヶ月かけて元請けとしての経験を積むことが最優先です。
この段階の目的は、大きな売上よりも、下請け時代には不要だったお客様への見積もり提示、価格交渉、直接のやり取りといった一連の流れを経験することです。下記アクションを取りましょう。
- マッチングサイトに登録
- 友人・親戚に声かけ
- チラシを500〜1000枚試す
最初の口コミと実績を獲得し、自分でも直接仕事が取れるという自信を掴むことがこのステップでは重要です。無理に案件を詰め込まず、対応できる範囲で堅実に始めましょう。
STEP2:直接受注の比率を高める
次の移行期では、STEP1で得た経験と実績を元に、直接受注の売上比率を30〜50%まで引き上げます。この段階では、集客方法を闇雲に試すのではなく、効果のあった施策に集中投資することが重要です。
例えば、マッチングサイトで手応えがあったなら、そこでの口コミ収集を徹底的に強化します。チラシの反響が良かったなら、配布エリアやデザインを改善して追加投資します。ここでは下記のようなアクションを取りましょう。
- 既存顧客に紹介を依頼
- 口コミを積極的に収集
- 効果のあった方法を強化
- リピート客を増やす工夫
一度施工したお客様へ紹介を依頼するなど、リピートや紹介を増やす工夫も始めましょう。収益源が複数あるという精神的な安心感が得られ、価格設定にも自信が持てるようになります。なお、この段階でも、まだ元請けとの関係を急に断つ必要はありません。
STEP3:直接受注を主軸にする
最後の独立期では、STEP2で築いた集客の仕組みをさらに強化・安定させ、直接受注の売上比率を70%以上に引き上げることで、経営の主導権を完全に握ります。
ここまで来ると、下請け時代にはなかった価格決定権やスケジュールの自由度が格段に高まり、仕事のやりがいも大きく変わります。この段階では、新規集客を継続しつつ、既存顧客からのリピートや紹介を確実に獲得する仕組み作りが最重要課題となります。
具体的な行動:
- STEP2で効果のあった集客施策をさらに強化する
- 既存顧客への定期連絡やアフターフォローを仕組み化する
- 顧客基盤を確立し、リピート・紹介率を高める
- 元請けとの関係を調整する
元請けとの関係も、依存する下請けから、対等に協力しあうパートナーへと変化させることも可能です。
下請けからの脱却に成功した事例
株式会社フォレストサービス(機器設置)
課題・背景
大手家電量販店の下請けとして15年間、エアコン設置を中心に電気工事を手がけていました。繁忙期は仕事が集中する一方、秋口から冬にかけての閑散期は収入が大きく減少し、経営は不安定になります。
価格は量販店が決めるため、自分で適正価格を設定することはできません。利益率の低い仕事を続けざるを得ず、将来の収入が不安でした。
実践したこと・成果
閑散期の収入不安を解消するため、下請けを段階的に減らし、エンドユーザーからの直接受注へ切り替えることに。Web集客は初めての経験でしたが、集客サイトに登録します。その際、エアコン設置だけでなく、コンセント増設、照明工事、配線変更、インターフォン取り付けなど、電気工事全般を受注対象として幅広く明示しました。
すると、下請け時代には出会わなかった依頼がたくさん来ました。「在宅ワークでデスク配置を変えたからコンセントを30cm横にずらしてほしい」「スティック型掃除機を買ったがクローゼットにコンセントがなく充電できない」といった内容です。大手なら小さすぎると断る案件ばかりでした。町の電気屋さんが姿を消している中、ネットで検索して依頼する人が急増していることに気づきます。従来のように大手家電量販店から頂く取り付け業務を下請けしているだけだったら、わからなかったニーズでした。
こうした小さな案件でも、価格相当以上の満足感を得てもらうことを意識しました。時間内に丁寧に仕事を終え、部屋は以前よりきれいにして退出することを徹底します。この姿勢が、安い、丁寧、きれいという評価につながりました。
登録3ヶ月目には月120件の成約を達成。下請けを完全に卒業し、自分たちから攻めていける状態を実現しました。
成功の鍵
コロナ禍の在宅ワーク需要と町の電気屋さん減少という市場変化を捉え、大手が対応しない小規模案件に特化したことが最大の成功要因です。下請けでは出会えなかった顧客ニーズに直接応えることで、価格決定権と安定収入を手に入れ、下請けからの脱却を実現しました。
【成功事例】すまいる住宅設備・杉本拓也氏(水道設備工事)
独立開業前の状況
前職では売上成績ナンバーワンを記録し、水道や住宅設備のプロとして経験を積んでいました。技術には自信がありましたが、独立を決意した際、最大の課題は営業方法でした。
蛇口など水道関係の工事は、顧客と直接つながる機会が少ない業種です。会社員時代は会社が仕事を持ってきてくれましたが、独立後は自分で顧客を獲得しなければなりません。営業方法も限られており、どうやって新規顧客を開拓するかが不透明でした。
実践したこと・成果
独立後、Web集客で新規顧客を獲得することに。最初は依頼に対してどのような返信をすれば安心してもらえるのかもわかりませんでした。そこで、自分自身が依頼側の立場に立って考えてみることに。事業者側だけでなく依頼する側の気持ちを理解し、どのような対応が顧客に安心感を与えるのかを探っていきました。
仕事では、依頼された作業を完遂するだけでなく、技術にプラスαの接客を心がけました。例えば水道管の詰まりの案件では、作業後にメンテナンスについて「今後どうしたら予防できるか」といった情報もあわせて提供します。会社員時代は会社の指示通りに作業するだけでしたが、独立後は顧客の気持ちに寄り添いながら満足度を上げていく仕事を意識しました。
この姿勢が「丁寧で助かりました」「説明が細かくてよかった」といった評価につながります。独立後すぐに月二桁の成約を実現。現在は月60件近くをコンスタントに成約し、評価の大半は5つ星、口コミは170件を超えています。顧客層も20代からシニアの60代70代まで幅広く、個人顧客と入口から出口まで直接関わることで、自分の仕事の結果が未来につながる独立開業のやり甲斐を実感しています。
成功の鍵
独立開業時に顧客視点でのコミュニケーションを徹底したことが成功の要因です。会社員時代の「指示された作業をこなす」姿勢から、「顧客の満足度を最大化する」姿勢へ転換。技術だけでなく、顧客の気持ちに寄り添った+αの接客により信頼を獲得し、独立開業の成功を実現しました。
【成功事例】はなまる造園・山下健太氏(造園業)
課題・背景
2年前、軽自動車1台と草刈り機1台、スタッフ2名という小さな規模で独立開業しました。前職は通信業でしたが、庭のビジネスと出会い人生が変わり、造園業で独立することに。
独立後は大手企業の下請け案件をいただくようになり、徐々に仕事は増えていきました。下請けを含め10人以上の組織になりましたが、大手からの紹介仕事に依存している状態でした。さらに事業を拡大するため、下請け依存から脱却し、直接受注の案件を増やす必要がありました。
実践したこと・成果
下請け依存から脱却するため、Web集客で直接受注を増やすことに。庭木・造園業界向けのフランチャイズに加盟し、複数の集客サイトにも登録します。
仕事では、「三者満足」を徹底的に追求しました。顧客、紹介会社、自社の三者みんなが満足できる結果を出すことを最優先に。価格設定では、現場に足を運び庭を見て、顧客と直接話をし、どのようにしたいかを把握した上で決めていきます。顧客の懐に応じて仕事をすることもありました。とにかく低価格にこだわる方もいれば、価格より仕事内容や早さや質を重視する方もいるため、常にコミュニケーションを細かく丁寧にとって顧客満足度を得られる価格を模索しました。
顧客からの口コミ評価は「本音が見える場所」として重視します。現場では「ありがとう」「頼んでよかったです」というシンプルな言葉をいただけても、詳細に感想を聞くことはできません。しかし後日改めて口コミを読むと、何がどうよかったのかが分かり、貴重な情報になります。また「初心に戻る」機会としても活用。日々忙しくしているとつい忘れてしまう原点——一人一人の顧客と向き合って、誠実な仕事をして信頼を得ていくこと——を再確認しました。
結果、下請け以外の直接受注案件が増加。Web集客では月20件以上を成約するようになり、大手企業からの紹介仕事だけでなく、Web経由、知り合いの会社からの紹介など、さまざまな受注ルートを確保できました。職人10人超を組織し、月300件以上の案件をこなす規模に成長。社員が増え、トラックを複数台保有するまでに事業を拡大できました。
成功の鍵
下請け依存から脱却できた要因は、顧客、紹介会社、自社の「三者満足」を徹底的に追求したことです。価格だけでなく、細かく丁寧なコミュニケーションを通じて顧客満足度を最優先にする姿勢が、口コミ評価と信頼獲得につながり、直接受注ルートの多様化を実現。下請け依存から脱却し、月300件超をこなす組織への成長を達成しました。
関連記事:「「自動集客方式」を使いこなして月20件以上成約。ミツモアが若手造園業の想いを集客でアシスト」
【成功事例】安心・駆除屋さん・尾崎強氏(害虫駆除)
課題・背景
害虫駆除会社に作業員として10年間勤め、経験を積んできました。個人事業主として駆除の仕事をする方法もあるかもしれないと気付き、独立することに。以前はこの業界でネット営業など考えられませんでしたが、Webでの集客インフラが整ってきていることもわかりました。
害虫駆除の仕事経験が約10年と自信はありましたが、営業方法が課題でした。
実践したこと・成果
独立後、Web集客で新規顧客を獲得することに。複数の集客サイトに登録し、営業を開始します。
仕事では、駆除の効果を最大化するため、丁寧な事前ヒアリングを徹底しました。いつ、どこで、何回くらい虫を見かけたか、できるだけ細かく聞き取ることで発生源を特定し、的確な対策を立てます。1か月保証を付け、効果が出るまで複数回通う姿勢を徹底しました。
口コミ評価も重視。顧客が口コミ評価を書いてくださると、忙しくても一つ一つに返事を書き込むよう心がけました。
登録直後から、月20件以上コンスタントに成約できるようになり、独立当初から集客がスムーズに回りました。口コミは50件超、評価も高く、顧客の信頼を獲得できました。
成功の鍵
独立開業で成功できた要因は、駆除の効果を最大化するための丁寧な事前ヒアリングとサービス品質の追求です。発生源を特定して的確な対策を立て、1か月保証で効果が出るまで通う姿勢が信頼につながり、独立直後から月20件超の成約を実現しました。
関連記事:「業界歴10年の駆除エキスパートがミツモアの活用で開業と同時に月20件の営業を成功させた秘訣とは?」
【成功事例】株式会社YDKリノベーション・阿部裕樹氏(建具工事)
課題・背景
建具職人として数々の現場仕事をこなし、建設会社から直接請け負う仕事が大半でした。個人顧客を相手に営業をしたことはほとんどなく、Web上で個人顧客に営業すること自体が未経験でした。
建設会社経由の大規模な現場仕事から、規模の小さな仕事にシフトしたいと考えました。個人顧客相手の建具製作や修理を営業したいと思いましたが、営業方法が課題でした。
実践したこと・成果
個人顧客からの直接受注に切り替えるため、Web集客で顧客を獲得することにしました。
個人顧客との対応では、専門用語を平易な言葉に置き換えることを徹底。建設業関係者と仕事をしてきたため普通に専門用語を使っていましたが、個人顧客相手では全く事情が異なるからです。相手が知らないという前提で、「こういう場所にこういうカタチで設置すると、こんな価格になります」と工程を含め細かく説明し、複数の選択肢を提示しました。
価格の内訳を説明し、顧客の納得を得てから成約することを徹底しました。もし顧客がちょっとでも不思議な表情をしたら、説明の仕方を変えて正確に伝わるよう工夫します。希望があれば事前に無料で現地へうかがい、状態を確認しました。緊急性が高い案件も多いため、できるだけ早く対応するよう心がけます。
登録した月に20件近く成約しました。玄関ドアの修理や取り替えは、ネット上に専門職人が少なく、古いマンションでは部品が廃番になっているケースも多いため専門的な技術が求められます。結果として、月二桁の成約を継続し、大半の顧客が自発的に口コミを書いてくれるようになりました。
成功の鍵
建設会社経由の仕事から個人顧客への直接受注に成功できた要因は、専門用語を平易な言葉に置き換え、顧客の納得を最優先にしたことです。建設業関係者向けの説明から個人顧客向けの丁寧な説明へと転換し、価格の内訳や工程を細かく伝える姿勢が信頼につながり、初月から月二桁成約を継続実現しました。
関連記事:「Web集客未体験のベテラン建具職人がドア修理の稼ぎ頭に。初月から二桁成約を継続する秘訣を公開」
【成功事例】二幸自動車・福神将樹氏(車の板金塗装・修理)
課題・背景
ディーラーや修理工場の下請けとして、車の板金塗装や修理を30年程手がけてきました。下請けでは作業代から何割か紹介料が引かれてしまい、元請け側の都合やスケジュールに合わせる大変さもありました。
下請け体制だけでなく、独自に営業して職人たちの仕事を増やしていかなければと考えました。しかし、地域で飛び込み営業をすると同業者の仕事を取ることになってしまうため、新規顧客開拓の兼ね合いが難しいという課題がありました。
実践したこと・成果
下請け依存から脱却するため、Web集客で直接営業を開始することにしました。
最大の課題は、地域の同業者と競合しない形で新規顧客を開拓することでした。地域で飛び込み営業をすると同業者の仕事を取ることになってしまうからです。そこで、営業エリアを近畿圏広域に設定。大阪市近辺だけでなく奈良や神戸など広い範囲で顧客を探すことで、地域の同業者との競合を避けるようにしました。
価格競争力を確保するため、リサイクル部品を活用することに。部品交換の際、新品に比べてリサイクル部品は価格がほぼ半額で済み、作業時間も短縮できます。顧客には新品とリサイクル部品それぞれの費用を示し、予算に合わせて選んでもらうようにしました。
結果として、2021年9月の登録以降、月10件程の成約をコンスタントに獲得。従来の下請けの仕事と組み合わせながら、安定した受注を実現しました。
成功の鍵
下請け依存から脱却できた要因は、リサイクル部品活用による価格競争力と広域営業による地域競合の回避です。新品の半額程度で提供できる価格設定により、地域の同業者と競合しない形で近畿圏広域での新規顧客獲得を実現しました。
関連記事:「固定費無料で見積もりが自動化できるミツモア。反響営業で月平均10件の成約&広域の集客力も魅力」
下請け脱却のリスクと対策
下請け脱却で直面する主なリスクは、収入の不安定化、下請法の保護対象外化、営業・事務負担の増加の3つですが、成約課金制の活用、法的知識の習得、業務のデジタル化により対策できます。
脱却前に備えるべき事業リスク
下請け脱却時には、収入の不安定化、下請法の保護対象外化、営業・事務負担の増加という3つのリスクがあり、それぞれ事前に対策を講じる必要があります。
収入の不安定化
直接受注では受注の波が大きくなります。成約課金制のプラットフォームを活用することで、広告費による資金繰りの悪化を防げます。段階的な移行により、下請けの収入を維持しながらリスクを分散できます。
下請法の保護対象外となる
元請けとなった場合、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法による保護が受けられなくなります。公正取引委員会の資料によれば、下請法は買いたたき、支払遅延、受領拒否、返品、減額、不当な経済上の利益提供要請など11の禁止行為を規制しており、この法的保護が失われます。
中小企業庁の無料セミナーや商工会議所の相談窓口を活用し、契約書の作成方法、支払い条件の設定など法的知識を習得する必要があります。
(出典:公正取引委員会, https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html)。
営業・事務負担の増加
見積もり作成、顧客管理、請求業務など、これまで元請けが担っていた業務を自社で行う必要があります。クラウド型の顧客管理システムや会計ソフトの導入、自動応募機能の活用により業務を効率化できます。
活用できる公的支援制度
全国47都道府県に価格転嫁サポート窓口を設置し、下請法の厳格な運用、電子発注システムの推進という3つの支援策により下請け企業の自立を後押ししています。
価格転嫁サポート窓口
原材料費や人件費の上昇分を適正に価格転嫁するための交渉を支援しています。2022年の調査では、サポートを受けた企業の約7割が価格交渉に成功しています(出典:中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html)。
下請法の厳格な運用
公正取引委員会は年間を通じた違反調査・指導を実施しています。令和5年度には違反企業に対する勧告・指導が多数行われ、企業名も公表されています。
電子発注システム
2022年版の中小企業白書では電子発注システムが「取引の共通インフラ」として位置づけられました。振興基準の2020年改正により活用促進が明文化され、取引の透明性向上と事務負担軽減が図られています(出典:中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/chusho/b2_3_1.html)。
下請け脱却に関するよくある質問
元請けとの関係を円満に解消できる?
段階的に直接受注の比率を高めていく方法が現実的であり、繁忙期の協力など良好な関係を維持しながら自立を進めることができます。
突然の断絶ではなく、お互いにメリットのある関係への移行を目指すことです。独立後も技術協力や相互支援という新たな協業関係を構築するケースも増えています。
Web集客の知識がなくても始められる?
マッチングサイトを活用すれば、ホームページ作成やSEO対策といった専門的なWeb知識なしで直接受注を始めることができます。
成功の鍵は、IT技術ではなく、丁寧な顧客対応と迅速なレスポンス、そして顧客視点の対応です。
脱却に必要な期間と資金はどれくらい?
3ヶ月〜1年程度で直接受注の比率を大きく高めたケースがあり、成約課金制のサービスを活用すれば初期投資を抑えながら始められます。
成約課金制の場合、初期費用はほぼゼロで、仕事が決まった時だけ手数料を支払う仕組みのため、資金面のリスクを軽減できます。
まとめ
下請けからの脱却は、段階的な移行と適切な支援の活用により、多くの中小企業や個人事業主が実現可能な経営改革です。
Web集客の経験がなくても、マッチングサイトを活用して成約数を増やした事業者が多数存在します。国の支援策も充実しており、価格転嫁サポート窓口や下請法による保護など、脱却を後押しする環境は整っています。
下請け脱却ならミツモア
下請けからの脱却は、集客、価格設定、顧客対応、そしてリスク管理と、多くの課題を乗り越える必要があります。実践ステップで解説したように、下請けの仕事を続けながら最初の一件を直接受注し、元請けとしてのノウハウを蓄積するSTEP1は、最も重要かつ困難な段階です。
この最初のハードルを、最もリスクなく越えるために設計されているのがミツモアです。
チラシやWeb広告のような先行投資は一切不要。初期費用ゼロ、成約課金制であるため、万が一仕事が決まらなくても赤字になるリスクがありません。収入が不安定になりがちな脱却の初期段階において最大のメリットです。
また、ミツモアは登録直後で実績がなくても最大5社に見積もりを提案できるため、新規参入者にも平等にチャンスがあります。相見積もりの中で適正価格を学び、顧客対応を磨き、そして口コミという最大の資産を蓄積していく。これら下請け脱却に必要な全てのノウハウを、リスクなく実践できる環境が整っています。
あなたの技術を適正な価格で直接お客様に届け、脱却への第一歩を踏み出すために、まずはミツモアの仕組みを詳しくチェックしてみてください。
関連記事
Stickyハウスクリーニング
【フジテレビ newsイット!取材】月間成約250件! 最大5社から見積もりが届くミツモアは依頼者が比較して選びやすく、事業者にもメリットになっています
ミツモアは見込み顧客と出会える集客プラットフォームです。