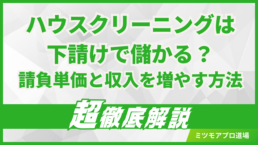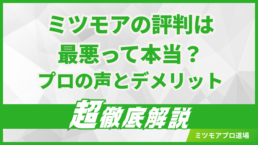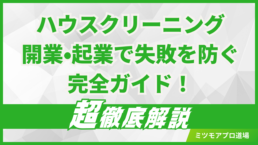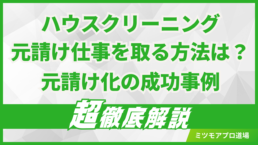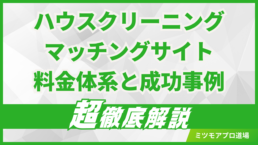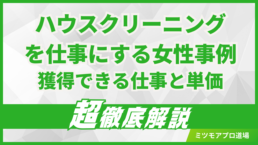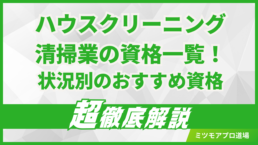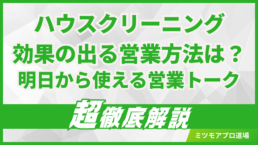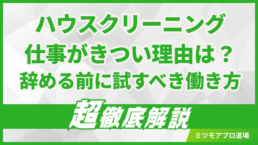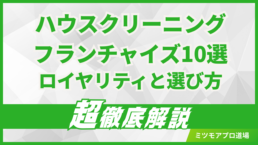ハウスクリーニングは下請けで儲かる?請負単価と収入を増やす方法
ハウスクリーニングは下請けで儲かる?請負単価と収入を増やす方法
「営業に自信がないからまずは下請けから始めたい」 「でも、下請けは単価が安くて生活できないと聞いて不安…」このようにお悩みではありませんか?
ハウスクリーニングの下請けは、自分で営業をしなくても仕事が入ってくる「安定感」が最大の魅力ですが、「単価の低さ」というシビアな現実があるのも事実です。
本記事では、下請けの単価相場や下請けのメリットとデメリットなど業界のリアルな実情を詳しく解説します。これから開業を目指す方も、現状の売上に満足できていない方も、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の要約
- 下請けは「営業不要で仕事が安定する」メリットがある一方、「単価交渉ができず収入に上限がある」のが現実です
- 空室クリーニング(1K)の単価相場は10,000円〜12,000円程度のため、収入を増やすためには工夫が不可欠です
- 下請けの仕事を維持しつつ、「ミツモア」などのマッチングサイトを併用して高単価な直接受注を増やすのが、リスクを抑えて収入を増やす最短ルートです
ハウスクリーニング下請けの仕組み
ハウスクリーニングの下請けは、元請けとなる会社が獲得した案件を、施工者として現場で作業する仕組みのことです。
下請け業者は、自分自身でチラシを配ったりネット広告を出したりする手間がない分、元請けに手数料(マージン)を支払う形で仕事をもらいます。営業が苦手な職人さんにとっては、現場作業に集中できる点が大きな特徴です。
ここからは、元請けから業務を受注する流れ、下請けで受注できる業務の種類について解説します。
元請けから業務を受注する流れ
下請けとして業務を受注するには、まず元請け企業の「協力会社」として登録し、案件の打診を待つのが一般的な流れです。
多くの場合は、元請け会社と業務委託契約を交わし、空き状況や対応エリアを伝えておきます。物件の退去が決まると、元請けの担当者から「○月○日にこの物件の清掃をお願いできますか?」と電話やメール、専用のアプリなどで連絡が入ります。
提示された単価や条件を確認して引き受けると、鍵の受け渡し場所や作業の注意点が共有され、実際の現場作業に向かうことになります。
下請けで受注できる業務の種類
下請け業者が請け負う仕事は、大きく分けて「空室クリーニング」と「ハウスクリーニング」の2種類があります。
| 業務区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 空室クリーニング | 賃貸物件の退去後・入居前清掃、新築引渡し清掃 |
| ハウスクリーニング | エアコン、浴室、キッチンなどのポイント清掃 |
下請け案件の多くを占めるのは、賃貸マンションやアパートの入居者が入れ替わる際に行う「空室クリーニング(退去後清掃)」です。空室クリーニングは、誰もいない部屋を丸ごと綺麗にする仕事で、作業の進め方を自分でコントロールしやすいのが特徴です。
一方で、大手量販店やマッチングサイト経由の下請けでは、お客様が住んでいる家にお邪魔する「ハウスクリーニング」や、特定の部位だけを洗う「エアコンクリーニング」などの案件も多く見られます。
ハウスクリーニング下請けのメリット
- 営業なしで案件を受注できる
- 安定した仕事量を確保できる
- 技術習得の場として活用できる
下請けという働き方には、個人事業主がゼロから事業を立ち上げる際のリスクを抑えられるメリットがあります。
自分で営業をする必要がなく、現場の仕事に専念できる環境は、技術一本で勝負したい職人さんにとって大きな支えとなります。
下請けだからこそ得られる具体的な3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
営業なしで案件を受注できる
下請けとして働く最大のメリットは、自分自身で仕事を探し回る必要がないことです。
本来であれば、チラシを配ったりホームページを運用したりといった営業活動には、多くの時間とお金がかかります。しかし下請けであれば、元請け会社から「次はここをお願いします」と連絡が来るのを待つだけで仕事が入ります。
営業が苦手な方や、集客のための資金が十分にない方でも、登録したその日からプロとしての売上を立てられるのは非常に大きな魅力です。
安定した仕事量を確保できる
特定の元請け会社と信頼関係を築くことで、年間を通じて安定した仕事量を確保しやすくなります。
特に不動産管理会社などは、引越しシーズン以外でも退去物件が定期的に発生するため、仕事が途切れる不安が少なくなります。大手企業の看板で集客した案件を回してもらえるため、自分で一件ずつ集客するよりも圧倒的に仕事の数が安定します。
「来月の予定が真っ白」という恐怖を感じることなく、決まったスケジュールで働き続けられるのは、家族を養う個人事業主にとって精神的な安心感に繋がります。
技術習得の場として活用できる
下請けとして数多くの現場をこなすことは、あなた自身の清掃技術を磨く「最高の修行場」にもなります。
特に大手フランチャイズの下請けでは、マニュアル化されたレベルの高い技術を現場で学ぶことができ、自分の腕を短期間で上達させることが可能です。自分一人では出会えないような特殊な汚れや、様々なメーカーのエアコンに触れる機会も多いため、対応力が自然と身についていきます。
将来的に直接受注を目指す場合でも、下請け時代に培った圧倒的な現場経験とスピード感は、お客様に選ばれるための強力な武器となります。
ハウスクリーニング下請けのデメリット
- 単価交渉の余地がほとんどない
- 元請けの都合で契約終了のリスクがある
- 収入の上限が見えてしまう
下請けという働き方にはメリットがある一方で、自分の力だけでは解決しにくい厳しい現実も存在します。
特に収入面や将来的な安定性を考えると、下請けだけに頼り切ることのリスクもしっかりと把握しておく必要があります。
これら3つのデメリットについて、現場のリアルな実態を交えて解説します。
単価交渉の余地がほとんどない
下請け仕事の最も大きな悩みは、自分から「単価を上げてほしい」と伝えるのが非常に難しい点にあります。
元請け会社は、あらかじめ決まった予算の中で利益を出そうとするため、下請けに提示する金額は最初から低めに固定されていることがほとんどです。どれほど丁寧に、どれほど綺麗に仕上げたとしても、「1Kなら1万円」といったルールが変わることは滅多にありません。
それどころか、元請けの経営状況によっては、突然「来月から単価を下げてほしい」と一方的な通告を受けることもあり、交渉の余地がないまま受け入れざるを得ないのが現状です。
元請けの都合で契約終了のリスクがある
下請け業者は、元請け会社にとって「外注先」の一つに過ぎないため、いつ仕事が打ち切られてもおかしくないリスクを常に抱えています。
例えば、元請けが別の安い業者を見つけた場合や、元請け自体の経営が悪化して倒産してしまった場合、あなたの仕事は一瞬でゼロになってしまいます。特定の1社だけに依存して働いていると、その会社との契約が切れた瞬間に収入が完全に途絶えてしまうため、非常に不安定な状態といえます。
自分の落ち度ではなく、相手の会社の都合で生活が左右されてしまう点は、下請けという働き方の大きな弱点です。
収入の上限が見えてしまう
下請けの仕事は単価が安く、自分の体一つで動ける時間には限界があるため、稼げる金額にどうしても天井(上限)ができてしまいます。
1件あたりの単価が1万円で、1日2件こなすのが限界だとすれば、どれだけ頑張っても日給は2万円です。ここからガソリン代や洗剤代、車の維持費などを引くと、手元に残るお金はさらに少なくなります。
毎日休みなく働けば月収を増やすことはできますが、それでは体を壊してしまい、結局は長く続けることができません。下請けという仕組みの中にいる限り、爆発的に収入を増やすことは難しく、将来への不安を完全に消し去ることは容易ではありません。
ハウスクリーニング下請けの単価相場
| 間取り | 広さ(目安) | 下請け単価相場 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 〜20㎡ | 10,000円〜12,000円 |
| 1LDK・2DK | 〜40㎡ | 18,000円〜25,000円 |
| 2LDK・3DK | 〜60㎡ | 25,000円〜35,000円 |
| 3LDK・4DK | 〜80㎡ | 35,000円〜45,000円 |
ハウスクリーニングの下請け案件のなかでも特に気になるのが「実際のところ、1件いくらで請け負うのか?」という下請け単価の現実ではないでしょうか。
ここからは、主に空室清掃(退去後の原状回復クリーニング)」に焦点を当て、標準的な単価相場を紹介します。
提示する金額はあくまで「売上の単価」です。ここから駐車場代やガソリン代、洗剤代などの経費が引かれることを念頭においてください。
1Kの単価相場
1Rや1Kといった単身者向けの物件では、下請け単価は10,000円〜12,000円程度が相場となります。
この価格帯は業界内で「1万円の壁」とも呼ばれており、東京都内であっても大きく上昇しにくい現状があります。エンドユーザー価格が15,000円〜25,000円であることを考えると、元請けの手数料は約30%〜50%にのぼります。
移動時間や洗剤などの消耗品費用を差し引くと、1件あたりの利益は決して多くありません。そのため、1日に2件から3件の現場を効率よく回ることで、日当を確保する動き方が求められます。
2LDKの単価相場
ファミリー層向けの2LDKや3DK(約60㎡)の物件になると、単価は25,000円〜35,000円程度に上がります。
作業範囲が広くなる分、1Kのように短時間で終わらせることは難しくなります。通常、一人で作業した場合は丸一日、あるいはそれ以上の時間がかかることもあるため、時間対効果を冷静に見極める必要があります。
3LDK以上の単価相場
3LDKや4DK、あるいは一戸建てなどの大型案件では、単価は35,000円〜45,000円以上となります。
広さが80㎡を超えるような物件では、一人で作業を完了させるには限界があるため、応援のスタッフを呼ぶなどの体制づくりが必要です。外注費を支払うと手元に残る利益が薄くなるため、受注前に「何人体制で何日かかるか」を正確に見積もらなければなりません。
ハウスクリーニング下請けの収益性
単価が分かったところで、次に重要となるのが「手元にいくら残るのか」という収益性の視点です。
下請け仕事は、売上から経費や税金を差し引くと、実質的な利益率は売上の半分程度になるのが業界の標準的な目安です。
経費の内訳や利益計算、そして月間で目指せる収入の目安について詳しく見ていきましょう。
作業にかかるコスト
1つの現場を完了させるためには、薬剤や消耗品だけでなく、移動に伴うコストも発生します。
具体的には、洗剤や雑巾、スポンジなどの資材費で1,000円〜2,000円、現場までのガソリン代や駐車場代で500円〜1,500円程度が1件あたりの変動費としてかかります。
1件あたりの利益
単価から経費を引いた金額が、あなたの「手取り」の原資となります。
たとえば、1Kの物件を10,000円で請け負った場合、経費で3,000円かかれば残りは7,000円です。この7,000円からさらに所得税や住民税、国民健康保険料などを支払う必要があるため、最終的な「自由になるお金」はさらに少なくなります。
作業に4時間かかったとすると、実質的な時給は2,000円を切ることも珍しくありません。利益を確保するためには、作業のスピードを上げて回転率を高めるか、移動の無駄を極限まで減らす工夫が不可欠です。
月間で稼げる現実的な収入
下請けをメインとする場合、月間の売上目標は40万円〜60万円程度に設定するのが現実的なラインです。
1日2件の現場を25日こなせば月50件となり、平均単価が12,000円なら売上は60万円になります。ここから経費や税金を差し引くと、手元に残る金額は25万円〜35万円程度になるのが一般的です。
ハウスクリーニング下請けで手取りを増やす方法
- 作業時間を短縮して1日の件数を増やす
- 材料を一括仕入れしてコストを削減する
- 移動時間を減らして効率を上げる
下請けは単価が固定されていることが多いため、手元に残る利益を増やすには現場での工夫が欠かせません。
ただなんとなく作業をこなすのではなく、時間やコストを意識した動きを徹底することが、収益アップへの近道となります。
具体的にどのような工夫を凝らせば利益を上積みできるのか、4つの実践的な方法を解説します。
作業時間を短縮して1日の件数を増やす
利益を増やすための最も基本的な戦略は、1件あたりの作業時間を短縮し、1日にこなせる現場数を増やすことです。
たとえば、1Kの空室クリーニングにこれまで6時間かかっていたところを、効率的な手順や強力な薬剤の導入によって4時間に短縮できれば、1日に2件の現場を回る余裕が生まれます。手順をルール化し、汚れの種類に合わせた最適な洗剤を迷わず選べるようになるだけで、作業効率は劇的に向上します。
「安く速く」ではなく「品質を維持しながら速く」仕上げる技術を磨くことが、実質的な時給アップに直結します。
材料を一括仕入れしてコストを削減する
洗剤やワックス、雑巾などの消耗品にかかる費用を抑えることも、利益の底上げには有効です。
ドラッグストアなどでその都度購入するのではなく、業務用の専門店やネットショップで大容量のものを一括仕入れすることで、1件あたりの材料費を数百円単位で削減できます。小さな差に見えますが、年間で数百件の現場をこなす下請け業者にとっては、数万円から十数万円の利益の差となって現れます。
また、薄めて使うタイプの洗剤を正しく使い分けることで、洗浄力を落とさずにコストだけを最小限に抑えることが可能です。
移動時間を減らして効率を上げる
ハウスクリーニングにおいて、移動時間は「売上を産まない時間」であることを強く意識する必要があります。
案件を受ける際は、できるだけ近隣エリアで固めるように元請けの担当者と調整することが重要です。1日の現場がバラバランスの場所にあると、移動だけで数時間を費やしてしまい、こなせる件数が減るだけでなくガソリン代もかさんでしまいます。
元請けに対して「このエリアの物件なら優先的に動けます」と得意エリアを伝えておくことで、移動ロスを最小限に抑えた効率的なスケジュールが組みやすくなります。
ハウスクリーニング下請けの登録ステップ
- 募集情報を探す
- 必要書類を準備する
- 審査と面談を行う
- テスト業務を実施する
- 正式契約を結ぶ
応募から案件の開始まで、一般的な5つのステップについて詳しく解説します。
募集情報を探す
まずは自分の条件に合う元請け会社を探すところから始まります。
地元の不動産管理会社や工務店のホームページを確認すると、「協力会社募集」というページが設けられていることが多くあります。また、求人サイトで「ハウスクリーニング 業務委託」と検索したり、職人向けの掲示板を活用したりするのも有効な手段です。
最近では、SNSで直接募集をかけている清掃会社も増えており、日頃から同業者のアカウントをチェックしておくことで、鮮度の高い情報を入手できます。
必要書類を準備する
応募したい会社が見つかったら、審査に必要な書類を一式揃えます。
| 項目 | 具体的な書類の例 |
|---|---|
| 身分・事業証明 | 免許証、開業届、インボイス登録通知書 |
| 保険・車両 | 賠償責任保険の証券、車検証のコピー |
| 実績アピール | 過去の現場写真、保有資格の証明書 |
審査と面談を行う
書類提出後は、元請け会社の担当者による審査や面談が行われます。
面談では、対応可能なエリアや時間帯、得意な清掃箇所(エアコン、空室など)を具体的にヒアリングされます。このとき、技術だけでなく「報告・連絡・相談がスムーズにできるか」というやり取りの丁寧さも厳しくチェックされるのが一般的です。
特にハウスクリーニングを請け負う場合は、清潔感のある身だしなみや挨拶などのマナーも重要な判断材料となります。
テスト業務を実施する
面談に合格しても、いきなり大量の案件を任されることは少なく、まずは1件〜3件程度の「テスト業務」が入ります。
元請けの担当者が現場を確認し、仕上がり品質や作業時間の早さ、現場でのマナーを確認します。ここで提示されたルール(写真の撮り方、ゴミの処理方法など)を完璧に守ることが、継続的な発注に繋がる大きな壁となります。
期待以上の仕上がりを見せることで、次回からより良い単価の案件や、優先的なスケジュールの割り当てが期待できるようになります。
正式契約を結ぶ
テスト業務で品質が認められれば、いよいよ業務委託契約書を締結し、正式な下請け業者としての取引が始まります。
契約書には、1件あたりの単価や支払いサイト(売上がいつ入金されるか)、損害賠償の範囲などが細かく記載されています。内容をよく確認せずに判を押すと、思わぬトラブルに繋がる恐れがあるため、不明な点は必ず事前に質問することが重要です。
一度契約が結ばれれば、信頼関係を維持し続ける限り、営業なしで継続的に案件が届く安定した環境が整います。
ハウスクリーニングは下請けではなくマッチングサイトがおすすめな理由
- 営業なしで直接受注できる
- 下請けより高い単価で受注できる
- 初期費用ゼロでリスクなく始められる
- 下請けと併用してリスク分散できる
下請けの低単価や依存リスクを解消する手段として、現在はマッチングサイトの活用が非常に有効です。
マッチングサイトとは、掃除をしてほしい人と、掃除のプロを直接つなぐインターネット上の仕組みのことです。
なぜ今の時代、下請けに専念するよりもマッチングサイトを使う方がメリットが大きいのか、その理由を具体的に解説します。
営業なしで直接受注できる
マッチングサイトの最大の特徴は、下請けと同じように自分から外へ売り込みに行かなくても仕事が入ってくる点です。
サイトに自分のプロフィールや対応可能なメニューを登録しておけば、掃除を頼みたいお客様から直接連絡が届きます。本来、直接お客様を見つけるにはチラシ配りやホームページ制作などの大変な営業が必要ですが、その部分をサイトが代わりに行ってくれます。
「営業は苦手だけど、下請けの安すぎる単価からは抜け出したい」という職人さんにとって、非常に相性の良い仕組みです。
下請けより高い単価で受注できる
マッチングサイトでは、間に業者を挟まないため、下請けに比べて圧倒的に高い単価で仕事を受けることが可能です。
下請けの場合、1Kの清掃で手元に残るのは1万円程度ですが、サイト経由で直接受ければ1万5,000円から2万円程度で受注できることも珍しくありません。同じ作業内容であっても、間に抜かれる手数料が少なくなるため、1件あたりの利益が増えます。
これにより、1日の現場数を無理に増やさなくても、今より少ない作業時間でこれまで以上の収入を確保できるようになります。
初期費用ゼロでリスクなく始められる
多くのマッチングサイトは登録料や月額料が無料で、実際に仕事が決まったときだけ手数料を支払う仕組みを採用しています。
そのため、開業したばかりで資金に余裕がない方でも、一切のリスクなしで集客を始めることができます。チラシのように「お金を払ったけれど一件も問い合わせが来ない」という失敗がないため、無駄な出費を抑えながら着実に売上を伸ばせます。
下請けと併用してリスク分散できる
マッチングサイトは、今の生活を支えている下請け仕事を辞めることなく、並行して使い始めることができます。
まずは週に数日だけサイトからの案件を受け、慣れてきたら徐々に直接受注の比率を増やしていくといった調整が可能です。複数の仕事ルートを持つことで、万が一元請け会社からの発注が止まったとしても、収入が完全にゼロになる事態を防げます。
下請けで安定した仕事量を確保しつつ、マッチングサイトで高単価な案件を上乗せする「いいとこ取り」の働き方が、今の個人事業主にとって最も現実的な成功ルートです。
ミツモアで収入を増やしたハウスクリーニング事業者の事例
マッチングサイトの中でも、特にミツモアを活用して「下請け中心の働き方」から抜け出し、大きく売上を伸ばしている職人さんが増えています。
実際にミツモアに登録したことで、どのような変化が起きたのかを具体的な3つの事例でご紹介します。
それぞれの成功の裏にある、具体的な工夫や考え方を見ていきましょう。
有限会社アセンション

「有限会社アセンション」は、大手企業からの独立後、長らく下請けと定期清掃だけで経営を行ってきました。
時期によって仕事量に大きな波があり、閑散期の収入減に悩んでいました。そこでミツモアに登録したところ、問い合わせに対する返信の早さと誠実なやり取りが評価され、わずか4カ月で150万円の成約を達成しました。
一度直接つながったお客様から「実家や知人にも紹介したい」と頼まれるなど、下請け時代にはなかった「紹介の輪」が広がったことが成功の決め手となりました。
関連記事:有限会社アセンション
クリシア
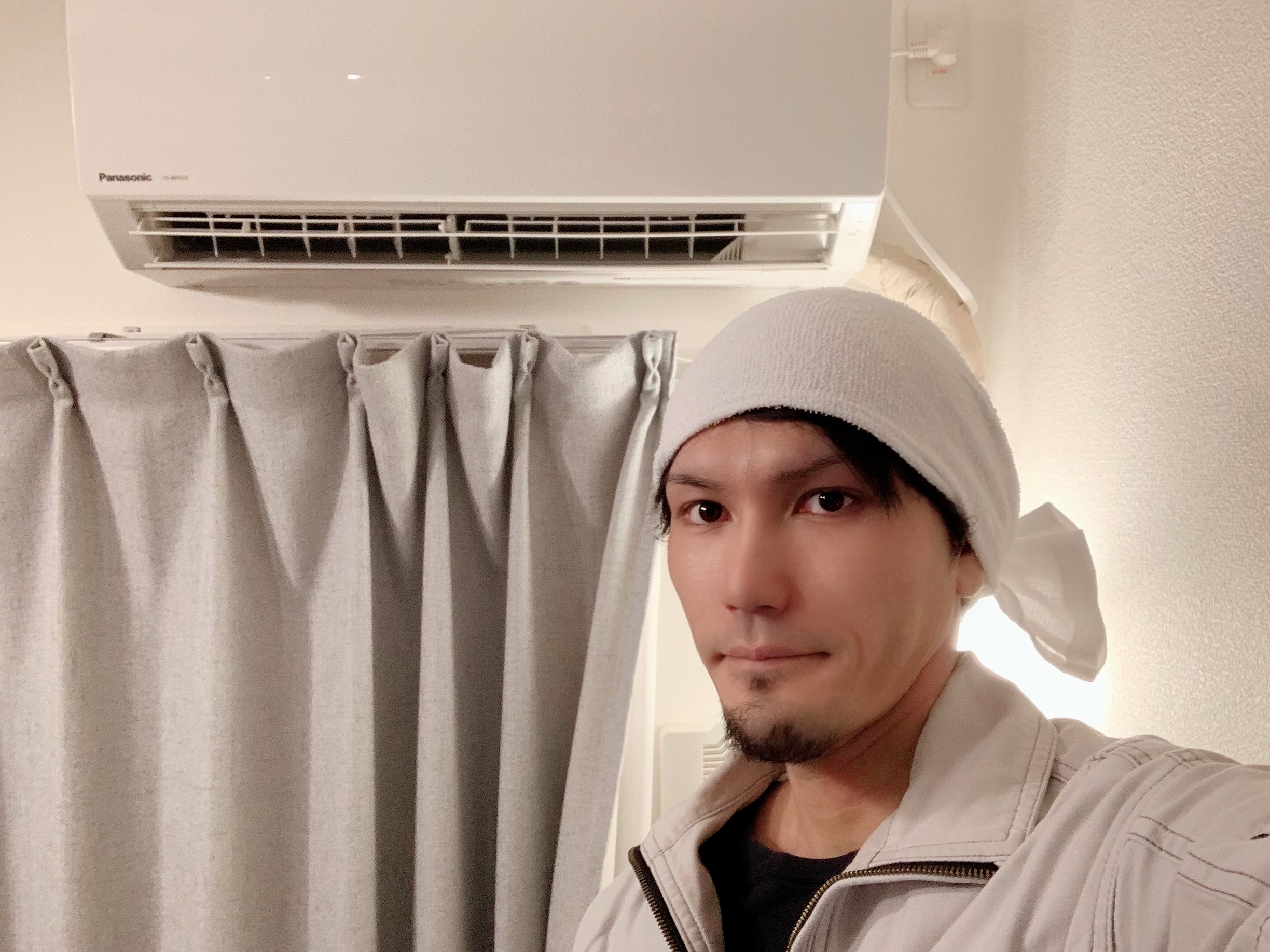
10年以上のキャリアを持つベテラン職人が運営する「クリシア」では、現場作業中の営業対応が大きな課題となっていました。
以前は作業中に見積もり対応をするのが難しく、多くの案件を逃していましたが、ミツモアの「自動応募システム」を導入したことで状況が一変しました。あらかじめ設定した条件に合うお客様へ、作業中も自動で見積もりが届くため、営業の手間が大幅に減ったのです。
結果として、繁忙期には月に30件を超える成約を獲得できるようになり、現場作業に集中しながら売上を最大化することに成功しました。
関連記事:クリシア
ラ・セグーロ

兄妹で経営している「ラ・セグーロ」が直面していたのは、他の集客サイトでの「安売り競争」でした。
腕に自信があるのに単価を下げざるを得ない状況に苦しんでいましたが、ミツモアではエアコン清掃に防カビコーティングを無料で付けるなどの付加価値をアピールし、人柄が伝わる丁寧なメッセージを心がけました。
すると「口コミを見て決めました」というお客様が増え、安さではなく品質で選ばれるようになったのです。現在では70件以上の高評価を獲得し、価格競争とは無縁の安定した集客を実現しています。
関連記事:ラ・セグーロ
ハウスクリーニング下請けに関するよくある質問
下請けとして独立を目指す際や、現在の働き方を見直すときには、制度や将来性について多くの疑問が湧いてくるものです。
現場の職人さんが直面しやすい、より踏み込んだ疑問について具体的にお答えします。
下請けだけで独立しても生活できますか
下請けだけでも生活することは可能ですが、そのためには「移動距離の短縮」と「作業のスピード」が絶対条件になります。
1Kの単価が1万円程度の場合、1日2件を週5日こなせば月40万円ほどの売上になります。ここから経費を引いても手元に25万円から30万円ほど残る計算になりますが、これはあくまで「順調に仕事が埋まった場合」の話です。下請けだけに頼ると元請けの都合に左右されるため、まずは下請けで基礎を作った後、徐々にマッチングサイトなどで自分でも集客できるルートを持っておくのが、生活を安定させる最も確実な方法です。
下請けと直接受注を併用すると契約違反になりますか
一般的に、下請けと自分での直接受注を併用すること自体は、契約違反にはならないケースがほとんどです。
ただし、注意しなければならないのは「元請けから紹介されたお客様」と直接取引をすることです。これは「中抜き」と呼ばれ、ほとんどの元請け会社との契約で厳しく禁止されており、発覚すれば即座に取引停止となる重大なルール違反です。自分で新しく見つけたお客様であれば、下請け案件と並行して進めることは全く問題ありませんので、スケジュールをうまく調整して両立を目指しましょう。
下請けから直接受注に切り替える最適なタイミングはいつですか
「下請け案件でスケジュールが埋まりすぎて、高単価な直接案件を断らざるを得なくなったとき」が、切り替えのベストタイミングです。
いきなり下請けをゼロにするのではなく、まずは売上の2割から3割を直接受注(マッチングサイトなど)に置き換えることから始めてみてください。直接受注の案件が増えてきたら、徐々に条件の悪い下請け案件を絞っていくことで、収入を下げることなくスムーズに独立した運営へと移行できます。
下請けに必要な保険や資格は何ですか
最も重要なのは「賠償責任保険」への加入で、これがなければ大半の会社と契約ができません。
資格については必須ではありませんが、「ハウスクリーニング技能士」などの国家資格を持っていると、技術の証明になるため単価交渉や審査で非常に有利に働きます。また、エアコン洗浄をメインにするのであれば、電気工事士の資格があると対応できる機種が増え、元請けからの信頼も厚くなります。
ハウスクリーニングで仕事を取るならミツモア
ハウスクリーニングの下請けで安定した仕事量を確保しつつ、さらなる収益アップを目指すなら、ミツモアの活用が最も現実的な選択肢となります。
下請けの「営業が不要」というメリットを活かしながら、直接受注による「高い利益率」を同時に手に入れることができます。
さらに初期費用や月額費用が一切かからないため、現在の下請け仕事を続けながら、リスクゼロで導入することも可能。
下請けの安定感と、直接受注の収益性。この両方をうまく組み合わせることで、将来の生活にゆとりを持たせられるようになります。
まずはミツモアに登録して、新しい収入のルートを一つ、作り始めてみてはいかがでしょうか。
【プロ向け】ミツモアの評判は最悪って本当?デメリットとリアルな登録プロの口コミを紹介
【プロ向け】ミツモアの評判は最悪って本当?デメリットとリアルな登録プロの口コミを紹介
「ミツモアで集客を始めようか迷っているけれど、ネットで評判を検索すると最悪や怪しいといった言葉が出てきて不安…」
新しい集客手段としてミツモアを検討する際、このようなネガティブな検索候補を目にして、登録を躊躇してしまう事業者様は少なくありません。大切な時間を使う以上、失敗したくないと考えるのは当然のことです。
確かに、インターネット上の口コミには「手数料が高い」「稼げない」といった厳しい意見も散見されます。しかし、その評判の裏側を詳しく調べてみると、「仕組みへの誤解」や「過去の古い情報」に基づいているケースも多いのが実情です。
そこで本記事では、ミツモアに関する評判の真偽を、実際の利用者の口コミや公式情報に基づいて徹底的に検証しました。
- 「手数料が高い」のか?
- 「怪しい」と言われる噂は本当なのか?
- 実際に利益を出しているプロは、どう使っているのか?
忖度なしで事実を解説しますので、ミツモアがみなさまのビジネスに合うかどうか判断するための材料としてお役立てください。
この記事の要約
- 実際の利用者の声:「手数料は長期的に見れば妥当」「営業が自動化できる」「集客力が凄い」と評価。初期費用・月額料金0円でリスクが低い点も支持されています
- 運営会社の信頼性:「日本スタートアップ大賞(経済産業大臣賞)」経済産業大臣賞や「みずほ銀行イノベーションアワード」を受賞した社会的信用のある企業が運営しています
- 登録前に確認すべき点:手数料率や料金体系はサービスごとに異なるため、事前に確認することが重要です
「手数料が高くて稼げない」という評判
ミツモアの利用を検討する事業者様にとって、最も気になるのが手数料ではないでしょうか。
「手数料を支払って利益は残るのか?」という点は、導入前の重要な判断基準です。
ミツモアには「成約課金型」と「応募課金型」という2つの料金形式があり、ご利用になるサービスの種類によってどちらかが適用されます。さらに成約課金型の場合、「自動応募」と「手動応募」で料金の発生タイミングが異なります。
ここでは、ミツモアの手数料体系の仕組みと、実際に利用して利益を上げているプロの口コミを交えて、その実態を検証します。
「手数料が高い」を検証
評判の内容
手数料について、「手数料が高いのではないか」と懸念されることがあります。
特に、最大税抜35%という料率設定を見て、負担が大きいと感じる場合があるようです。
事実
ミツモアの手数料体系は、ご利用になるサービスの種類によって「成約課金型」と「応募課金型」の2つに分かれており、さらに成約課金型の場合は応募方法(自動応募・手動応募)によって料金の発生タイミングが異なります。
【成約課金型サービスの場合】
- 自動応募を利用する場合:成約時のみ成約手数料が発生します(税込16.5%〜38.5%、サービスにより最低料金あり)
- 手動応募を利用する場合:見積もり応募時に応募手数料 150円〜(税込165円〜)と、成約時に成約手数料(税込16.5%〜38.5%)が発生します
【応募課金型サービスの場合】
- 見積もり応募時のみ:応募手数料 150円〜(税込165円〜)
- 成約手数料:なし
【成約手数料の料率例】
- 低料率(8%〜15%前後):外壁塗装、屋根修理、リフォームなど、単価が高額になりやすいカテゴリ
- 高料率(30%〜35%台):税理士・行政書士(士業)、出張撮影など
利用者の口コミ
一見、手数料率が高めに設定されている税理士カテゴリのプロは、長期的な関係構築を見据えてコストパフォーマンスを評価しています。特に、税理士であれば顧問契約の2年目以降や、前回の成約から2年以上経過した案件などは手数料が無料になります。
「仮に10年お付き合いするお客様だとすると初年度35%は年にして3.5%。それなりに廉価で手頃な手数料だなという感覚です」
関連記事:初月から100万円突破!確定申告最多成約数を誇る税理士が使う『安心料金制・自動集客方式』とは
また、害虫駆除のプロは、無駄な課金が発生しないシステムや、他者と比較して手数料が高くないという面も評価しています。
「ミツモアは成約した仕事に対して手数料が課金されるシステムなので納得できます。(中略)手数料の割合も他と比べて格安だと思います」
関連記事:業界歴10年の駆除エキスパートがミツモアの活用で開業と同時に月20件の営業を成功させた秘訣とは?
結論
「手数料が高い」という懸念は、一部のカテゴリの料率(最大35%)などを見て生じるものですが、実際には他社と比較しても納得できる水準です。
特に成約課金型サービスで自動応募を利用する場合、初期費用ゼロで成約時のみの支払いとなるため、リスクを最小限に抑えられます。
手動応募や応募課金型の場合は応募時に費用が発生しますが、いずれの形式でも月額固定費はかからないため、実際に利用しているプロからは長期的な費用対効果の良さが評価されています。
「見積金額を高めに設定する必要がある」を検証
評判の内容
「手数料分を確保するために、見積もり金額を調整する必要があるのではないか」という点についても検証します。
事実
ミツモアでは、成約課金型サービスの場合は成約手数料を、応募課金型サービスや手動応募の場合は応募手数料を見越して、適正な見積金額を設定することが推奨されています。
しかし、だからといって「高すぎて成約しない」わけではありません。
利用者の口コミ
月50件成約しているハウスクリーニングのトッププロは、極端な安売りをせず、適正価格で提案しています。
「見積もり価格の上限と最安値を想定し、5人のプロ中”上から2番目”あたりの価格を狙うようにしています。あまり安いと質が不安、高いと納得できないので、お客様心理では中間を選ぶのではと想像してのことです」
関連記事:月50件成約のトップクラスプロが語る、ミツモアでビジネスを成功に導く5つの要素とは?
また、不用品回収のプロも、価格以外の魅力を伝えることで選ばれています。
「価格だけでなく、口コミ評価とか実績とか文面から伝わってくる感じとか、いろいろな要素を見てお客様自身が5件のプロの中から選ぶわけですよね。必ずしも低価格だから選ばれる、というわけではない点がすごく気に入っています」
関連記事:月200件超実績のプロがミツモアを評価。『口コミ5件後、月3ケタ成約まであっという間でした』
結論
成約課金型サービスの場合は成約手数料を、応募課金型サービスの場合は応募手数料を見越して見積額を設定する必要があります。
しかし、手数料を見越して見積金額を高く設定しても、提案内容や安心感で成約できていることが事例からもわかります。
「カテゴリによっては採算が合わない」を検証
評判の内容
「単価の安い仕事だと、手数料を引かれると採算が合わないのではないか」という懸念について検証します。
事実
ミツモアではカテゴリごとに手数料率や最低料金設定が異なります。
【成約課金型サービスの場合】
一定の最低手数料(例:税込2,200円など)が設定されている場合があるため、単価が極端に低い依頼では成約手数料の比率が高くなる傾向があります。さらに手動応募を利用する場合は、応募時に応募手数料(150円〜)も発生します。
【応募課金型サービスの場合】
応募手数料(150円〜)のみが発生するため、単価の低い案件でも手数料比率を抑えられますが、成約に至らない案件に応募した場合もコストがかかる点に注意が必要です。
利用者の口コミ
では、低単価なサービスを扱うプロはどのように利益を出しているのでしょうか。
単発案件が中心となる害虫駆除のプロの場合、空き時間を埋めるように効率よく受注することで、トータルの収益性を高めています。
「空いている時間を埋めるようにスケジュールを組むと、効率よく稼働できます。(中略)全体の売り上げを伸ばすことができました」
関連記事:業界歴10年の駆除エキスパートがミツモアの活用で開業と同時に月20件の営業を成功させた秘訣とは?
結論
「カテゴリによっては採算が合わない」というのは、一部の低単価・単発カテゴリにおいては当てはまる場合があります。
特に手動応募や応募課金型で応募手数料が発生する場合、単価の低い案件では手数料比率が高くなる傾向があります。
しかし、成約課金型サービスで自動応募を利用する場合は成約しなければ費用がかからないため、空き時間を活用して効率的に受注する運用などを行うことで、十分に利益を出すことが可能です。
「システムが使いにくい」という評判
手数料と並んで事業者の皆様が気にされるのが、「システム面」です。
ミツモアはインターネットを介したマッチングサイトであるため、下請けやフランチャイズとは異なる特徴があります。
ここでは、システムの仕組みと実際に利用しているプロの実感を交えて検証します。
「1つの依頼に対して提案できるのは5社まで」を検証
評判の内容
「せっかく依頼があっても、すぐに枠が埋まって応募できない」「競争が激しいのではないか」といった、提案枠の制限に関する評判です。
事実
ミツモアでは、1つの依頼に対して見積もりを提案できる事業者は最大5社までと決まっています。
一見すると「応募しにくい」と感じるかもしれませんが、これは事業者と依頼者の双方を守るための仕組みです。
提案者が無制限だと価格競争が激化し、依頼者も選びきれなくなります。
利用者の口コミ
実際に利用しているプロは、この「5社制限」をチャンスと捉えています。
「事業者目線でも、5社という限られた中で選んでもらえるのでチャンスがあると感じています」
関連記事:ミツモアは情報量が豊富で相場観も養える。競合他社から学んで今や月30件超の安定成約を実現
また、新規参入の税理士も、自動応募を活用することで枠を獲得し、成果を上げています。
「数が多いから、一つ成約できなくても次々トライすればいいという攻めの気持ちになれるのがいいですね」
関連記事:初月から100万円突破!確定申告最多成約数を誇る税理士が使う『安心料金制・自動集客方式』とは
結論
「1つの依頼に5社まで」というのは事実ですが、これは「悪い評判」ではなく、むしろ成約率を高めるためのメリットと言えます。
多くのプロが、無駄な競争に巻き込まれず、効率的に受注できる点を評価しています。
「依頼者と継続的な関係を築きにくい」を検証
評判の内容
「ミツモアを通さずに直接連絡先を交換してはいけない」「毎回システムを通すのが手間」といった、顧客との関係構築に関する懸念です。
事実
ミツモアの利用規約では、いわゆる「中抜き(直接取引)」や、成約前の連絡先交換は禁止されています。これはトラブル防止と安全確保のためです。
しかし、継続依頼自体がしにくいわけではありません。
むしろ、税理士顧問契約の2年目以降や、前回の成約から2年以上経過した案件などは手数料が無料になるなど、長期的な関係構築を支援する仕組みがあります。
利用者の口コミ
ルールを守りながらミツモア経由で信頼を積み重ね、多くのリピーターを獲得している事例があります。
「上手に使えば一人のお客さまから複数の案件へと拡大していくことができます」
関連記事:Web完結する業務フローを追求した結果、ミツモアが集客のコストダウンと時短の切り札に。7割のリピート依頼を獲得したIT税理士に密着
また、便利屋のプロも、質の高い顧客と長期的な関係を築いています。
「ミツモアのお客様は情報リテラシーが高いというか、良質な方が多いですね。(中略)こちらの対応次第で、継続的なお客様になり得ると思います」
関連記事:ミツモアは情報量が豊富で相場観も養える。競合他社から学んで今や月30件超の安定成約を実現
結論
直接取引(中抜き)が禁止されているのは事実ですが、ミツモアのシステムを通じて継続的な関係を築くことは十分に可能です。
特に成約課金型サービスでは、税理士顧問契約の2年目以降の手数料が無料になるなど、長期的な関係構築を支援する優遇措置があり、多くのプロがリピーター獲得に成功しています。
「対応が追いつかなくなる可能性もある」を検証
評判の内容
「成約課金型サービスで自動応募に設定していると、知らない間に依頼が来すぎて対応できなくなるのではないか」という、嬉しい悲鳴とも言える懸念について検証します。
事実
成約課金型サービスで自動応募を利用する場合、ただ闇雲に応募されるわけではありません。
対応可能エリア、日時、1日の件数上限などを細かく設定できます。また、繁忙期や休暇中は自動応募をOFFにするなど、自分のスケジュールに合わせて柔軟にコントロールできる仕組みになっています。
※自動応募は成約課金型サービスでのみ利用可能です。応募課金型サービスは手動応募のみとなります。
利用者の口コミ
多くの案件を獲得しているプロは、カレンダー機能などを活用して受注量を調整しています。
「お客様が日程の希望を自らチェックして入れてくださるのでスケジュール管理もしやすくていいですね」
関連記事:業界歴10年の駆除エキスパートがミツモアの活用で開業と同時に月20件の営業を成功させた秘訣とは?
行政書士のプロも、依頼の多さに驚きつつ、自分のペースで対応しています。
「毎日たくさんの新しい依頼案件がメールで入ってきて、嬉しい悲鳴をあげています。(中略)自分たちの強みが活かせる案件や、お役に立てそうな案件を選んで返信しています」
関連記事:登録2ヵ月で成約額100万円目前と営業の悩み解消!「ミツモアに助けられた」と大絶賛の独立・開業税理士の声
結論
成約課金型サービスで自動応募を利用する場合、「対応が追いつかなくなる」可能性はありますが、それはシステムで制御可能です。
手動停止や上限設定を適切に行えば、自分の許容量を超えた仕事が舞い込むことは防げます。むしろ、それだけ集客力があるという証拠とも言えます。
なお、応募課金型サービスは手動応募のみのため、自分で応募をコントロールできます。
「危ない・悪質・怪しい」という評判
インターネットで検索すると「危ない」「悪質」といったキーワードが出てくることがあり、不安を感じる方もいるかもしれません。
「危ない」「悪質」「怪しい」を検証
評判の内容
「運営会社の実態がよくわからない」「怪しいサービスではないか」といった漠然とした不安の声です。
事実
運営会社の株式会社ミツモアは、2017年に設立された日本の企業です。
信頼性は客観的に評価されており、2023年には「日本スタートアップ大賞(経済産業大臣賞)」を受賞しています。また、みずほ銀行のイノベーションアワードを受賞するなど、社会的信用の高い企業が運営しています。
登録事業者には本人確認や資格証の提出を義務付けており、プラットフォームとしての安全性も確保されています。
利用者の口コミ
利用を開始する前は不安を感じていたプロも、実際に使ってみて信頼を寄せています。
ある税理士は、登録当初に運営会社を直接確認しに行ったほど慎重でしたが、現在は主力として活用しています。
「住所に本当に会社があるのかと、ミツモアのオフィスを直接見に行ったくらいですから(笑)。(中略)今ではミツモアが営業の柱です」
関連記事:Web完結する業務フローを追求した結果、ミツモアが集客のコストダウンと時短の切り札に。7割のリピート依頼を獲得したIT税理士に密着
結論
「危ない」「悪質」という評判は、サービスの実態を知らないことによる誤解から生まれるものです。
実際には公的な受賞歴もあり、本人確認を徹底している健全なプラットフォームです。
「案件が獲得できない」という評判
「登録しても自分の専門分野の仕事がないのではないか」「本当に依頼が来るのか」という不安は、新しい集客サービスを利用する上での基本的な不安です。
特に、マッチングサービスでは「人気業種ばかりで自分の業種は需要がない」「都市部だけで地方には案件が来ない」といった偏りを心配する声も聞かれます。
せっかく登録しても仕事につながらなければ、時間の無駄になってしまいます。
ミツモアは「案件数が豊富」と言われていますが、それが本当に幅広い業種・地域に当てはまるのか、それとも一部の事業者だけの話なのか。
ここでは、ミツモアの集客力、対応業種の幅広さ、商圏の柔軟性について、具体的なデータとプロの声をもとに検証します。
「集客力がある」を検証
評判の内容
「とにかく依頼数が多い」「自分で営業するよりお客さんが集まる」という評判です。
事実
ミツモアの累計依頼数は700万件を突破しています(2025年時点)。
強力なマーケティングにより、多くの見込み客をプラットフォームに集客し続けています。
利用者の口コミ
不用品回収のプロは、その圧倒的な案件数に驚き、他の集客手段が不要になったと語っています。
「ミツモアを使うことで営業の成果が非常に上がり本当に感謝しています。とにかく集客力が凄いので今は仕事で精一杯で、正直他のweb集約サイトを使う余裕はありません。」
関連記事:月200件超実績のプロがミツモアを評価。『口コミ5件後、月3ケタ成約まであっという間でした』
また、大阪のハウスクリーニング事業者も、Web検索での強さを実感しています。
「Web検索しているとミツモアが常にトップに表示されるので、(中略)そうしたことも集客力につながっているのでしょう」
関連記事:月50件成約のトップクラスプロが語る、ミツモアでビジネスを成功に導く5つの要素とは?
結論
客観的な依頼数データと、現場で対応しきれないほどの依頼を受けているプロの実感の双方から、ミツモアが高い集客力を持っていることは明らかです。
「自分で集客するのが難しい」「営業に時間を割けない」という事業者にとって、強力な集客ツールとして機能しています。
「対応したい業種が全て揃っている」を検証
評判の内容
「自分の専門分野の仕事が必ずある」「複数のサービスを掛け持ちで登録できるため、仕事の幅が広がる」という評判です。
事実
ミツモアで取り扱うサービスカテゴリは300種類以上に及びます。
ハウスクリーニングや引越しといった生活関連サービスだけでなく、以下のような多岐にわたる業種をカバーしています。
- 税理士、カメラマン、Web制作
- 害獣駆除や庭木の剪定などのニッチな分野
- その他専門職・技術職
また、最大の特徴は「1つの事業者アカウントで複数のカテゴリに登録できる」点です。これにより、事業者は自社の持つスキルやリソースを余すことなく活かし、複合的に集客することが可能になっています。
利用者の口コミ
引越しだけでなく、周辺業務も合わせて受注することで事業を安定させているプロの事例があります。
「ミツモアはプロが登録するサービスの幅が広いんですよ。私の場合、引越だけでなく不用品回収、家具組み立て、家電設置、便利屋といった項目でも登録しています。その分、幅広く集客できるのでありがたいですね」
関連記事:信頼を重ねて口コミ370件超&☆評価4.8以上の引越しのプロ。その原動力はお客様の手間を省く提案力
また、ハウスクリーニング事業者でありながら、エアコン掃除からリフォーム、屋根工事まで幅広い業務を手掛け、月50件前後の安定成約を実現している事例も報告されています。
結論
業界最大級のカテゴリ数を誇り、事業者が「自分の対応できる仕事」を漏らさず拾えるよう、網羅的なカテゴリ設計がなされています。
特定の専門職だけでなく、多能工(マルチスキル)の事業者にとっても非常に有利な環境と言えます。
「遠方の案件でも獲得できる」を検証
評判の内容
「地元だけでなく、遠くのエリアの仕事も取れる」「地方にいながら都心の案件を獲得できる」という、商圏拡大に関する評判です。
事実
ミツモアには仕事エリア設定において「遠隔地のリモート案件に自動応募する」という機能があります。
これを有効にすると、オンライン完結が可能なサービス(税理士、Web制作、翻訳など)では、拠点から300kmを超える遠方の依頼にも応募可能になります。
これにより、地方在住のプロが首都圏の案件を獲得したり、逆に出張可能なカメラマンが全国各地の依頼を受けたりすることがシステム上可能になっています。
利用者の口コミ
実際に、地方から商圏を広げて事業拡大に成功した事例が報告されています。
岩手県で活動を開始したカメラマンは、登録直後に東京の大型案件を獲得し、それを機に東京へ進出しました。
登録2日目で大企業案件を成約し、「願ってもない大きな東京の企業様との仕事でした」と驚きを語っています。
関連記事:登録2日目で初成約。リピートで評価額10億円の物撮り案件も獲得! 1ヵ月で岩手から東京進出のサクセスストーリー
結論
特にオンライン対応可能な業種(税理士、Web制作、翻訳など)や、広域出張が可能な業種(カメラマンなど)においては、地理的な制約を超えて案件を獲得できるチャンスがあります。
また、エリア設定を広げることで商圏を拡大するという使い方も可能です。
「仕事条件を自由に設定できる」を検証
評判の内容
「自分のスケジュールや対応エリアに合わせて、無理なく仕事を受けられる」「細かく設定できるのでミスマッチが少ない」という評判です。
事実
ミツモアのシステムでは、仕事エリアを「市区町村単位」または「拠点住所から半径300km以内(一部条件でそれ以上も可)」で細かく指定できます。また、特定の地域のみ除外する設定も可能です。
さらに、単なるエリア設定だけでなく、以下の条件も自由に設定できます。
- 予約受付期間(当日から何日後まで受け付けるか)
- 対応可能なオプション(追加サービス)
- 価格設定
対応できないオプションはチェックを外しておけば、その条件を含む依頼には自動応募されないため、対応不可能な依頼が届いて断るという無駄な手間が発生しません。
利用者の口コミ
自動集客機能を活用している不用品回収のプロは、条件設定による効率化を実感しています。
「手間がかからないしとにかくスピードが速いですね」
関連記事:月200件超実績のプロがミツモアを評価。『口コミ5件後、月3ケタ成約まであっという間でした』
また、中古自動車販売・整備を行うプロは、スケジュール調整の円滑さを評価しています。
「スケジュール管理もしやすいし、最初の段階でこちらのスケジュール状況をお客様に提示できてお客様の納得感も高い。ミツモアはプロとお客様がいわば対等な立場で互いの条件を見ながら交渉が進められる、という点がとても良いですよね」
関連記事:ベテラン経営者が驚かされたと語るミツモアの自動応募システム
結論
他社サービスと比較しても、対応エリア、日程、オプション内容などを非常に細かくカスタマイズできる機能が備わっています。
特に成約課金型サービスで自動応募を利用する場合、事業者は「自分の条件に合う案件」だけを自動的に選別して集客できるため、評判通り効率的な営業活動が可能です。応募課金型サービスの場合は手動で案件を選択することになりますが、細かい条件設定により、自分に合った案件を見つけやすい環境が整っています。
ミツモアに登録するメリット・デメリット
プロの声を総合すると、ミツモアは「営業効率」と「初期費用・月額費用ゼロのリスクの低さ」に強みがある一方で、プラットフォーム特有の「手数料」がデメリットとして挙げられます。
事業者にとってのメリット
ミツモアの最大のメリットは、初期費用・月額費用がゼロで始められることと、サービスによっては営業活動を自動化できる点にあります。
- 初期費用・月額費用がゼロでリスクが低い
- 成約課金型サービスなら自動応募で営業工数を大幅に削減できる
初期費用・月額費用がゼロでリスクが低い
いずれの料金形式でも、初期登録料や月額固定費は一切かかりません。
特に成約課金型サービスの自動応募を利用する場合、成約(予約確定)した場合のみ手数料が発生するため、仕事が得られないのに費用だけがかさむという「持ち出しリスク」がなく、安心して利用できます。
手動応募や応募課金型サービスの場合は応募時に費用が発生しますが、月額固定費がないため、自分のペースで営業活動をコントロールできます。
成約課金型サービスなら自動応募で営業工数を大幅に削減できる
成約課金型サービスで自動応募を利用する場合、事前に条件を設定しておけば、24時間365日システムが自動で見積もりを送信してくれます。
現場作業中や移動中でもスピーディーに顧客対応ができ、自らテレアポや飛び込み営業をする手間から解放されます。
※自動応募は成約課金型サービスでのみ利用可能です。応募課金型サービスは手動応募のみとなります。
事業者にとってのデメリット
一方で、ミツモアを利用する上で最も注意すべきなのが「料金形式と使い方によって、手数料負担が大きく変わる」という点です。
料金形式による手数料の違い
まず、ミツモアの料金形式を整理します。
【成約課金型サービス × 自動応募】
- 応募時:費用なし(0円)
- 成約時:成約手数料 税込16.5%〜38.5%(サービスにより最低料金あり)
- リスク:成約しなければ費用は一切かからない(最もリスクが低い)
【成約課金型サービス × 手動応募】
- 応募時:応募手数料 150円〜(税込165円〜)※依頼によって異なる
- 成約時:成約手数料 税込16.5%〜38.5%(サービスにより最低料金あり)
- リスク:応募した時点で費用が発生。成約に至らない場合は応募手数料のみ負担
【応募課金型サービス × 手動応募(のみ)】
- 応募時:応募手数料 150円〜(税込165円〜)※依頼によって異なる
- 成約時:成約手数料なし(0円)
- リスク:応募した時点で費用が発生。成約に至らない場合は応募手数料のみ負担
具体的なコスト試算例
料金形式の違いを、具体的な数字で見てみましょう。
ケース1:成約課金型サービス(ハウスクリーニング)で自動応募を利用
- 成約手数料:20%(税込22%)
- 成約金額:30,000円の場合 → 手数料 6,600円
- 応募して成約しなかった案件:0円(リスクなし)
ケース2:成約課金型サービス(ハウスクリーニング)で手動応募を利用
- 応募手数料:165円 × 10件応募 = 1,650円
- 成約手数料:20%(税込22%)
- 成約金額:30,000円の場合 → 手数料 6,600円 + 応募手数料 1,650円 = 合計 8,250円
- 成約率が30%の場合、成約しなかった7件分の応募手数料(1,155円)も負担
ケース3:応募課金型サービスで手動応募(成約手数料なし)
- 応募手数料:165円 × 10件応募 = 1,650円
- 成約手数料:0円
- 成約金額:30,000円の場合 → 手数料 1,650円のみ
- 成約率が30%の場合でも、手数料は応募した分だけ(1,650円)
このように、同じハウスクリーニングでも、自動応募なら成約時のみ6,600円、手動応募なら合計8,250円と、使い方によって負担額が27.5%も変わります。
低単価案件で特に注意が必要なケース
さらに注意が必要なのが、低単価案件における「最低手数料」の存在です。
例:電球交換(成約課金型サービス、手数料率20%、最低手数料2,200円の場合)
案件A:成約金額 5,000円の場合
- 本来の手数料(20%):1,100円
- 実際の手数料(最低料金適用):2,200円
- 実質手数料率:44%
案件B:成約金額 3,000円の場合
- 本来の手数料(20%):660円
- 実際の手数料(最低料金適用):2,200円
- 実質手数料率:73.3%
さらに手動応募の場合は、上記に加えて応募手数料165円も発生するため、3,000円の案件で合計2,365円(実質手数料率78.8%)となり、ほとんど利益が残りません。
このような低単価案件では、表示されている手数料率(20%)と実際の負担率が大きく異なるため、見積もり作成時に注意が必要です。
手動応募・応募課金型のリスク
もう1つの注意点が、「応募した時点で費用が発生する」手動応募と応募課金型のリスクです。
例:応募課金型サービスで10件応募した場合
- 応募手数料:165円 × 10件 = 1,650円
- 成約率30%の場合:3件成約、7件不成約
- 不成約の7件分の応募手数料:1,155円は回収不可能
成約課金型の自動応募であれば、不成約の7件は費用0円ですが、手動応募や応募課金型では「応募した時点で費用が確定する」ため、成約率が低い場合や、案件の見極めが甘い場合、コストだけがかさむリスクがあります。
どのような事業者が注意すべきか
以上を踏まえると、以下のような事業者は特に料金形式を慎重に確認する必要があります。
- 低単価の単発サービスが中心の事業者:最低手数料により実質負担率が高くなる可能性があります
- 成約率に自信がない新規参入者:手動応募や応募課金型では、不成約でも費用が発生します
- 複数カテゴリに登録している事業者:カテゴリごとに料金形式が異なるため、それぞれの仕組みを把握する必要があります
デメリットを最小化する使い方
ただし、このデメリットは「料金形式を理解して、適切に使い分ける」ことで軽減できます。
- 成約課金型サービスは自動応募を優先:成約しなければ費用0円のため、リスクを最小化できます
- 手動応募は厳選して使用:応募手数料が発生するため、成約の見込みが高い案件のみに絞ります
- 低単価案件は見積額を工夫:最低手数料を踏まえた価格設定を行い、適正な利益を確保します
- 応募課金型は成約率を重視:応募時に費用がかかるため、成約確度の高い案件を見極めます
結論
ミツモアの最大のデメリットは、「料金形式が複雑で、使い方を間違えるとコストが想定以上にかかる」という点です。
特に以下のケースでは注意が必要です。
- 低単価案件で最低手数料が適用される場合(実質負担率が50%を超えることも)
- 手動応募や応募課金型で、成約率が低いまま大量応募してしまう場合
- 自社のサービスがどの料金形式に該当するか確認せずに始めてしまう場合
しかし、この点さえ理解していれば、自動応募を活用する、案件を見極める、適正な見積額を設定するといった工夫により、手数料負担を最適化しながら効率的に利益を上げることが可能です。
重要なのは、登録前に自社のサービスがどの料金形式に該当するかを確認し、その特性に合わせた運用計画を立てることです。
ミツモアの評判に関するよくある質問
最後に、ミツモアへの登録を検討されている方からよく寄せられる疑問について、これまでの検証結果をもとにQ&A形式で回答します。
「手数料が高くて稼げない」って本当ですか?
回答:料金形式と使い方によりますが、多くのプロが利益を出しています。
ミツモアの手数料は、サービスの種類と応募方法によって異なります。
【成約課金型サービスの場合】
- 自動応募:成約しなければ費用は0円。成約時のみ成約手数料(税込16.5%〜38.5%)が発生します
- 手動応募:応募時に応募手数料(150円〜)、成約時に成約手数料が発生します
【応募課金型サービスの場合】
- 応募時に応募手数料(150円〜)のみが発生し、成約手数料はかかりません
一部の高料率カテゴリ(最大35%)や、単価が極端に低い案件では手数料負担が重く感じられる場合がありますが、以下の理由から「稼げない」とは一概に言えません。
- いずれの料金形式でも初期費用・月額費は0円。大きな持ち出しリスクがありません
- 成約課金型サービスの自動応募なら、成約しなければ費用は0円です
- 税理士などは2年目以降の手数料が無料になるため、長期的に見れば高収益になります
- 自動応募で手間をかけずに集客できるため、空き時間を埋めることでトータルの売上を伸ばせます
初期費用ゼロのリスクの低さと、成約率の高さ(20〜30%)を考えれば、広告費として十分に割に合う投資です。
「システムが使いにくい」って本当ですか?
回答:慣れは必要ですが、効率化のための機能が充実しています。
「1つの依頼に5社まで」「直接連絡禁止」といった独自のルールがあるため、最初は戸惑うかもしれません。
しかし、これらは「過度な価格競争を防ぐ」「トラブルを防止する」ための仕組みです。
特に成約課金型サービスで自動応募を利用する場合、事前に条件を設定しておけば、営業活動をほぼ自動化でき、非常に効率的に働くことができます。
応募課金型サービスや手動応募の場合も、テンプレート機能などを活用することで、応募の手間を削減できます。
「危ない・悪質」って本当ですか?
回答:いいえ、公的評価も高い健全なサービスです。
運営会社は本人確認や資格確認を厳格に行っており、経済産業大臣賞を受賞するなど社会的信用のある企業です。
「怪しい」という噂の多くは、サービス初期の仕様や、仕組みへの誤解に基づくものです。現在は累計700万件以上の依頼実績があり、多くの事業者がメインの集客ツールとして安全に利用しています。
まとめ
ミツモアの評判について、悪い口コミから良い口コミまで徹底的に検証してきました。
結論として、ミツモアは「料金形式を理解して、自社に合った使い方をすれば、効率的に集客できる強力なツール」であると言えます。
もちろん、全ての事業者に完璧にマッチするわけではありません。
しかし、いずれの料金形式でも初期登録料・月額利用料は0円です。まずは登録して試してみるリスクは非常に低いと言えます。
まずは無料登録を行い、あなたの対応エリアでどのような依頼が来ているかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
ハウスクリーニングの開業・起業で失敗を防ぐ完全ガイド!助成金から保険、資金、屋号、開業届、資格情報まで網羅
ハウスクリーニングの開業・起業で失敗を防ぐ完全ガイド!助成金から保険、資金、屋号、開業届、資格情報まで網羅
ハウスクリーニングで開業したいが、開業資金はどれくらい必要か、どんな手続きが要るのか、何から準備すればいいのか分からない。多くの開業検討者がこうした疑問を抱えています。
「フランチャイズに加盟しないと成功できない」「まとまった資金がないと開業できない」といった思い込みでは一歩を踏み出せません。しかし、正しい手順と準備を知れば、計画的に開業を進められます。
この記事では、開業資金の具体的な内訳と調達方法、必要な手続きと届出、そして開業を成功させるための準備事項を解説します。
この記事の要約
- 個人で開業する場合の資金は30万〜100万円で、フランチャイズの高額な加盟金は不要です
- 日本政策金融公庫の創業融資や小規模事業者持続化補助金を活用すれば、自己資金が少なくても開業資金を調達できます
- 開業後の集客はマッチングサイト「ミツモア」を活用し、順調に案件数を増やした事業者がいます
ハウスクリーニングの主な開業方法
ハウスクリーニングで独立する道は、開業費用を抑えて自由に運営できる「個人での開業」と、確立されたノウハウと看板で早期に安定できる「フランチャイズ(FC)への加盟」という2つに分かれます。
個人開業とフランチャイズ加盟のどちらを選ぶかは、「費用と自由度」を重視するか、「安心感とノウハウ」を重視するかで決まります。
個人で開業する場合の特徴
個人での開業は、開業時の資金を最小限に抑えられ、自分の理想とするサービスを自由に追求できる点が最大の特徴です。
特定の看板を背負わないため、屋号や料金設定、作業内容をすべて自分の裁量で決められます。一方で、集客や営業活動はすべて自力で行う必要があり、信頼を積み上げるまでの努力が求められます。
フランチャイズで開業する場合の特徴
フランチャイズでの開業は、本部のブランド力や確立されたノウハウを使うことで、未経験からでも早期に事業を軌道に乗せやすい点が特徴です。
大手チェーンでは、数週間の研修で清掃技術や接客マナーを学べる体制が整っています。開業直後から「有名店の看板」による信頼を得られます。
ただし、加盟金や保証金として200万円から500万円程度の開業資金が必要です。毎月数万円から十数万円のロイヤリティが発生する点は念頭に置く必要があります。
個人とフランチャイズのどちらを選ぶべき?
| 比較項目 | 個人開業 | フランチャイズ |
|---|---|---|
| 開業資金 | 30万円〜100万円 | 200万円〜500万円以上 |
| ロイヤリティ | なし | あり(固定または歩合) |
| 集客・営業 | 自分で行う | 本部からの支援あり |
| 自由度 | 高い | 本部のルールを遵守 |
「費用と自由度」を重視するなら個人開業、「安心感とノウハウ」を優先するならフランチャイズを選ぶべきです。
判断の目安
個人開業:すでに現場経験があり、独自のサービスを展開したい人
フランチャイズ:フランチャイズが持っているブランド・仕組みを使って独立開業したい人
個人開業を選び、ミツモアのようなマッチングサイトを使って集客の弱点を補うスタイルも選択肢の一つです。
関連記事:ハウスクリーニングマッチングサイト
ハウスクリーニングの開業に必要な資金
ハウスクリーニングの開業資金は、店舗を構える必要がないため、他の業種と比べて安く抑えられます。
個人開業なら30万円から100万円、フランチャイズなら300万円から500万円が目安です。
個人で開業する場合の開業資金
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 清掃道具・機材一式 | 30万円〜50万円 |
| 車両費(中古軽バンなど) | 30万円〜50万円 |
| 広告宣伝費(チラシ・Web) | 5万円〜15万円 |
| 損害賠償保険料(年額) | 1万円〜3万円 |
個人で開業する場合、開業時にかかる費用は30万円から100万円程度に収まります。
日本政策金融公庫のデータによれば、創業資金500万円未満で開業する人が全体の約4割を占めています。主な内訳は、洗剤や高圧洗浄機などの道具一式、移動用の軽自動車、そして当面の運転資金です。
事務所を自宅にすれば家賃負担もなく、道具一式を30万円程度で揃えて小規模から事業を開始することも可能です。
出典:日本政策金融公庫「創業に関する実態調査」
フランチャイズで開業する場合の開業資金
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 加盟金・保証金 | 100万円〜250万円 |
| 研修費・ノウハウ提供料 | 30万円〜100万円 |
| 本部指定の機材・消耗品 | 50万円〜100万円 |
| 月額ロイヤリティ | 3万円〜15万円 |
フランチャイズで開業する場合は、本部に支払う加盟金などを含めて、300万円から500万円程度のまとまった資金が必要です。
大手チェーンの「おそうじ本舗」を例に挙げると、加盟時に約300万円前後の費用が発生します。内訳は、ブランド使用料や技術研修費、本部が指定する機材一式の購入代金です。
開業後も、毎月3万円から15万円程度のロイヤリティを継続して支払う必要があります。個人開業に比べて損益分岐点が高くなる点に注意が必要です。
開業に必要な資金は、フランチャイズのプランによっても変わります。詳細は、フランチャイズ本部に問い合わせてください。
ハウスクリーニング開業資金の調達方法・利用できる助成金
開業資金の調達は、日本政策金融公庫の創業融資、自治体の制度融資、小規模事業者持続化補助金の3つを組み合わせることで、無理なく準備できます。
自己資金が足りない場合でも、公的な融資や補助金を使うことで、開業に必要な資金を工面できます。
資金の調達方法
| 調達先 | 特徴 |
|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 無担保・無保証で借りやすい |
| 自治体の融資制度 | 利子の一部を補給してくれる場合がある |
| ビジネスローン | 審査は早いが金利は高め |
資金を調達するには、金利が低く、実績のない個人事業主でも相談しやすい公的な機関を優先して検討すべきです。
主な調達先は、日本政策金融公庫、自治体の融資制度、ビジネスローンの3つです。
日本政策金融公庫の創業融資を利用する
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は、無担保・無保証人で最大7,200万円の融資枠があり、新しく事業を始める人にとって最も身近な選択肢です。
運転資金は4,800万円までとなっています。申し込みから融資実行までは約3週間から4週間ほどかかります。審査では事業にかかるお金の1割以上の自己資金を用意していることが望ましいとされています。
出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
自治体の融資制度を利用する
各市区町村が提供する「融資制度」は、自治体、銀行、信用保証協会の3つが連携して、個人事業主が安くお金を借りられるようにサポートする仕組みです。
自治体が利子の一部を負担してくれる「利子補給」があるため、通常の銀行融資よりも返済負担を抑えて資金を用意できる場合があります。
ビジネスローンを利用する
ビジネスローンは、銀行や消費者金融が提供する融資商品で、最短即日で審査結果が出るなど、急いで資金を手に入れたいときに役立ちます。
ただし、公的な融資に比べて金利が高く設定されています。あくまで一時的なつなぎ資金として考え、無理のない返済計画を立てる必要があります。
利用できる助成金
| 名称 | 補助額の目安 |
|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 最大50万円〜250万円 |
| 自治体の創業助成金 | 最大400万円(経費の2/3) |
| IT導入補助金 | 最大450万円 |
| キャリアアップ助成金 | 1人あたり40万円〜60万円 |
国や自治体が提供する助成金や補助金は、返済不要であるため、集客や機材の購入に使えます。
利用できる助成金は、小規模事業者持続化補助金、自治体の創業助成金、IT導入補助金、キャリアアップ助成金の4つです。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、チラシの作成やホームページ制作、機材の導入などの取り組みに使える補助金です。
通常枠では最大50万円(補助率2/3)ですが、創業して3年以内の人が使える「創業枠」であれば最大200万円まで補助額が引き上げられます。
出典:中小企業庁「小規模事業者持続化補助金」
自治体の創業助成金
東京都などの各自治体では、開業したばかりの事業者を対象に、事務所の家賃や広告費、人件費などを支援する独自の助成金制度を設けています。
例えば東京都の場合、経費の2/3(最大400万円)を最長2年間補助してくれる手厚い支援があります。採択率は10%から15%程度と低いため、計画書の準備が必要です。
出典:東京都「創業助成事業」
IT導入補助金
IT導入補助金は、会計ソフトや予約管理システム、顧客管理アプリなど、仕事を効率化するためのITツールを導入する際にかかる費用の一部を国が負担してくれる制度です。
2025年度の補助額は最大450万円に及び、ツールの購入費用の半分から最大8割近くを補助してもらえます。事務作業の負担を減らしたい場合に役立ちます。
出典:経済産業省「IT導入補助金」
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、アルバイトなどの非正規の人を正社員に転換した際などに、1人あたり約40万円から60万円が支給される制度です。
開業後、事業が大きくなってスタッフを雇用する段階になったとき、人件費の負担を減らしながら組織を強化できます。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」
ハウスクリーニングの開業に必要な資格と許可
ハウスクリーニング業を始めるにあたって、法律で定められた必須の資格や免許はありません。
誰でもすぐに仕事を始めることができます。ただし、お客さんからの信頼を得たり、作業の幅を広げたりするためには、専門的な資格を持っておくことが有利に働きます。
あると有利になる資格
| 資格名 | 種類 |
|---|---|
| ハウスクリーニング技能士 | 国家資格 |
| ハウスクリーニング士 | 民間資格 |
| 電気工事士(第二種) | 国家資格 |
代表的な資格は、ハウスクリーニング技能士、ハウスクリーニング士、電気工事士(第二種)の3つです。
お客さんからの信頼を得るため、また作業の幅を広げるために、専門的な資格を持っておくことが有利に働きます。
ハウスクリーニング技能士
ハウスクリーニング技能士は、厚生労働省が認定する業界で唯一の国家資格です。
試験では、レンジフードの洗浄や床のワックスがけ、シミ抜きといった実技と学科が課されます。合格すれば「国が認めた専門家」として看板を掲げることができます。資格の取得には数万円の費用がかかりますが、技術力の証明になるため、他社との差別化に役立ちます。
出典:厚生労働省「技能検定制度」
ハウスクリーニング士
ハウスクリーニング士は、NPO法人日本ハウスクリーニング協会などが認定する民間資格です。
数日間の講習と試験を通じて、プロとして必要な基礎知識や道具の正しい使い方、環境に優しい洗剤の知識などを体系的に学べます。独立前に基本的な技術を身につけておきたい人や、資格という形で実績をアピールしたい人にとって、有効な選択肢となります。
第二種電気工事士
第二種電気工事士の資格を持っていると、エアコンの取り外しや取り付け、コンセントの交換といった電気工事を伴う作業が法律に基づいて行えるようになります。
ハウスクリーニングの現場ではエアコン掃除のついでに設置や修理を頼まれることも多いため、資格があれば仕事の単価を上げ、より多くのお客さんの要望に応えることが可能です。
開業に必要な届出
ハウスクリーニング業を開業する際、必要な届出は個人事業の開業・廃業等届出書と所得税の青色申告承認申請書の2つです。
特別な許認可は不要ですが、税金に関する基本的な手続きだけは行っておく必要があります。
開業届
新しく事業を始めたら、1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を管轄の税務署へ提出します。
開業届を出すことで、正式に個人事業主として認められます。銀行での事業用口座の開設や、屋号名義での契約がスムーズに進むようになります。手続き自体は簡単で、窓口だけでなく郵送やオンラインでも提出が可能です。
青色申告承認申請書
節税を考えるなら、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出しておく必要があります。
青色申告を行うと、最大65万円の所得控除が受けられるため、支払う税金を大幅に減らすことができます。複式簿記という帳簿付けが必要になりますが、最近は会計ソフトを使えば専門知識がなくても対応できます。節税効果が大きいため提出を推奨します。
ハウスクリーニングで開業する手順
ハウスクリーニングで開業する手順は、事業計画の作成、機材と車両の準備、開業届の提出、集客準備の4ステップで進めます。
事業計画を立てる
ハウスクリーニングは、エアコン掃除などの「在宅関連のクリーニング」と、退去後の掃除を行う「空室クリーニング」で収益モデルが大きく異なります。例えばエアコンクリーニングなら1台あたり7,000円から12,000円、浴室なら12,000円から15,000円が相場です。
参考までに、ミツモアでのエアコンクリーニングの成約単価を紹介します。
| 品目 | 料金相場 |
|---|---|
| 壁掛けエアコンクリーニング | 7,000円~8,500円/台 |
| 壁掛け(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 11,550円~13,860円/台 |
| 天井埋込1・2方向エアコンクリーニング | 15,000円~18,000円/台 |
| 天井埋込4方向エアコンクリーニング | 17,000円~20,000円/台 |
| 天井埋込1・2方向(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 15,840円~19,000円/台 |
| 天井埋込4方向(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 17,600円~21,000円/台 |
※出典:ミツモアの2024年1~12月の成約データ
エアコン掃除と浴室クリーニングを組み合わせて月40件ほど対応すれば、売上は約38万円となります。経費を除いても手元に30万円前後を残すという具体的な目標が見えてきます。
必要な機材と車両を揃える
仕事に必要な機材や車両を揃える際は、最初からすべて新品で揃えようとせず、最低限必要なものから優先して準備すべきです。
最低限必要なもの
- 移動用車両:軽バン(中古でも可)
- 機材:高圧洗浄機、掃除機、脚立
- 消耗品:洗剤各種、ブラシ、ウエス
特に移動用の車両は、機材や脚立を積み込める軽バンが適しています。中古であれば30万円から50万円程度で見つけることができます。
エアコンクリーニングを行うなら高圧洗浄機は必須ですが、洗剤やブラシ類は現場の状況に合わせて少しずつ買い足していくことで、開業資金を抑えられます。
開業届を提出する
必要な準備が整い、仕事を始める目処が立ったら、管轄の税務署へ開業届を提出して正式に個人事業主として開始します。
提出期限は開業から1ヶ月以内とされていますが、事前に書類を準備しておけば窓口での手続きは数分で終わります。開業届を出すことで、税務署から事業用の書類が届くようになります。
個人事業主向けの助成金や融資を申し込む際の証明書としても使えるようになります。後回しにせず早めに済ませておくことが重要です。
集客の準備をする
開業届の提出と並行して、最も重要となる「最初のお客さんを見つける方法」という集客の仕組みを構築します。
チラシのポスティングや知人への紹介も一つの手ですが、現在はインターネットを通じた集客が主流です。特にミツモアのようなマッチングサイトに登録しておけば、自分から営業に回らなくても、開業初日から見積もり依頼が届く環境を作れます。
ホームページを作る時間や予算がなくても、マッチングサイトを使うことで、開業直後の「仕事がない」という状況を解消できます。
関連記事:ハウスクリーニングマッチングサイト
ハウスクリーニングの開業で失敗を防ぐ準備事項
開業後のトラブルや「仕事が取れない」といった事態を避けるために欠かせないポイントを4つ解説します。
屋号を決めておく
屋号は自分のお店の名前であり、お客さんにどのようなサービスを提供しているかを一目で伝えるための看板となります。
ハウスクリーニング業の場合、名前に「クリーン」や「お掃除」といった言葉を入れることで、何をしている業者かがすぐに伝わるようになります。親しみやすさを重視するのか、プロとして技術力を強調するのかによっても選ぶ言葉は変わります。
覚えやすく、かつ誠実な印象を与える名前を付けることが、信頼獲得につながります。
保険に加入しておく
作業中の事故や物損トラブルから自分を守るために、損害賠償保険への加入は開業前に必ず済ませておくべきです。
保険の種類
- 賠償責任保険:作業中にお客さんの家財を壊したとき
- 受託物賠償責任保険:預かった品物を壊したり失くしたとき
作業中には、高価な家具を傷つけたり、エアコンの基板をショートさせてしまったりする可能性がゼロではありません。万が一のときに数百万円から数千万円の賠償を求められる場合があります。年額1万円から3万円程度の保険料は、事業を続けるための必要経費として計上すべきです。
開業支援サービスを利用する
技術や経営に不安がある場合は、プロのアドバイスやサポートを受けられる開業支援サービスを利用すべきです。
洗剤の正しい知識や最新のエアコン分解方法などを学べる講習、あるいは経営計画の立て方を教えてくれるセミナーが数多く存在します。経験者の知恵を借りることで、独学では気づけない落とし穴を未然に防ぎ、開業までの時間を短縮できます。
集客方法にあたりをつける
あらかじめ複数の集客ルートを想定しておくことが廃業を防ぐ鍵となります。
集客方法
- チラシ・ポスティング:近隣エリアを直接狙える
- 地域の不動産屋への挨拶:空室清掃の継続依頼が期待できる
- マッチングサイトの登録:開業直後でも広範囲から集客できる
特に、独立したばかりの頃は実績がないため、知名度に関わらず案件を提案できる環境が必要です。ミツモアのようなマッチングサイトであれば、営業の経験がなくても依頼主とつながれます。複数の集客方法と組み合わせて使うことで、仕事が途切れる可能性を減らせます。
ミツモアがハウスクリーニング開業後の集客に最適な理由
ハウスクリーニングで独立した直後の大きな壁は「実績がないためにお客さんから選ばれない」ことですが、ミツモアは課題を解決する仕組みを備えています。
開業直後から案件を得られる
ミツモアは、登録したばかりで実績がない事業者にも、ベテランと同じように案件を得るチャンスが平等に与えられる仕組みです。
通常のホームページや広告では、検索順位が上がるまでに時間がかかります。しかし、ミツモアなら登録当日からお客さんの見積もり依頼が届きます。
ミツモアは、業者を指名してお仕事を依頼する指名型ではなく、最大5社がマッチングされる相見積もり型の仕組みであり、価格だけでなく、事務所の近さやプロフィールの丁寧さといった要素で選ばれる可能性があります。実績ゼロからスタートする開業初期において、公平なチャンスは大きな強みです。
高額なフランチャイズ加盟金が不要
ミツモアを使えば、数百万円単位の加盟金を支払ってフランチャイズに頼らなくても、自分の力で集客を安定させることができます。
フランチャイズへの加盟は看板の安心感を得られる一方で、高額な開業資金と毎月のロイヤリティが大きな負担となります。一方、ミツモアは登録料や月額費用がゼロの成果報酬型です。毎月の固定費による負担を最小限に抑えられます。
浮いた資金を機材の充実や、さらなる広告宣伝に充てることで、個人開業として自由度を保ったまま事業を成長させることが可能です。
※料金形態はサービスによって異なります。ハウスクリーニングの場合はほとんどが成果報酬型です。サービス別の料金形態は下記に詳細を記載しています
関連記事:サービスごとの手数料を知りたい
見積もり依頼に返信するだけで営業できる
営業を自動化できるミツモアの仕組みを使えば、営業が苦手な人や現場作業で忙しい人でも、効率よく仕事を受注できます。
主な機能
- 自動応募システム:現場作業中でも見積もりを自動送信できる
- テンプレート機能:同じ内容を入力する手間を省ける
事前に条件を設定しておけば、お客さんの依頼に対してシステムが自動で見積もりを送ってくれます。チャンスを逃すことがありません。
電話での強引な売り込みや飛び込み営業をする必要もなく、興味を持ってくれたお客さんとチャットでやり取りをするだけで商談が進みます。営業にかかるストレスと時間を大幅に削れるため、本業である清掃作業に集中できる環境が整います。
個人事業主に適した案件が多い
ミツモアには、大手業者よりも「顔の見える個人」に頼みたいと考えている一般家庭のお客さんからの依頼が数多く寄せられています。
エアコン1台の掃除や浴室クリーニングといった単発の案件が多いため、1人で動いている個人事業主がスケジュールを柔軟に組みやすい点が特徴です。丁寧な対応を積み重ねることで口コミが自然に集まる仕組みになっており、一度満足してもらえれば次回の指名やリピートにつながります。
個人ならではの機動力と誠実さが正当に評価されるため、安定した事業基盤を築くのに適しています。
ミツモアで開業を成功させたハウスクリーニング事業者の事例
ここでは、「開業時にミツモアを選んだ」2人の事業者の成功事例を紹介します。どちらも特別な営業スキルや莫大な広告費を使ったわけではありません。ミツモアの仕組みと、誰でもできる具体的な行動の積み重ねで成功しています。
事例1:想成株式会社(神奈川県藤沢市・平野大輔さん)

クリーニング会社から独立した平野さんが直面したのは、「営業をどうすればいいのか分からない」という課題でした。技術力には自信がありましたが、継続的な取引先を見つけるのには時間がかかる見込みで、開業直後から安定収入を得られる目途が全く立たなかったのです。
「まずはネットでの集客から始めよう」。この判断が、平野さんの事業を成功に導きました。複数の集客サイトをリサーチする中で、平野さんがミツモアを選んだ理由は3つです。
- お客様との対話がしやすい:口コミに返信できる機能があり、コミュニケーションを重視できる
- プロに裁量がある:お客様との接点を作った後は、自分のスタイルで仕事ができる
- 営業スキルがなくても顧客と出会える:見積もり依頼が届くので、顧客獲得のチャンスがある
成果:開業1ヶ月で20件超の成約
累計550件以上(在宅300件以上、空室250件以上)を達成し、法人化を実現。県道沿いに店舗をオープンしました。
平野さんが成功した秘訣は、特別なスキルではありません。3つの基本的な行動の徹底です。
口コミへの返信を最重視することで、「またこの業者に頼みたい」という気持ちを生み出しました。平野さんは「お客様からの口コミに返信できるのが、ミツモアの素晴らしい点。御礼の気持ちを伝えることは、クリーニング事業においてとても大事なことです」と語ります。
自動応募システムで現場との両立を実現し、仕事になる可能性が高いお客様とのやりとりに集中できるようになりました。「ハウスクリーニングは現場に入ると忙しくて、なかなかメールのチェックや返信をする時間がとれない」という課題を、仕組みで解決したのです。
そしてコミュニケーション力を武器にしました。「メールやチャットの短い文面からもお客様の人柄がにじみ出てきます。お客様のお宅に上がるので、的確な距離感を測りつつコミュニケーションできるかどうかが非常に重要」と、技術だけでなく対話力を磨くことを重視しています。
法人化のタイミングで、平野さんはあえて実店舗を構えました。「ネットって便利だけれど、相手が見えない不安もある。webを介して弊社を知っていただいたら、今度は店舗にいらしていろいろとお話できるような、そんな地域密着型の事業展開をしていけたら」。Webで集客し、店舗で信頼を構築するこの戦略が、事業をさらに成長させています。
関連記事:ハウスクリーニング開業の成功事例「想成 株式会社」
事例2:HOME BASE(埼玉県富士見市・白石和也さん)

業界歴18年のベテランとして独立した白石さん。開業にあたって最も重視したのは、「Web集客の仕組み」でした。「独立開業する時、先輩たちの話をいろいろと聞く中でwebサイトを使った営業が大事だと認識していました」と、技術力に自信があっても、集客の仕組みがなければ安定経営はできないと考えていました。
しかし白石さんは、開業時からミツモアに登録しましたが、最初から順調だったわけではありません。「登録当初はなかなか成約できなかったのですが、自動応募が始まってから格段に成約できる案件が増えました」。最初は誰でも苦戦する。しかし、ミツモアの仕組みを活用し、試行錯誤することで成果は確実に上がるのです。
成果:月20件→月50件→月100件ペースへ成長
開業3年で安定した事業基盤を確立。口コミ70件以上、高評価を維持しています。
白石さんが実践したのは、3つの「誰でもできる」行動です。
まず自動応募システムで対応件数を最大化しました。「応募する手間をかけずに自動的に見積もりを返すことができるのは非常に楽。しかも、依頼段階でお客様自身が意向を細かくチェックして送るシステムなので、事業者とのマッチング度合いも高い」。現場作業中でも機会損失を防ぎ、対応可能件数が飛躍的に向上しました。
即レス対応で競合に差をつけました。「仮の予約が入った際、その日程確定などとにかくレスポンスの速さは重要」。お客様は複数の事業者に見積もり依頼しているため、スピードが成約の分かれ目になります。
そして口コミ返信を毎日のルーティンにしました。「昼間の現場仕事が終わった後、夜の事務作業のルーティンとして、いただいた口コミに目を通して返信を書いています。お客様に感謝の気持ちを伝えると同時に、安心感を高め、結果的に依頼者から選んでいただける情報につながっていく」。
白石さんが成約後にお客様から聞く言葉で印象的なのは、「業界での経験18年という実績が決め手だった」「ベテランだから」という声です。お客様は「価格」だけでなく「信頼できる理由」を探していることに気づきました。経験年数でなくても、プロフィールでの情報発信、口コミでの評価、対応の速さなど、信頼を示す方法は数多くあります。
関連記事:ハウスクリーニング開業の成功事例「HOMEBASE」
2つの成功事例から学べること
平野さんも白石さんも、開業時に「集客の仕組み」を最優先課題として認識し、ミツモアを選びました。そして両者に共通するのは、特別なスキルではなく「誰でもできる基本の徹底」です。
- 自動応募システムで、現場作業と集客を無理なく両立:ミツモアの機能を使うだけで実現可能
- 口コミ返信という「誰でもできること」が、信頼と次の仕事を生む:特別な才能ではなく、習慣の問題
- 「即レス対応」「コミュニケーション力」で差別化:経験年数に関係なく、意識と習慣で実践できる
「誰でもできる基本を徹底する」この意識があれば、ミツモアで成果を出すことができます。
ハウスクリーニングの開業に関するよくある質問
未経験でも開業できますか
ハウスクリーニングは特別な資格がなくても開業できるため、未経験からスタートして成功している人が多いです。
清掃技術は、専門のスクールに通ったり、開業支援サービスを利用したりすることで数週間から1ヶ月程度で習得できます。技術も大切ですが、それ以上にお客さんへの丁寧な対応や誠実さが評価に直結する仕事です。
未経験から独立し、ミツモアなどのサイトで高い評価を得て安定して稼いでいる事業者はたくさんいます。
開業にどれくらいの期間が必要ですか
早ければ1ヶ月程度、じっくり準備をしても3ヶ月以内には開業することが可能です。
清掃技術の習得に2週間から1ヶ月、道具や車両の準備に2週間、開業届などの事務手続きに1日といったスケジュールが一般的です。
集客の準備も並行して進める必要がありますが、ミツモアのようなマッチングサイトであれば登録当日から案件を提案できます。店舗を構える業種に比べて短期間で仕事を始められます。
一人で開業しても稼げますか
効率よく案件をこなす仕組みを作れば、一人での開業でも月商50万円以上を目指すことは可能です。
例えば、エアコンクリーニングであれば1台あたり1時間から1.5時間程度で完了します。1日に3から4件をこなすことができれば、日給3万円から4万円ほどになります。
移動時間や事務作業の時間をいかに削るかが鍵となりますが、自動応募システムなどのITツールを使って営業を効率化すれば、一人でも高い利益率を維持して稼ぎ続けることができます。
個人開業とフランチャイズはどちらがおすすめですか
「費用と自由度」を重視するなら個人開業、「安心感とノウハウ」を優先するならフランチャイズがおすすめです。
個人開業とフランチャイズの比較
| 項目 | 個人開業 | フランチャイズ |
|---|---|---|
| 開業資金 | 30万円〜100万円 | 200万円〜500万円 |
| ロイヤリティ | なし | あり |
| 自由度 | 高い | 本部のルールあり |
自己資金を抑えて自分流のサービスを作りたい人は個人開業が向いています。一方、まとまった資金があり、一から集客方法を考えるのが苦手な人はフランチャイズが適しています。
個人開業の低い費用と、ミツモアの集客力を組み合わせるスタイルが、負担を抑えた成功パターンとして定着しています。
開業後すぐに仕事は取れますか
マッチングサイトを使えば、開業初日から見積もり依頼を受け取り、すぐに仕事を得られる可能性があります。
自分でチラシを配ったりホームページを作ったりする場合、最初のお客さんが来るまでに数ヶ月かかることも珍しくありません。
しかし、ミツモアのようなサイトには毎日多くのお客さんが集まっています。実績がなくても丁寧なプロフィールと迅速な対応を心がければ、開業直後から案件を受注することが可能です。
ハウスクリーニング開業時の集客なら「ミツモア」
ミツモアは、営業経験がない個人事業主でも開業初日から案件を得られ、高額な加盟金なしで集客を自動化できる、ハウスクリーニング開業に最適なツールです。
ハウスクリーニングでの独立開業を成功させる最大の鍵は、技術力以上に「いかにお客さんを安定して得るか」という集客の仕組みにあります。個人での開業は、フランチャイズに比べて開業資金を大幅に抑えられる一方で、看板がないため集客に苦戦しやすい課題がありました。しかし、ミツモアという選択肢を加えることで、不安は解消されます。
営業の自動化、実績がなくても選ばれる公平な仕組み、そして誠実な仕事が正当に評価される口コミ機能。ミツモアを使えば、営業の経験がない人でも開業初日からプロとして一歩を踏み出すことができます。
集客の不安を取り除き、本業である清掃の仕事で多くのお客さんに喜んでもらう。理想の独立生活を、ミツモアから始めることができます。
ハウスクリーニングで元請け仕事を増やす効果的な方法は?元請け化に成功した事例も紹介
ハウスクリーニングで元請け仕事を増やす効果的な方法は?元請け化に成功した事例も紹介
下請けとして働き続けても、手数料が引かれて手元に残る利益は少なく、繁忙期と閑散期の差で資金繰りに苦しむ。多くのハウスクリーニング業者がこの状況に直面しています。
「営業力を強化する」「ホームページを作る」といった一般論では元請け化できません。しかし、資金も集客にかけられる時間が限られた方でも実践できる元請け化の方法があります。
この記事では、初期費用をかけずに始められる集客方法、下請けを続けながらリスクを抑えて元請けを増やす考え方、そしてハウスクリーニングに強いマッチングサイト「ミツモア」での具体的な成功事例を解説します。
この記事の要約
- SNS・マッチングサイト・Googleビジネスプロフィールなど初期費用を抑えて始められる集客方法があります
- マッチングサイトの「ミツモア」では見積もりを自動送信できる自動応募機能があり、初期費用も無料であるため、手間をかけずに元請け案件を取れます
- いきなり全ての仕事を元請けに切り替えるのではなく、下請けを続けながら少しずつ元請けの比率を高めることでリスクを抑えて元請け化できます
ハウスクリーニング業界の現状
ハウスクリーニング業界は開業率が高い一方で廃業率も高く、需要はあるものの正しい経営戦略なしでは生き残れない業界です。
ハウスクリーニングの需要は増加している
ハウスクリーニングを含む生活支援サービス市場は、高齢化と共働き世帯の増加により2024年度以降も拡大を続けており、年間6,100億円規模に達しています。
矢野経済研究所の調査(2024年)によれば、市場規模は2023年度時点で前年比104.2%(5,633億円)を記録しました。当時はすでに6,100億円規模への拡大が見込まれており、予測通り右肩上がりの成長トレンドが続いています。
現在ハウスクリーニングを利用したことがない人でも「今後利用したい」と考える層が3割近くに上っており、市場には依然として大きな潜在需要があります。
出典:矢野経済研究所「住まいと生活支援サービスに関する調査(2024年)」
開業も廃業も多い業種である
ハウスクリーニング業界は年間開業率6.2%と参入しやすい反面、廃業率4.8%と撤退も多く、業者の入れ替わりが激しい業種です。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| ハウスクリーニングの年間開業率 | 6.2% |
| ハウスクリーニングの年間廃業率 | 4.8% |
| 全業種平均の年間開業率 | 4.4% |
| 全業種平均の年間廃業率 | 3.5% |
ハウスクリーニングを含む生活関連のサービス業では、年間の開業率が6.2%と全業種平均(4.4%)を上回る一方、廃業率も4.8%(平均3.5%)と高い水準にあります。少ない資金で資格がなくても始めやすい反面、集客や採算に失敗して短期間で撤退する業者が多い状態です。
特に一人親方のような小規模な業者は、統計に表れない入れ替わりも多く、現場での競争は数字以上に激しいと言えます。廃業理由としては、「安定した集客のルートがない」「価格競争で利益が出ない」「繁忙期と閑散期の資金管理に失敗した」など、経営面の課題が大半を占めます。
需要はあるものの、正しい経営戦略を知らないと続けられない業界であり、元請けとして成功するには綿密な戦略が必要です。
出典:中小企業庁「開廃業の状況(2024年)」
ハウスクリーニングの元請けと下請けのメリット・デメリット
| 比較項目 | 元請け(直接契約) | 下請け(業務委託) |
|---|---|---|
| 一件あたりの単価 | 高い | 低い |
| 営業活動 | 自分で集客する | 不要 |
| 仕事の自由度 | 高い(自分で決める) | 低い(指示に従う) |
| 収入の安定性 | 自分次第 | 取引先次第 |
元請けは「単価が高く自由度も高いが、営業が必須」。対して下請けは「営業不要だが、単価が低く自由度も低い」。それぞれのメリットとデメリットを整理します。
元請けのメリット・デメリット
元請けの最大のメリットは、顧客と直接やり取りすることで高い利益率を得られる点にあります。
マッチングサイト「ミツモア」のエアコンクリーニング相場は以下の通りです。
| 品目 | 料金相場 |
|---|---|
| 壁掛けエアコンクリーニング | 7,000円~8,500円/台 |
| 壁掛け(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 11,550円~13,860円/台 |
| 天井埋込1・2方向エアコンクリーニング | 15,000円~18,000円/台 |
| 天井埋込4方向エアコンクリーニング | 17,000円~20,000円/台 |
| 天井埋込1・2方向(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 15,840円~19,000円/台 |
| 天井埋込4方向(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 17,600円~21,000円/台 |
※出典:ミツモアの2024年1~12月の成約データ
下請け仕事ではマージンが差し引かれますが、元請け仕事であれば、顧客が支払う費用がそのまま売上になります。同じ作業をしていても、年間にすれば大きな収入差が出る計算です。
また、提供するサービスの範囲や作業の日時、エリアなどを自分の裁量で決められるため、自由な働き方が可能になります。自社の強みを活かした差別化もしやすく、顧客との信頼関係を築ければ営業費用をかけずに仕事が入り続ける好循環も生まれます。
一方で、集客の全てを自分で行う責任も生じます。チラシやWebサイトの管理といった作業が必要になり、軌道に乗るまでは受注が不安定になることもあります。加えて、クレーム対応や代金回収、損害賠償保険への加入なども、全て自分の責任で解決しなければなりません。
下請けのメリット・デメリット
下請けは、自分で営業をしなくても定期的に仕事が回ってくる「手間のかからなさ」が最大のメリットです。
開業したばかりで営業のやり方が分からない時期でも、技術さえあれば現場に出て仕事に従事できるため、営業が苦手な人にとっては参入しやすい形態となります。取引先を持っていれば常に一定の案件を受注できるため、売上がゼロになる危険性も低めです。
しかし、元請けの仕事と比較して、自分の取り分が少ないことは避けられません。手数料やマージンが差し引かれるため、洗剤代や交通費を考慮すると職人の手元に残る利益はごく僅かになる場合もあります。
1日に何件も現場を回らなければ十分な収入にならない「薄利多売」の状態に陥りやすいのが実情です。
さらに、業務内容や品質基準、スケジュールは元請けの指示に従う必要があります。自社の裁量でサービスを変更したり、独自の強みを打ち出したりすることは難しく、いつまで経っても自社の顧客資産が蓄積されないというリスクも抱えています。
ハウスクリーニングで元請け仕事を獲得する方法
元請け仕事を獲得する方法は、SNSでの作業実績発信、マッチングサイト登録、不動産会社への営業、Googleビジネスプロフィール登録、リピート・紹介の仕組み化の5つです。
- SNSで作業実績を発信する
- マッチングサイトに登録する
- 地域の不動産会社に営業する
- Googleビジネスプロフィールに登録する
- リピート・紹介で自然に問い合わせが入る状態を作る
チラシ配りや飛び込み営業のような、断られるストレスが大きい方法は必ずしも必要ではありません。現代では、スマートフォンを使って技術力をアピールしたり、集客を自動化できる仕組みを利用したりすることで、安定して元請け仕事を受けることが可能です。
SNSで作業実績を発信する
SNSで施工前後の写真を継続的に投稿することで、技術力と信頼性を視覚的に示し、地元の見込み客から直接問い合わせが得られます。
特にInstagramやX(旧Twitter)は、ハウスクリーニングとの相性が抜群です。施工前の汚れがひどい状態と、施工後のピカピカになった状態の写真を並べて投稿するだけで、言葉で説明するよりも説得力のある営業資料になります。
投稿を続けることで、以下のような印象を伝えられます。
- 技術力:どのような汚れをどの程度落とせるかが一目で分かる
- 誠実さ:作業中の様子や道具の手入れを載せることで安心感を与えられる
- 親近感:職人の顔や人柄が見えることで、依頼したいと思ってもらえる
最初はフォロワーが少なくても問題ありません。ハッシュタグに「#(地域名)ハウスクリーニング」を入れることで、地元の困っている顧客の目に留まる可能性が高まります。
マッチングサイトに登録する
マッチングサイトへの登録により、営業活動を自動化でき、登録したその日から見積もり依頼が届く状態を作れます。
「ミツモア」などのマッチングサイトには、ハウスクリーニングを頼みたいと考えている意欲の高い顧客が集まっています。登録して自分のプロフィールを公開しておくだけで、自分から営業をしなくても見積もりの依頼が届くようになります。
マッチングサイトを活用するメリットは以下の通りです。
- 集客の自動化:サイトが代わりに顧客を集めてくれる
- 実績の蓄積:作業後の口コミが蓄積され、それが次の依頼を呼ぶ看板になる
- 決済の安心:支払いシステムが整っているため、代金の未回収リスクを減らせる
地域の不動産会社に営業する
地域の不動産会社への営業により、空室清掃などの継続的な受注と安定収入が得られます。
地域の不動産会社は、管理物件の退去後の清掃を行う業者を探しています。既存の業者に不満を持っていたり、繁忙期で人手が足りなかったりすることもあるため、営業経験がなくても実力があれば契約を獲得できる可能性があります。
アプローチの際のポイントは以下の通りです。
- 先方の仕事が落ち着く午後のタイミングに訪問
- 写真付きの名刺や実績のわかる資料を持参
- 「急ぎの案件や、既存業者が対応できない時だけでも」という姿勢で
Googleビジネスプロフィールに登録する
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)への登録により、地元で検索する見込み客に自社情報が地図と一緒に表示され、問い合わせが増えます。
Googleビジネスプロフィールに登録することで、「(地域名) エアコンクリーニング」と検索した際に、地図と一緒に自社の店舗情報が表示されるようになります。
ただし、表示率を高めるためには、口コミ返信などの運用が必要なため、成果を出すためには少し手間がかかります。登録時に最低限やっておくべきことは以下の通りです。
- 基本情報の設定:住所、電話番号、営業時間を正確に入れる
- 写真の投稿:外観(看板)や作業風景、スタッフの笑顔の写真を載せる
- 最新情報の更新:キャンペーン情報や作業事例を定期的に投稿する
リピート・紹介で自然に問い合わせが入る状態を作る
リピート・紹介の仕組み化により、営業費用をかけずに継続的な受注が得られ、長期的な経営安定につながります。
最終的に目指すべき理想的な元請け仕事の取り方は、一度作業した顧客からのリピートや紹介だけでスケジュールが埋まる状態です。新規の集客には費用も労力もかかりますが、既存顧客からの「リピート依頼」であれば、営業コストはほぼゼロになります。
リピートを生むための具体的な工夫は次の通りです。
- アフターケアのアドバイス:作業後に「きれいに保つコツ」を伝える
- 次回時期の案内:汚れやすい時期の1ヶ月前などにハガキやメッセージを送る
- 紹介カードの配布:知人を紹介したくなるような特典を用意する
ハウスクリーニングで元請けになるポイント
元請けになるポイントは、下請けを続けながら段階的に増やす、即効性の高い方法から始める、閑散期に準備を進める、競合と違う強みを作るの4つです。
- 下請けを続けながら段階的に元請けを増やす
- 即効性の高い方法から始める
- 閑散期に元請け化の準備を進める
- 競合と違う強みを作る
いきなり全ての仕事を元請けに切り替える必要はありません。現在の安定した収入源を保ちつつ、空いた時間を使って少しずつ自社の顧客を増やしていくことが、失敗しないための現実的な進め方です。
下請けを続けながら段階的に元請けを増やす
元請け化への移行は、現在の仕事を続けながら段階的に進めることで、資金繰りの悪化を防ぎながら確実に元請け比率を高められます。
いきなり下請けをゼロにしてしまうと、集客が軌道に乗るまでの資金繰りが苦しくなる危険があります。まずは「売上の2割を元請けにする」等の現実的な目標を立ててください。徐々に比率を上げていくことで、今の生活レベルを保ちながら確実に元請け化を目指せます。
即効性の高い方法から始める
即効性の高いマッチングサイトから始めることで、登録したその日から見積もり依頼が届き、早期に「自分で仕事を取る」経験を積めます。
営業に慣れていない時期は、自分で一から仕組みを作るよりも、すでに仕組みが整っている方法から手をつけるべきです。
元請け仕事を取る方法としてありがちな「ホームページの作成」や「SEO対策(検索結果で上位に出す工夫)」は、成果が出るまでに数ヶ月から1年以上の時間がかかります。まずは「ミツモア」のようなマッチングサイトを活用することが重要です。
閑散期に元請け化の準備を進める
閑散期に種まき活動を行うことで、次の繁忙期に高い単価で仕事を受ける準備が整い、年間を通じた収入の安定化につながります。
仕事が落ち着く閑散期は元請け化の準備を進める絶好のタイミングです。エアコンクリーニングの需要が落ち着く秋などは、現場の作業が減って時間が作りやすくなります。
閑散期に「SNSの過去の作業写真を整理する」「不動産会社への挨拶回りに行く」「マッチングサイトへの登録だけ済ませる」といった種まきにより、次の繁忙期に備えられます。
【補足】閑散期の収入減リスクへの対策
事務所や飲食店などの「非住宅」の顧客を開拓したり、近年需要が増えている墓石クリーニングや車内のクリーニングなど多角化を進めることで、年間を通じた収入の安定化を図ることができます。
出典:中小企業基盤整備機構(J-Net21)「開業ガイド」
競合と違う強みを作る
独自の強み(専門性、安心感、利便性)を持つことで、価格競争に巻き込まれず適正価格でも選ばれる事業者になれます。
多くの中から選ばれるためには、価格の安さだけで勝負するのではなく「依頼する理由」を作る必要があります。大手や他社と同じサービス内容では、どうしても価格競争に巻き込まれて利益が削られてしまいます。
「女性スタッフが必ず同行する」「夜間・早朝の作業も対応できる」「特定の機種に非常に詳しい」といった独自の強みを持つことで、適正な価格でも納得して依頼してくれる顧客が集まります。
強みを作るための視点として以下が挙げられます。
- 専門性:ドラム式洗濯機や特殊なエアコンに特化する
- 安心感:損害保険の加入や、作業内容の徹底的な事前説明を行う
- 利便性:LINEで簡単に予約ができ、返信がどこよりも速い
ハウスクリーニングで元請けとして成功している事例
元請けとして成功している事業者に共通するのは、Web集客プラットフォームを活用し、即レスと丁寧な対応で顧客との信頼関係を築くスピードが速いという点です。
- 有限会社アセンション
- 大成技研株式会社
- クリシア
下請け中心の働き方から脱却し、元請け案件を増やすことで事業を拡大させた方々がいます。技術の高さはもちろんのこと、Web集客プラットフォームを賢く活用し、顧客との信頼関係を築くスピードが非常に速いことが共通点です。具体的な3つの事例から、成功のヒントを探ります。
有限会社アセンション

有限会社アセンションは、Web集客開始から4ヶ月で成約金額150万円を達成し、即レスと柔軟な対応により27件の高評価レビューを獲得しました。
もともとは下請け業務や紹介による依頼が中心で、仕事がある時期とない時期の差が激しいことが悩みでした。Web集客プラットフォームに登録し、現場の空き時間を使って丁寧に見積もり対応を行ったところ、短期間で大きな成果に繋がりました。
成功の背景にある具体的な行動は以下の通りです。
- 即レスの徹底:依頼が届いたらすぐに返信する体制を整えた
- 柔軟な顧客対応:顧客の細かい要望に最大限応える姿勢を貫いた
- 口コミの蓄積:一つひとつの現場を丁寧に行い、27件の高評価レビューを獲得した
迅速な対応が顧客の安心感を生み、家族や大家を紹介されるという好循環が生まれています。
関連記事:有限会社アセンション 事例記事
大成技研株式会社

大成技研株式会社は、競争が激しい大阪エリアにおいて成約率27%を維持し、女性代表の強みと誠実なメッセージで法人顧客も開拓しました。
創業2年目で新規の顧客を増やす必要があった同社は、飛び込み営業などの時間のかかる方法ではなく、Web集客をメインの営業ルートに据えました。女性代表という強みを活かした安心感の提供と、誠実なメッセージのやり取りで着実に案件を増やしています。
主な戦略と効果は以下の通りです。
| 実践した戦略 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 女性代表の強みを強調 | 単身女性や主婦層からの信頼を獲得 |
| 手頃な価格提案 | 初めて依頼する方のハードルを下げた |
| 法人顧客の開拓 | 不動産管理会社からの受注も増加 |
手数料を「効率の良い広告費」と捉え、営業にかかる時間を現場作業に充てることで、月間20件を超える安定した受注を実現しています。
関連記事:大成技研株式会社 事例記事
クリシア
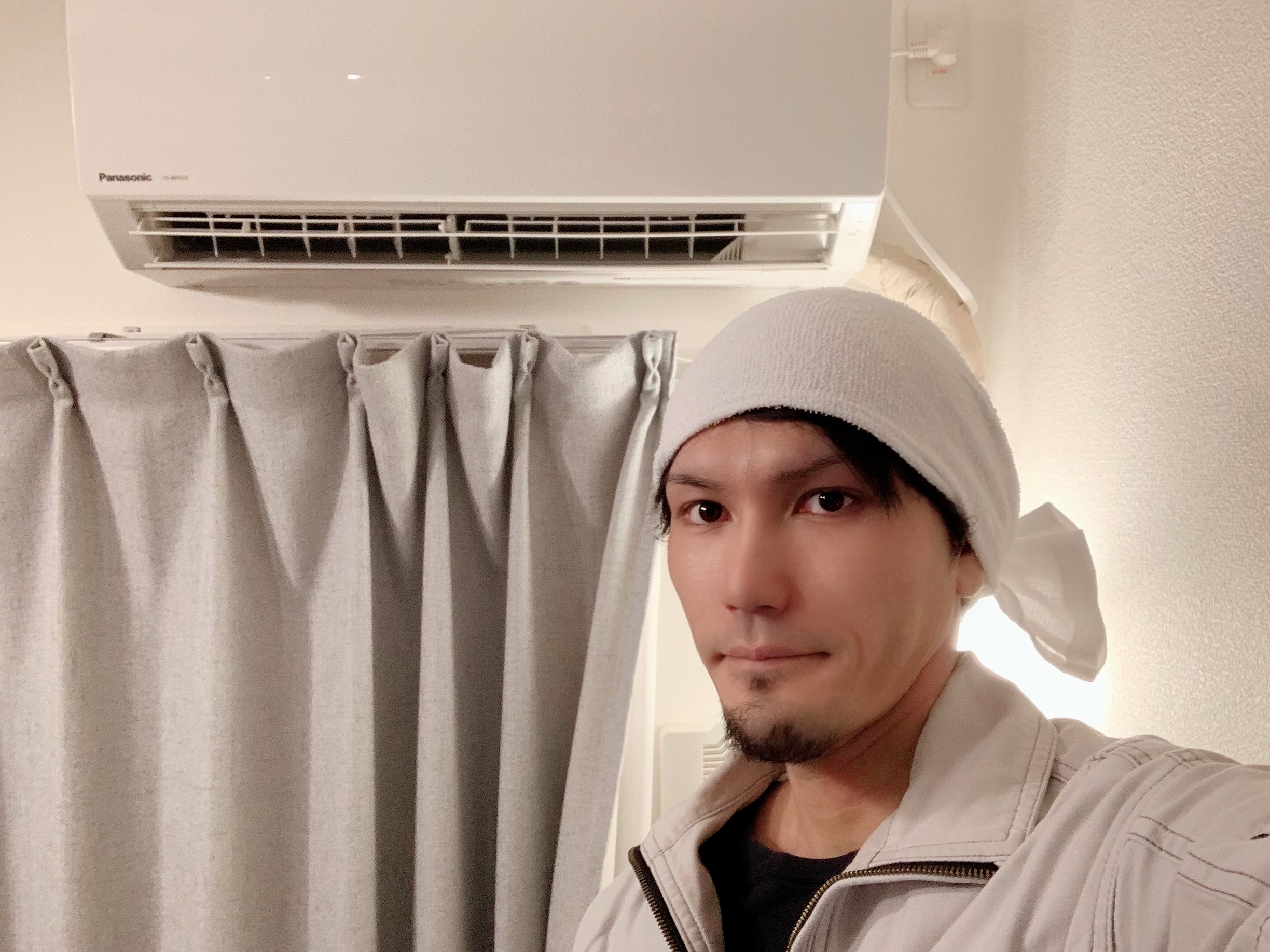
クリシアは、自動集客方式により営業の仕組みを自動化し、月間約30件の成約を継続しています。
現場作業で忙しい職人は、見積もりを作る時間を持つのが大変です。クリシアでは事前に条件を設定して自動で見積もりを送る「自動集客方式」を導入し、作業中であってもチャンスを逃さない体制を作りました。
成功を支えている独自の工夫は以下の通りです。
- 安心料金制の導入:料金体系を分かりやすく標準化した
- 事前の詳細把握:エアコンの型番などを事前に把握し、現場トラブルを防いだ
- エリアの限定:アフターフォローが届く範囲に絞り、地域密着を徹底した
年間1,000件以上の施工実績を支えているのは、大手には真似できない細やかなコミュニケーションと、効率的な営業の仕組み化にあります。
関連記事:クリシア 事例記事
ミツモアがハウスクリーニングの元請け化に最適な理由
ミツモアは、営業活動を自動化、実績ゼロでも案件獲得可能、営業スキル不要、成功報酬型という4つの特徴により、元請け仕事の獲得に最適です。
- 営業活動を自動化できる
- 実績がなくても案件を獲得できる
- 営業スキルがなくても見積もりが届く
- 案件が取れた時だけ手数料が発生する
ミツモアであれば、元請け仕事を取るときにハードルになりがちな「集客」と「営業」の手間や、投資リスクが一切かかりません。
営業活動を自動化できる
ミツモアの「自動応募」機能により、現場で作業をしている間もシステムが自動で見積もりを送信し、営業機会を逃しません。
通常、元請け案件を取るには、問い合わせにいちいち返信したり、電話をかけたりする必要があります。ミツモアでは、あらかじめ設定した条件に合う依頼が来ると、自動で見積もりが送信される「自動応募」という独自の機能があるため、チャンスを逃すことがありません。
自動応募で得られるメリットは以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 見積もり送信の自動化 | 依頼に対して自動で見積もりが届く |
| テンプレート機能 | メッセージを打ち込む手間を省ける |
| 営業ストレスの軽減 | 電話営業などの心理的負担がない |
| 受動的な案件獲得 | 待っているだけで集客の機会が増える |
日中は現場が忙しくて営業活動に時間を割けない方でも、効率的にスケジュールを埋めることが可能です。
実績がなくても案件を獲得できる
ミツモアは相見積もり型のマッチングサイトであり、口コミがゼロの状態でも顧客に見積もりを提示でき、選ばれるチャンスがあります。
相見積もり型のマッチングサイトは、一度の依頼に対して最大5社などの決まった数の業者が提案を送る仕組みです。一方で、直接応募型マッチングサイトは、顧客が業者のプロフィールや口コミを見て、気に入った一人を直接選んで予約する仕組みとなります。
ミツモアは相見積もり型のマッチングサイトであり、たとえ口コミがゼロの状態であっても、顧客に見積もりを提示することができます。
実績がゼロの段階でも、見積もりの提案文で「なぜ適正価格なのか」を丁寧に説明したり、過去の実績をしっかりアピールすれば、選ばれるチャンスは十分にあります。
営業スキルがなくても見積もりが届く
ミツモアではメッセージテンプレートを作成できるため、派手な営業トークがなくても技術力と安心感を確実にアピールできます。
顧客が求めているのは、派手な営業トークではなく「技術力」と「安心感」です。ミツモアでは、システム上でメッセージのテンプレートを作成することができます。
メッセージテンプレートを使えば、その場の営業は不要で、口下手な方もしっかり自分の強みをアピールすることができます。
案件が取れた時だけ手数料が発生する
ミツモアは初期費用や月額料金がかからず、仕事が成立して初めて手数料が発生する成功報酬型のため、金銭的なリスクがありません。
ミツモアの料金体系はサービスによって異なりますが、ハウスクリーニングの多くは仕事が成立して初めて手数料が発生する「成功報酬型」です。WEB広告やチラシは、広告費用がかかることが一般的ですが、ミツモアは初期費用や月額料金がかかりません。
売上が出てから手数料を支払うモデルなので、リスクを抑えて元請け化に挑戦できます。「チラシを撒いたけれど反応がなかった」「広告費だけ払って赤字になった」という失敗をする心配がなく、安心して事業をスタートさせられます。
ミツモアの手数料について、詳しく知りたい方は以下のページも参考になります。
関連記事:サービスが成約課金型なのか応募課金型なのかを知りたい
ハウスクリーニングで元請けになるべきか判断する基準
元請けになるべきかどうかは、営業活動への適性と収入最大化の優先度によって判断すべきです。
今のまま下請けを続けるか、思い切って元請けに挑戦するかは、自分の理想とする働き方や性格によって決めるべきです。無理に元請けを目指すことが正解とは限りません。
下請けを続けたほうがいい人
営業活動が苦痛で安定を最優先したい方は、下請けを続けるほうが充実感を得られます。
現場での作業そのものが大好きで、営業や顧客対応に全く興味が持てない方は、下請けを続けるほうが充実感を得られるかもしれません。下請けの最大の魅力は、現場の仕事さえ完璧にこなせば売上が約束される点にあります。
具体的には、以下のような特徴に当てはまる人です。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 営業がとにかく苦痛 | 自分で仕事を探すことが大きなストレス |
| 事務作業が苦手 | 見積もりや請求書の作成を負担に感じる |
| 安定を最優先したい | 収入の変動を極端に避けたい |
集客の悩みや事務作業に時間を取られたくない職人であれば、下請けの仕事を続ける方がよいかもしれません。
元請けになったほうがいい人
自分の技術を適正価格で評価してほしい、収入を最大化したい、働き方を自由にしたいという方は、元請け化に踏み出すべきです。
同じ現場作業をしていても、元請けになるだけで収入の取り分は大きく変わります。下請けで手数料を引かれ続ける現状に疑問を感じている方や、自分のペースで納得のいくサービスを顧客に届けたい方は、元請けになることで大きな満足感を得られます。
以下のような思いがある方は、元請け化に踏み出すべきです。
- 収入を最大化したい:中抜きされる手数料を自分の利益にしたい
- 直接感謝されたい:顧客の笑顔を直接見て、やりがいを感じたい
- 働き方を自由にしたい:作業の時間や休みを自分でコントロールしたい
元請けになれば、自分が頑張った分だけ売上が上がり、蓄積された口コミが一生の財産になります。
判断のポイント
迷っている方は、まずは下請けの仕事を8割残したまま、残り2割でミツモアなどの元請け案件を受けてください。直接受注の「利益の高さ」を肌で感じてから判断しても遅くはありません。
ハウスクリーニングの元請けに関するよくある質問
元請けへの移行を考える際に、多くの職人が抱く疑問は、初期費用、下請けとの並行、集客期間、営業スキルの4つです。
- 元請けになるための初期費用はどれくらいかかりますか?
- 下請けの仕事を続けながら元請けもできますか?
- 元請けとして集客できるまでどれくらい時間がかかりますか?
- 営業が苦手でも元請けになれますか?
直接顧客と契約するとなると、これまで意識しなかった実務面の不安が出てくるものです。一つひとつ具体的に確認して、不安を解消しておきます。
元請けになるための初期費用はどれくらいかかりますか?
ミツモアのようなマッチングサイトを活用する場合、初期費用は実質ゼロ円でスタートできることがほとんどです。
自分でホームページを作成したりリスティング広告を出したりする場合は、制作費として30万円から50万円、月々の広告費として5万円以上の出費が一般的です。しかし、ミツモアは登録料や月額料金が一切かからないため、手元の資金を減らすことなく元請けの集客を始められます。
ただし、マッチングサイトによっては、月額料金が発生するタイプもあるため、事前に料金形態を確認することが重要です。
また、事故に備える「損害賠償保険」への加入は、元請けとして活動するなら入っておいた方が安心です。加入される方は保険料だけが最低限発生するものと捉えておくとよいでしょう。
下請けの仕事を続けながら元請けもできますか?
はい、下請けで安定した収入を保ちながら、空いた時間で元請け案件を受けることは十分可能です。
むしろ、いきなり下請けを辞めるのではなく、まずは週に1〜2件程度から直接依頼を受ける「二足のわらじ」で始めるのが最も安全な方法です。ミツモアなら「指定日だけ案件を受けたい」といったスケジュールの調整もスマホ一つで簡単にできるため、現在の仕事に支障をきたす心配もありません。
元請けとして集客できるまでどれくらい時間がかかりますか?
ミツモアを活用すれば、登録したその日から見積もりの依頼が届き、早い方では数日以内に成約しています。
自社サイトを育てて検索結果の上位に表示させるには半年から1年以上の時間がかかりますが、すでに集客力のあるサイトを利用すれば、時間をかけずに元請け案件を獲得できます。登録から4ヶ月で150万円を成約した事例もあり、行動次第ですぐに結果を出せるのが強みです。
営業が苦手でも元請けになれますか?
はい、営業スキルがなくても「誠実さ」と「速さ」さえあれば元請けとして成功できます。
元請けに必要な営業とは、巧みな話術ではなく「迅速に対応すること」と「作業内容を丁寧に説明すること」です。ミツモアのようなチャット形式のやり取りなら、事前に用意した文章をテンプレートとして使うことができ、直接話すのが苦手な方でもストレスなくコミュニケーションが取れます。
ミツモアならハウスクリーニングで元請け仕事が取れる
ミツモアは、初期費用ゼロ、営業の自動化、口コミの蓄積という3つの特徴により、リスクを最小限に抑えながら元請け化を実現できます。
ハウスクリーニングで下請けの低単価から抜け出し、収入を増やすための最も確実な道は「マッチングサイトへの登録」です。中でもミツモアは、元請け化に挑戦したい人にとって最適な選択肢の一つとなります。
- 初期費用が一切かからない
- 営業の自動化で現場作業に集中できる
- 蓄積された口コミが一生の財産になる
「自分には営業ができない」「失敗して資金を失うのが怖い」という不安を抱える必要はありません。ミツモアという仕組みを賢く利用することで、リスクを最小限に抑えながら、確かな技術を適正な価格で評価してくれる顧客と直接つながることができます。
下請けとして他人の看板で働き続けるのか、それとも自分の名前で勝負して利益を最大化させるのか。ミツモアなら元請けとしての一歩を踏み出せます。
ハウスクリーニングのマッチングサイト料金体系を比較!おすすめの選び方と月200万円達成した事例
ハウスクリーニングのマッチングサイト料金体系を比較!おすすめの選び方と月200万円達成した事例
チラシ配布やホームページ作成といった従来の方法では、営業に手間がかかり、成果が出るまでに時間がかかることも珍しくありません。
そこで鍵を握るのがマッチングサイトの存在です。しかし、中身を理解せずに登録すると、無駄な月額料金の支払いや大手との価格競争に巻き込まれる危険性があります。
料金体系やマッチング方式などマッチングサイトの仕組みや、それぞれのタイプの違い、実際にマッチングサイト「ミツモア」で活躍する事業者の成功事例を解説します。
この記事の要約
- マッチングサイトの料金体系は成約課金型・月額固定型・リード課金型の3つがあり、最もリスクを抑えられるのは成約課金型です
- 相見積もり型のサイトは大手やベテランに埋もれず、新規参入者でもお客さんの検討リストに残りやすくなります
- 自動応募機能を使えば現場作業中も集客が進み、実際に開始1カ月で200万円に近い成約額を実現した事例があります
ハウスクリーニングマッチングサイトとは
マッチングサイトは、ハウスクリーニングを依頼したいお客さんと仕事を受けたい事業者をネット上でつなぐ場所です。
マッチングサイトでは、事業者が営業をかける従来の方法とは逆に、お客さんからの依頼が向こうから届く構造になっています。
従来の集客方法
お客さん ← 事業者が営業をかける(チラシ、電話営業、飛び込み等)
マッチングサイト
お客さん → プラットフォーム ← 事業者(依頼が届く)
これまでは事業者が自ら足を運んでお客さんを探す必要がありました。マッチングサイトに登録すると、ハウスクリーニングを依頼したいお客さんの方から依頼が届くようになります。
マッチングサイトの基本的な流れ
マッチングサイトが条件に合う事業者とお客さんをつなぎ、見積もりや予約を経て作業に至る流れが基本です。
- 事業者登録:対応エリア、作業の内容、料金の目安などを設定
- 依頼投稿:お客さんがハウスクリーニングしたい場所、日時、予算を入力
- マッチング:条件に合う事業者へ通知が届く
- 見積もり提示:事業者が具体的な料金を提示
- 成約と作業:お客さんが業者を選んで予約・作業実施
- 評価:作業後に口コミが積み上がる
どのように事業者とお客さんをつなぐかは、サイトによって異なります。
一連のやり取りは基本的にネット上で完結するため、電話での対応や紙の見積書を作る手間が省けます。
プラットフォームの役割
マッチングサイトは、お客さんと事業者の間に立ち、依頼のマッチングだけでなく、決済や評価の管理まで行います。
サイトが担っている主な機能
- 広告やSEO対策といった集客機能
- 依頼と事業者を結びつけるマッチング機能
- クレジットカード等の決済代行機能
- 口コミの蓄積と表示機能
- お客さんとのメッセージ機能
従来は事業者が個別に用意する必要があった集客や決済といった機能を、プラットフォーム側が一括で担う構造になっています。
ハウスクリーニングマッチングサイトのタイプ
マッチングサイトは、「扱う仕事の範囲」と「お客さんとのつながり方」という2つの軸で分類されます。
- 対応カテゴリ:業界横断型 / 業界特化型
- マッチング方式:相見積もり型 / 直接応募型
対応カテゴリ
あらゆる業種が集まる業界横断型のサイトと、ハウスクリーニングだけに絞った業界特化型のサイトに分かれます。
業界横断型マッチングサイト
業界横断型マッチングサイトは、ハウスクリーニングだけでなく、庭の手入れや引っ越しなど幅広い依頼が集まるサイトです。
ミツモアなどの業界横断型は、あらゆる業種が揃っているため、仕事が落ち着く閑散期に、別のジャンルの案件を受けて売上を補える点が大きな強みです。
自身の仕事の幅を広げやすく、年間を通じた売上の平準化が期待できます。
業界特化型マッチングサイト
業界特化型マッチングサイトは、ハウスクリーニング専門の依頼だけが集中して届くサイトです。
特定のニーズに最適化されている一方で、閑散期に別の仕事で穴埋めをするといった柔軟な使い方は、業界横断型に比べると難しくなる場合があります。
マッチング方式
お客さんと事業者のつながり方にも違いがあります。「お客さんが依頼を投稿して事業者を待つ方式」と「お客さんが事業者を検索して選ぶ方式」の2つに分かれます。
相見積もり型マッチングサイト
相見積もり型のマッチングサイトは、一度の依頼に対して最大5社などの決まった数の業者が提案を送る仕組みです。
ミツモアなどの相見積もり型は、提案できる業者の数に制限があるため、口コミが圧倒的に多い大手やベテランに埋もれず、新規参入者でもお客さんの検討リストに残りやすくなります。
実績がまだ少ない独立直後の職人さんにとって、生存戦略として非常に有効な仕組みです。
競合の料金設定が可視化されるため、自分の価格戦略を考える際の参考にもなります。
【実践のコツ】新規参入者が選ばれるために
実績がゼロの段階でも、提案文で「なぜこの価格なのか」を丁寧に説明したり、清潔感のある写真を用意したりすることで、差別化が可能です。お客さんの悩みに寄り添う姿勢を見せれば、最安値でなくても選ばれるチャンスは十分にあります。
直接応募型マッチングサイト
直接応募型マッチングサイトは、お客さんが業者のプロフィールや口コミを見て、気に入った一人を直接選んで予約する仕組みです。
直接応募型は、既に評価を積み上げた業者が圧倒的に有利になる、実績重視の構造になっています。
口コミの数が少ないうちは依頼自体が届きにくい傾向にありますが、一度信頼を勝ち取れば、指名に近い形で高い成約率を維持できます。
自分のプロフィールを営業資料としてどれだけ作り込めるかが、勝負の分かれ道になります。
ハウスクリーニングマッチングサイトの料金体系の違い
ハウスクリーニングのマッチングサイトの料金体系は、大きく3つの種類に分けられます。
- 成約課金型
- 月額固定型
- リード課金型
成約課金型
成約課金型は、ハウスクリーニングの予約が確定したときにだけ手数料を支払う仕組みであり、仕事のない時期に赤字が出る心配がありません。
手数料はハウスクリーニングの予約が確定するまでかからないため、独立したばかりで手元の資金を減らしたくない職人さんに適しています。
手数料は売上が確定した後に支払う形になるため、手元の現金を確実に守りながら活動を続けられます。
【こんな人におすすめ】失敗を避けたい人
お客さん集めにお金を払ったのに一件も依頼が来ないという不利益がありません。仕事が決まった分だけ費用を出すため、無理のない経営でハウスクリーニングの依頼を増やせます。ミツモアも成約課金型の仕組みで利用することができます。
月額固定型
月額固定型は、毎月一定の金額を支払うことでハウスクリーニングの依頼を無制限に受け取れるため、多くの案件をこなすほど一件あたりの集客コストを抑えられます。
安定してハウスクリーニングの仕事を獲得できる力がある人にとっては、一件あたりの集客にかかる費用を低く抑えられる可能性があります。
一方で、仕事が取れない時期であっても決まった支払いは発生するため、駆け出しの時期には金銭的な負担が重くなりやすい点には注意が必要です。
リード課金型
リード課金型は、お客さんに見積もりを送るごとに費用が発生する仕組みであり、営業に自信のあるプロにとっては成約課金型よりも支払いの総額を安く抑えられる可能性があります。
見積もりを送った時点で費用がかかるため、成約しなかった場合でも支払いが発生する不確実性があります。
勝算のある案件を慎重に見極める目が必要になるため、ハウスクリーニングの現場数が足りない方には不向きな支払い方法です。
ハウスクリーニングマッチングサイトに向いている人
ハウスクリーニングのマッチングサイトは、お金をかけずに自分でお客さんを集める土台を作りたい職人さんに最適な仕組みです。
- 開業したばかりで集客基盤がない人
- 下請けや業務委託から脱却したい人
- フランチャイズの高額な手数料に悩んでいる人
- 閑散期の案件不足を解消したい人
- 口コミ実績を積み上げたい人
- 自分のペースで仕事をしたい人
開業したばかりで集客基盤がない人
お金を失う心配をせずに、登録するだけで地元の幅広い世代のお客さんに自分の存在を知ってもらえます。
独立したばかりの頃は「本当にお客さんが来てくれるのか」という不安がつきまとうものです。
マッチングサイトは仕事が決まった分だけ費用を払えば良いため、広告費を出したのに一件も依頼が来ないという失敗のリスクがありません。
集客のためにチラシを配る時間を、ハウスクリーニングの現場作業や技術を磨くことに充てられるため、精神的にも余裕を持って事業をスタートできます。
【こんな人におすすめ】初めての集客に悩む人
営業のノウハウや多額の資金がなくても、スマホ一台あれば今日から集客を始められます。リスクを背負わずに「まずは待つだけ」で地元の依頼が届く安心感は、開業初期の強い味方になります。
下請けや業務委託から脱却したい人
これまでは元請けから決められた単価で働くしかなかったかもしれませんが、マッチングサイトなら自分で納得できる適正価格を決められます。
万が一のトラブルの際も、自分で誠実にお客さんへ謝罪して解決できる環境の方が、精神的に楽だと感じる職人さんも多いです。
お客さんから直接「ありがとう」と感謝される喜びは、仕事のやりがいを大きく変えてくれるはずです。
元請けからのプレッシャーを離れて、自分の責任でハウスクリーニングを完結させて利益を増やせます。
フランチャイズの高額な手数料に悩んでいる人
売上の多くを引かれる仕組みから抜け出し、頑張った分だけ手元にお金を残せるようになります。
本部の看板ではなく自分自身のブランドを育てることで、健全な経営が続けられます。
高額なロイヤリティや本部への支払いに縛られず、自分の腕を信じて正当な報酬を受け取れるようになれば、ハウスクリーニングの仕事がもっと楽しくなるはずです。
閑散期の案件不足を解消したい人
サイトにはさまざまな仕事が届くため、これまで未経験だった作業に挑戦するきっかけにもなります。
たとえばエアコンクリーニングを主軸にしている方であれば、エアコンの依頼が減る時期は、クロスの張り替えなどの新しい分野の仕事を受けることができ、収入を安定させられます。
新しい技術を身につけて施工できる範囲を広げれば、一年中仕事が途切れない体制を整えられます。
一年を通じて売上の波を平準化していくことは、事業を安定して続けていくための大事なポイントになります。
関連記事:ハウスクリーニングは仕事がない?原因と仕事の取り方を解説
口コミ実績を積み上げたい人
ネット上で集めた高い評価は、名刺やチラシにも活用できる一生の資産になります。
お客さんからの生の声は、初めて依頼する人にとって何よりも安心できる証拠になります。
マッチングサイトでコツコツと良い評価を貯めていけば、それがデジタルの看板となって新しい注文を呼び込んでくれます。
ネット上の評判が良いことは、チラシや紹介などの別の場所での成約にも良い影響を与えてくれるはずです。
関連記事:口コミ効果とは?
自分のペースで仕事をしたい人
現場の状況や家族との時間を考えながら、スケジュールの主導権を自分の手で握れます。
「あと1時間後に次の案件を入れる」といった細かい調整も、自分の判断一つで決められます。
土日はしっかり休む、あるいは夕方以降は仕事を受けないなど、自分のライフスタイルに合わせた働き方を設計できるのは、独立した職人さんならではの特権です。
精神的なゆとりを持ちながら、長く健康にハウスクリーニングを続けていくための土台を作れます。
ハウスクリーニングマッチングサイトに向いていない人
価格以外の魅力を伝える工夫が苦手だったりする方には、不向きな場合があります。
- すでに十分な顧客基盤があり仕事に困っていない人
- 即レスポンスやこまめな連絡が難しい人
- 価格競争を避けたい人
- 対応エリアや仕事内容の条件が極端に限定的な人
すでに十分な顧客基盤があり仕事に困っていない人
リピーターや知人の紹介だけで予約が埋まっている状態では、手数料を払ってまで新しいお客さんを探す必要はありません。
新しい依頼を断らなければならないほど忙しいフェーズの方には、サイトのメリットは少ないと言えます。
即レスポンスやこまめな連絡が難しい人
返信を後回しにしたりする習慣がある方には向きません。
お客さんは複数のプロに見積もりを頼んでいることが多いため、返信が遅いだけで他社に決まってしまう確率が非常に高いです。
スマホの通知にすぐ反応して、チャットでやり取りを続けることができないと、せっかくの依頼を成約に繋げるのは難しいでしょう。
価格競争を避けたい人
相見積もりが基本となる場所では、どうしても他社と金額を比べられる場面を避けられません。
価格以外の付加価値を口コミや提案文で伝える工夫ができないと、安売り競争に巻き込まれて疲れてしまう恐れがあります。
自分の技術を安売りしたくないという強い思いがある場合は、別の集客方法を検討すべきかもしれません。
対応エリアや仕事内容の条件が極端に限定的な人
ハウスクリーニングを行える場所や作業の種類を絞り込みすぎると、サイトから届く依頼の数そのものが少なくなってしまいます。
活動する範囲が狭すぎたり、特定の作業しか受け付けなかったりすると、マッチングの機会を逃してしまいます。
せっかく登録しても集客の仕組みを十分に活かせない恐れがあるため、ある程度の柔軟な受け入れ姿勢が必要です。
ハウスクリーニングマッチングサイトと他の集客手法を比較
ハウスクリーニングのマッチングサイトは、他の集客手法と比べてコストを無駄にするリスクがなく、すぐに仕事獲得につながるのが強みです。
代表的なWEB集客手法とマッチングサイトを比較します。
- オンライン広告との比較
- ホームページとの比較
- SNSとの比較
オンライン広告との比較
Googleの検索結果やSNSの画面に、お金を払って自分の広告を表示させる方法がオンライン広告です。
「ハウスクリーニング地域名」などで調べた人に対して自分の存在をアピールできます。
オンライン広告は検索結果の目立つ場所に自分の情報を出せる仕組みですが、ネットの広告はクリックされるだけで費用がかかるため、赤字になる危険があります。
- 広告はクリックされるだけで費用がかかるため、一件も依頼が来なくても支払いが発生します。
- 効果的な広告を出すには、どの言葉で広告を出すかといった難しい設定の知識がいります。
- 広告は一日数千円といった予算を自分で決めて運用しますが、放っておくといつの間にかお金を使い切ってしまうことがあります。
成約課金型のマッチングサイトなら仕事が取れた分だけ手数料を払う形になるので、開業したばかりで手元の資金を減らしたくない時期でも安心して始められます。
- お客さんとつながって仕事が決まるまで費用が発生しないため安心です。
- 自分の情報を登録して待つだけで、システムがお客さんを運んできてくれます。
- 売上の中から手数料を出す形になるため、赤字になる心配がありません。
ただし、月額固定型や、リード課金型の場合は、オンライン広告同様に依頼が発生していない状況でも支払いが発生するため注意が必要です。
【補足】新規顧客の獲得にかかる費用
一般的に、新しいお客さんを一人見つけるためにかかる費用は、既存のお客さんにリピートしてもらう費用の約5倍と言われています。そのため、開業したばかりの時期は、いかにリスクを抑えて最初のお客さんを見つけるかが経営の鍵となります。
ホームページとの比較
自分のホームページはネット上の看板として信頼を得るのに役立ちますが、お客さんの目に留まるまで半年以上の長い時間がかかるのが一般的です。
ホームページは、自分の事業の内容やこだわりを詳しく紹介する、自分専用のネット上の看板です。
これがあることで「しっかりした業者さんだ」という信頼につながりますが、実際の成果に繋がるまでには時間がかかります。
- ホームページを多くの人に見てもらうには、定期的にブログや情報を更新し続ける必要があります。
- 本格的なホームページを作るには、数十万円といったまとまったお金が必要になることもあります。
- ホームページは自分で内容を直したり、不具合がないか見たりする管理の手間がかかります。
マッチングサイトは、ホームページを一から作って人を集める苦労を、代わりに行ってくれる形になります。
今すぐ売上を立てていきたいという切実な願いに応えられるのが、マッチングサイトの即効性という大きな魅力です。
- サイト自体がすでにお客さんを集めているため、自分は現場の仕事に集中できます。
- 登録無料のところが多く、少ない資金で集客を始められます。
- 使いやすいスマホだけで運用できるサイトが多くあります。
【実践のコツ】自分のサイトを育てる前に
自分のホームページを育てるのは将来の目標としつつ、まずはリスクの低いマッチングサイトで目の前の仕事を集めるのが、個人事業主として賢い進め方です。マッチングサイトで喜んでくれたお客さんの声を集めてからホームページに載せれば、より信頼される看板になります。
SNSとの比較
SNSは日々の様子を伝えることで親しみを持ってもらえますが、ハウスクリーニングを今すぐ頼みたい近所のお客さんへ確実に届けるのは難しい面があります。
インスタグラムやX(旧ツイッター)などを使って、自分の仕事の風景や人柄を発信する方法がSNSです。
無料で始められ、お客さんと身近な関係を築けるのが魅力ですが、営業の道具としては不安定な部分もあります。
- SNSは日本中の人に見てもらえる可能性がありますが、自分の地域のハウスクリーニングを探している人にピンポイントで届けるには、かなりの工夫が必要です。
- SNSを見ている人は「いつか頼みたい」「ただ見ているだけ」という人も多く、今すぐの仕事に繋がりにくい面があります。
見てくれる人を増やすのに時間がかかるSNSと違い、マッチングサイトは最初からハウスクリーニングの依頼を考えているお客さんだけを相手にできます。
現場で忙しく働く職人さんにとって、余計な投稿の手間を省いて効率よく仕事を見つけられるのは大きな利点となります。
- 最初から自分の地域でプロを探している意欲の高い人だけを相手にできます。
- マッチングサイトは過去の実績や星の評価、口コミの内容が一目でわかるため、初めてのお客さんでも安心して依頼を決められます。
マッチングサイト「ミツモア」の特徴
ミツモアは、開業にかかる費用をかけずに地元の依頼を受け取れるため、ハウスクリーニングで独立したばかりの方でも無理なく集客を始められる仕組みです。
- 完全無料で案件が届く
- 最大5社提案だから新規参入者にもチャンスがある
- 自動応募で営業効率が向上する
- 詳細な仕事条件の設定でミスマッチを防げる
- 事業者に配慮したキャンセル処理で安心
それぞれ詳しく解説します。
完全無料で案件が届く
ミツモアは登録料や月額費用が一切かからないため、仕事が決まるまでお金を失う心配をせずにハウスクリーニングの依頼を待つことができます。
クレジットカードの登録も不要で、リスクを背負わずに集客の窓口を作れる安心感があります。
開業したばかりで手元の資金を減らしたくない時期でも、まずは登録しておくだけで地元のハウスクリーニングを必要としているお客さんとつながるきっかけを得られます。
【こんな人におすすめ】固定費を抑えたい人
仕事が取れなければ費用は1円もかかりません。営業の手間をシステムに任せるための手数料は、売上が確定した後に支払う形になるため、赤字になるリスクを避けたい職人さんに適しています。
最大5社提案だから新規参入者にもチャンスがある
一つの依頼に対して提案できる業者を5社までに絞っているため、口コミがまだ少ない人でもお客さんの検討リストに必ず残ることができます。
実績が豊富な大手が市場を独占しにくい仕組みになっており、始めたばかりの人にも平等にチャンスが回ってきます。
提案文で「なぜこの金額なのか」や「自分に頼むメリット」を丁寧に伝えることで、大手やベテランと並んで選ばれる可能性を十分に高められます。
関連記事:【クリーニング事業者の皆様へ】セールスポイントをアピールできる新機能導入
自動応募で営業効率が向上する
依頼者の希望に応じた見積もりを自動で算出し、カスタマイズされたメッセージとともに自動で届ける機能が、ミツモアの「自動応募」です。
自動応募により、現場でハウスクリーニングの作業をしている間も、システムが自分の代わりに営業を続けてくれます。
わざわざ手を止めて電話をかけたり、夜遅くに見積もり書を作成したりする必要はありません。
自分の代わりに24時間365日、営業活動を代行してくれる窓口が手に入ります。
作業に集中している間に成約が決まっているという環境は、一人で切り盛りする職人さんの大きな支えとなります。
詳細な仕事条件設定でミスマッチを防げる
自分の対応できるエリアや作業の種類を細かく設定しておけば、希望に合わない依頼を自動で弾くことができます。
お客さんが事前に詳しい状況や写真を送ってくれるため、現地へ行った後で「話が違う」といったトラブルや金額のズレも起こりにくくなります。
お客さんも金額に納得した状態で申し込んでくるため、確実性の高い商談だけに取り組めます。
事業者に配慮したキャンセル処理で安心
お客さんの都合で急に作業がなくなった場合でも、職人さんが不当に手数料を支払わされることのないよう、公正な基準でキャンセル処理が行われます。
審査はすべてチャット上のやりとりを見ておこなわれ、公正なルールに基づいて、長く使い続けられる環境が守られています。
マッチングサイト「ミツモア」に登録するハウスクリーニング業者の成功事例
有限会社アセンション:登録から4ヶ月で150万円を達成

東京都中野区で創業15周年を迎える有限会社アセンションは、大手ハウスクリーニング会社から独立して20年の経営歴を持つ事業者です。
定期清掃や下請け業務が中心で、繁忙期と閑散期の波が激しく、仕事が途切れる時期の収入が不安定でした。
新規のお客さんを自力で獲得する方法が大きな課題となっていました。
取り組み
以前に案内を受けていたミツモアへの登録を、閑散期の時間を使って実行。
見積もり応募には素早く返信し、お客さんの希望に柔軟に対応することを徹底しました。
いい仕事ができたと実感した時には「ぜひ口コミをお願いします」と声をかけ、web上での選択の手がかりとなる口コミを地道に積み上げていきました。
成果
登録から4ヶ月で約150万円の成約金額を達成し、27件の高評価口コミを獲得。
一度作業したお客さんのご家族から別の依頼が来たり、不動産の大家さんから「別の部屋もやってほしい」と追加で頼まれたりと、仕事が次々につながるケースも出てきました。
定期清掃や下請け業務と組み合わせることで、閑散期の時間を収益化できるようになりました。
関連記事:登録4ヶ月で約150万円達成│20年の経験者が実践した新規集客の転換
クリシア:自動応募機能で月30件超の成約を実現
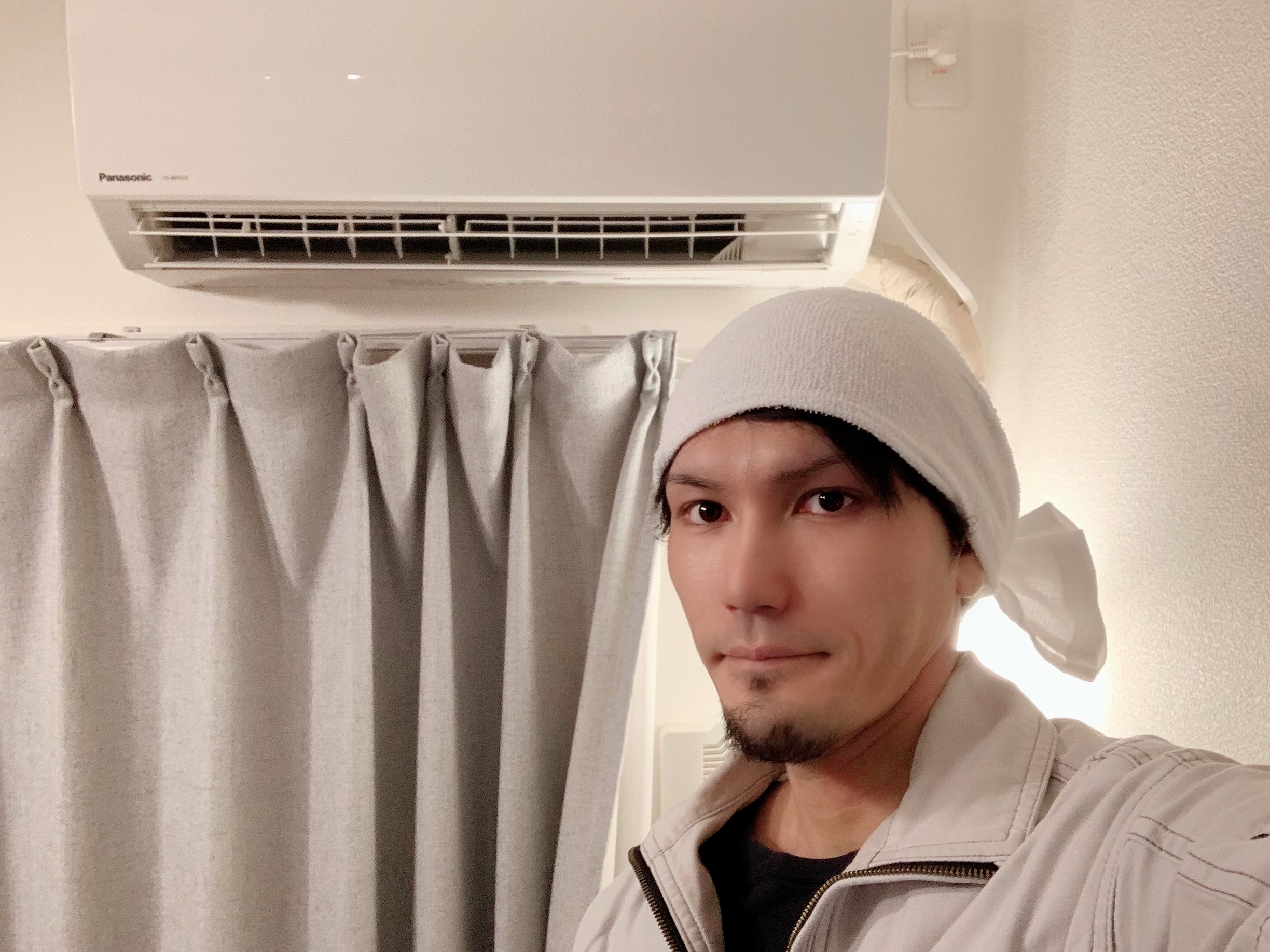
大阪府を拠点とするクリシアは、10年超のキャリアを持ち、年間1000件以上のエアコン・ハウスクリーニング案件を手がける事業者です。
技術力と実績は十分でしたが、現場作業が多忙で営業活動に時間を割けないことが悩みでした。
現場に出ている間は集客ができないというジレンマを抱えていました。
実践した方法
ミツモアの自動応募機能を活用。
現場で作業している最中も、条件に合う依頼に対して自動で見積もりを届けられるため、営業時間を確保する必要がなくなりました。
エアコンの型番や設置場所といった詳細情報はチャットで事前に確認し、行き違いやキャンセルも削減。
移動中や休憩時間のスマホ対応で、お客さんとのやり取りもスムーズに進められました。
成果
5月・6月で月30件超の成約を達成し、1日約1件のペースで案件獲得を実現。
現場作業に集中しながら集客も進む体制ができ、安定的な収入確保につながりました。
関連記事:月30件超の成約達成│年間1000件実績者が実践した「現場作業中も集客できる」仕組み
株式会社FRISCH:自動応募で事務負担を削減し1ヶ月200万円

東京墨田区を拠点とする株式会社FRISCHは、クロス張り替え・床施工・クリーニングを一括提供する事業者です。
月100~120件の空室クリーニング、月100台のエアコン洗浄など、案件の対応体制が整っていましたが、事務専任スタッフが不在で、見積もり確認や返信対応に時間を取られることが課題でした。
実践した方法
w
ミツモアの自動応募機能を使い、見積もりの算出と送信を自動化。
条件に合う依頼に対してシステムが自動で見積もりを作成して送るため、見積もり書を手作業で作る手間が大幅に削減されました。
成果
開始1ヶ月で200万円に迫る成約額を達成。
口コミ評価4.8を獲得し、事務負担を抑えながら現場作業に集中できる体制が整いました。
関連記事:開始1カ月で200万円│月100件超処理する事業者の「事務負担ゼロの集客術」
まとめ
ハウスクリーニングのマッチングサイトは、従来のように自分で営業をかける必要がなく、登録しておけば条件に合う依頼の通知が届きます。
料金の支払い方は主に3つあります。
成約課金型は仕事が決まった時だけ支払うため、開業直後でリスクを抑えたい人に適しています。
月額固定型は毎月決まった金額を払う代わりに、多くの案件をこなせる人ほど一件あたりのコストを抑えられます。ただし仕事が少ない時期でも支払いは発生する点に注意が必要です。
リード課金型は見積もりを送るごとに費用がかかるため、成約率に自信のある人向けです。
集客基盤がない開業直後の人、下請けやフランチャイズから抜け出したい人、閑散期の仕事不足に悩む人には、マッチングサイトが最適な選択肢。
マッチングサイトは「今すぐハウスクリーニングを頼みたい人」と直接つながれる即効性が強みです。
中でも、ミツモアは登録料や月額費用が無料の成約課金型の仕組みです。
自動応募機能により現場作業中も集客ができ、一つの依頼に対して提案できる業者が最大5社までなので、口コミが少ない新規参入者でもお客さんの検討候補に必ず残れます。
成約課金型であれば、仕事が決まるまで費用は発生しません。
まずは登録して、自分の地域でどんな依頼が届くのか確認してみるところから始められます。
ハウスクリーニングを仕事にする女性事例!活躍のコツと実際に獲得できる仕事・単価も紹介
ハウスクリーニングを仕事にする女性事例!活躍のコツと実際に獲得できる仕事・単価も紹介
ハウスクリーニングを仕事にしたいと考えている女性にとって、どのように集客し、どのような案件で活躍できるのかは非常に気になるポイントです。
男性中心のイメージが強い業界ですが、実は「女性ならでは」の視点や安心感が強力な武器になります。
この記事では、実際に現場で活躍しているプロの事例を交えながら、成功のコツと具体的な案件例を詳しく解説します。
この記事の要約
- 女性一人暮らしや子育て世帯をターゲットに「安心感」を打ち出すのが成功の鍵
- 自分に合った集客ルート(業務委託・フランチャイズ・下請け・マッチングサイト)を使い分ける
- ミツモアなら直接契約で、女性の強みを活かした納得の単価で仕事が獲得できる
ハウスクリーニングで女性が仕事を獲得するコツ
- 女性一人暮らしの方をターゲットにする
- 子育て経験・主婦目線を強みとして打ち出す
ハウスクリーニング市場は、現在の利用者7.0%に対して今後の利用を希望する人は29.4%と、約4倍の潜在需要があります。
こうした潜在需要の高まりに加え、男性中心の業界だからこそ、女性プロが持つ安心感という強みを打ち出すことで、多くの依頼を掴むチャンスが眠っている業界でもあります。
女性がハウスクリーニングで仕事を獲得するコツを2つ紹介します。
出典:J-Net21(中小機構)「消費者アンケート調査」
女性一人暮らしの方をターゲットにする
| ポイント | 具体的な方法 |
|---|---|
| プロフィール写真 | 明るい場所で笑顔の写真を撮る |
| 事業者名 | ひらがなを使い柔らかい印象にする |
「女性スタッフに来てほしい」という明確な需要がある層にターゲットを絞ることで、大手業者との価格競争に巻き込まれず、指名で仕事をもらえるようになります。
ハウスクリーニングはプライベートな空間に人を招き入れるため、お客さんは無意識に警戒心を抱いています。
特に男性の職人さんに対して「怖そう」「威圧感がある」と感じるお客さんにとって、女性の存在はそれだけで大きな安心材料になります。
プロフィールでは、作業服を着ていても清潔感があり、親しみやすい笑顔の写真を載せて、女性であることを明確にアピールしましょう。
名前や写真で女性であることを伝えることは、お客さんが抱く「どんな人が来るか分からない」という恐怖心を取り除く最も効果的な方法です。
【補足】第一印象が安心感を生む
写真の印象が「この人なら家に入れても大丈夫か」という第一の判断基準になります。作業中の真剣な表情だけでなく、話しかけやすい雰囲気の写真を1枚用意しましょう。
子育て経験・主婦目線を強みとして打ち出す
| 打ち出す強み | 顧客のメリット |
|---|---|
| エコ洗剤の使用 | 子供やペットがいる家庭の安心 |
| 細部へのこだわり | 普段気づかない場所まで綺麗になる |
日々の暮らしの中で培った「汚れへの気づき」や「家族の健康を気遣う視点」をアピールすることで、付加価値のあるサービスとして評価してもらえます。
子供が床に触れることを前提とした洗剤選びや、家事の動線を考えた整理整頓のアドバイスなど、生活者としての実感を込めた提案はお客さんの心に深く響きます。
【実践のコツ】言葉選びのポイント
「綺麗にします」という言葉に加えて、「お孫さんが遊びに来ても安心なように仕上げますね」といった、生活シーンを想像させる一言を添えるだけで、プロとしての信頼がぐっと高まります。
ハウスクリーニングの仕事の探し方
自分に合った仕事を見つけるには、「業務委託」「フランチャイズ」「下請け」「マッチングサイト」という4つのルートを、自分の目標とする働き方に合わせて使い分けることが重要です。
- 業務委託案件を探す
- フランチャイズに加盟する
- 下請け案件を探す
- マッチングサイトで案件を探す
業務委託案件を探す
業務委託案件を探す方法としては、求人サイトが有効です。
Indeed(インディード)や求人ボックスといったネット上の求人サイトには、ハウスクリーニングの業務委託求人が数多く掲載されています。
特に「女性スタッフ活躍中」と書かれた募集は、女性ならではの配慮を高く評価してもらえる環境が予想されるのでおすすめです。
ただし、過度な期待は禁物。面接でお話をして必ず相性や条件面の確認を行うようにしましょう。
【注意】契約内容の確認
業務委託は働く時間を選びやすい一方、洗剤や道具が自己負担になるケースがあります。契約前に経費をどこまで自分が負担するかを必ず確認してください。
フランチャイズに加盟する
フランチャイズ(FC)に加盟して仕事を探す方法は、大手の看板を利用できるため、未経験からでも早期に収益化を目指しやすいルートです。
加盟することで、技術研修だけでなく、集客ノウハウや専用の洗剤・道具の提供も受けられます。特に大手の知名度は強力な武器になり、自分で一から集客する手間や不安を大幅に減らせます。
しかし、高額な加盟金や月々のロイヤリティが発生する点には注意が必要です。売上から経費を差し引いて、最終的に手元に残る利益がいくらになるかを事前によくシミュレーションしておくことが重要です。
下請け案件を探す
ネット上の協力業者募集サイトから下請けに入る方法は、仕事の数は安定しやすい一方、何重もの下請け構造によって利益を出しにくいのが現状です。
ネットで「ハウスクリーニング 協力業者 募集」と検索すると、下請けを募集している不動産管理会社やリフォーム業者の窓口が見つかり、多くの会社と繋がるきっかけになります。
しかし、ハウスクリーニング業界では元請けから何社も間に入る「多重下請け構造」も見られるため、実際に作業する人に回ってくる金額は少なくなります。
フランチャイズのような加盟金はかかりませんが、利益をしっかり残すのは難しいという側面があります。
マッチングサイトで案件を探す
マッチングサイトに登録してお客さんからの依頼を待つ方法は、間に業者を挟まずにお客さんと直接繋がれるため、利益を最大化しやすいルートです。
マッチングサイトで仕事を取るためには、登録を済ませて、プロフィールを充実させることから始めます。
仕事を取るまでの流れはサイトによって異なりますが、マッチングサイト「ミツモア」であれば、希望する条件にマッチする問い合わせが、登録完了した日からすぐに届きます。
マッチングサイトでは、自分で仕事単価を設定できるため、下請けよりも高い単価で仕事を受けられる機会が多いです。
プロフィール欄に女性ならではのこだわりや掃除のコツを詳しく書くことで、価格の安さだけではなく「この人に頼みたい」という安心感で選んでもらえるようにもなります。
良い口コミが貯まれば、それが安心してもらうための看板となり、過度な売り込みをしなくても依頼が舞い込む状態を作れるのが大きな魅力です。
【実践のコツ】実績の積み上げ
ネット集客は口コミが看板になります。最初の方は実績作りと割り切って、丁寧な作業で良い口コミを集めることに集中すると、その後の受注率が飛躍的に高まります。
ミツモアでハウスクリーニングの仕事を獲得する女性プロ事例
実際にミツモアを利用して、女性ならではの強みを活かしながら多くの依頼を獲得しているプロの方々をご紹介します。
それぞれのプロがどのように自分たちのポジションを確立し、お客さんからの信頼を得ているのか、具体的な集客のヒントを探ってみましょう。
- スズキクリーン
- クリーンα
- ひまわりの種
- あやめクリーン
- HOUSECLEANING BELL’s
スズキクリーン

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | スズキクリーン |
| ミツモア評価 | 408件(4.9点) |
| エリア | 静岡県静岡市葵区 |
選ばれる理由①:女性専門クリーニング店として明確なポジションを取っている
スズキクリーンは、プロフィールの冒頭で「《女性のためのハウスクリーニング専門店》」と明確に打ち出し、ターゲット顧客を女性に絞っています。
「女性スタッフのみ・指定OK」「全スタッフ非喫煙者」という安心材料を前面に出すことで、「男性スタッフに家に入られたくない」「タバコの匂いが気になる」という女性特有の不安を解消。
実際に口コミでも「女性の方で話しやすくとても楽しみながら掃除ができました」と、女性スタッフであることが安心感と満足度に直結していることが分かります。
選ばれる理由②:前職(看護師)の経験を強みに転換している
前職が看護師という経歴を持っています。プロフィールでは「看護師時代に培った丁寧さ・清潔・安全への意識・相手に寄り添う姿勢をそのままクリーニングにも活かしています」と明記し、異業種からの転身でも経験を価値に変えられることを示しています。
選ばれる理由③:年間500台の実績と408件の高評価口コミで信頼を証明している
年間500台以上のエアコンクリーニング実績と、408件の口コミ(平均4.9点)、さらに「90%以上が満点評価」という数字で信頼性を明確に示しています。
法人取引実績(生協・ホームセンター・大手ハウスメーカー)も記載することで、個人だけでなく企業からも信頼されていることをアピールしています。
【代表的な口コミ例】近藤様(★5.0 / 2024年5月18日)
3年ほどエアコンクリーニングを行っていなかったので、口コミも良くお値段もちょうど良くて助かるなと思い、お願いしました!チャットでのメールでも丁寧に連絡をくださり、当日もお電話で到着時刻の連絡を頂き助かりました。
クリーニングの作業も、気温が高い日だったのもあり、大変だったと思いますが、とても丁寧に作業して下さいました!!beforeとafterの写真や動画も見せて頂けて、おぉぉーーー!となりました!
明るくて、丁寧な女性スタッフさんで、楽しく話も出来、お願いして本当に良かったです!!次回もお願いしようと思います!!この度は本当にありがとうございました!!
クリーンα

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | クリーンα |
| ミツモア評価 | 117件(4.7点) |
| 特徴 | 女性チームで訪問し効率的に作業 |
| エリア | 埼玉県北本市 |
選ばれる理由①:チームで訪問する体制がある
クリーンαは、プロフィールの冒頭で「☆女性スタッフメインの当店☆」と明記し、「女性ならではの気配り・丁寧さ・安心・安全をモットー」と打ち出しています。
また特徴的なのは、口コミに「女性2人で来てくださり、手際よく3時間足らずで終わりました」とあるように、女性スタッフが複数人で訪問するケースもあること。
エアコン3台と換気扇を3時間足らずで完了できたのは、女性2人体制で手分けして作業できたから。広範囲のクリーニングや複数台の作業でも、効率的に対応できる体制を整えています。
選ばれる理由②:事前相談の丁寧さ・透明性がある
クリーンαは、事前のやり取りで現場の写真を送って相談できる体制を整えています。
口コミでは「二段ベッドの上にあるエアコンの相談を事前に写真でできた」とあり、作業前に不安を解消できる対応が評価されています。
また、「当日の追加料金も一切なく、とても良心的」と料金の透明性も高く、コミュニケーションの丁寧さも評価されています。
選ばれる理由③:累計500台以上の実績と損害保険加入で信頼性を担保できている
累計500台以上のエアコンクリーニング実績に加え、「損害保険加入済みの為、万が一の際も安心」と明記することで、初めて依頼する人でも安心して任せられる体制を整えています。
また、不用品回収も対応可能で古物商許可も取得しているため、クリーニングと合わせて不用品処分も相談できる点が差別化になっています。
【代表的な口コミ例】佐々木様(★5.0 / 2023年6月1日)
本格的にエアコンを使用する時期が来る前に、と思いクリーニング業者さんを探していました。エアコン3台と、ついでに換気扇の掃除もお願いしたのですが、女性2人で来てくださり、手際よく3時間足らずで終わりました。
子供部屋のエアコンは二段ベッドの上にあるため、移動させたりするのが大変だなあと思っていたのですが、事前のやり取りで現場の写真を見せて相談したところ、移動なしでできるとのことで安心しました。当日の追加料金も一切なく、とても良心的だと思います。
ビフォーアフターを見せてくれたり、フィルターの相談に乗ってくれたり、説明や対応もとても丁寧でした。次は浴室やトイレのクリーニングも、同じ業者さんにお願いしたいと思います。
ひまわりの種

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | ひまわりの種 |
| ミツモア評価 | 55件(4.8点) |
| エリア | 埼玉県加須市 |
選ばれる理由①:女性店長による細かな作業・丁寧さで安心感を獲得している
ひまわりの種は、店長が女性で「女性ならではのハウスクリーニング」を行っています。
実際に口コミでも「個人的には女性の方に来ていただいたのが良かったです」「作業は丁寧ですし」と、女性スタッフであることと丁寧な作業が評価されています。
選ばれる理由②:ガラスコーティングという独自サービスで差別化している
ひまわりの種の最大の特徴は、ハウスクリーニングにガラスコーティングを組み合わせている点です。
トイレやお風呂へのコーティングを提案することで、日常的な掃除の手間や安全への配慮を打ち出しながら、女性ならではの目線で独自サービスを提案できています。
【代表的な口コミ例】田口様(★5.0 / 2020年6月29日)
エアコンの埃っぽいにおいに悩んでいました。今まではなんとかごまかして、家庭用のスプレーで対応していましたが、カビだらけのエアコン内をみて、初めて依頼させていただきました。
作業は丁寧ですし、個人的には女性の方に来ていただいたのが良かったです。また依頼させて頂きたいです。ありがとうございました。
あやめクリーン

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | あやめクリーン |
| ミツモア評価 | 52件(4.92点) |
| 所在地 | 埼玉県久喜市 |
選ばれる理由①:実績を打ち出し実力を証明している
あやめクリーンは、高い技術力と対応力があることを証明していることが強みです。
不用品回収や遺品整理といった力仕事が必要な業務も対応しており、「女性でもハードな仕事ができる」という実績を示すことでイメージを払拭しています。
選ばれる理由②:迅速な対応力で急ぎの依頼にも対応している
レスポンスの早さと柔軟な対応も好評です。
口コミでは「他の業者よりも格段に早く見積もりを出していただき、当日対応していただきました」とあり、急な事情にも対応できるスピード感が評価されています。
【代表的な口コミ例】エーラート様(★5.0 / 2024年12月4日)
中古戸建てを購入し入居したばかりで、元々ついてたエアコンが古くすごーーく汚かったため依頼しました。来週義母がアメリカから来日し家に1ヶ月間泊まるので、それに合わせて急ぎでクリーニングをしたくて急遽見積もりをお願いしました。
急だったのにも関わらず、他の業者よりも格段に早く見積もりを出していただき、クリーニングも当日対応していただきました。女性スタッフということもあり安心して任せることができました。無事エアコンはピカピカ、来週の来客にも間に合いました!
HOUSECLEANING BELL’s

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | HOUSECLEANING BELL’s |
| ミツモア評価 | 7件(4.86点) |
| 特徴 | 大手で研修を受けたプロの対応力 |
| 所在地 | 東京都板橋区 |
選ばれる理由①:大手で研修を受けた技術力をアピールしている
HOUSECLEANING BELL’sは、「大手ハウスクリーニング業で経験を積んだ、プロの女性スタッフが在籍しております」と明記し、体系的な研修を受けたプロであることを強調しています。
選ばれる理由②:衛生面への配慮を徹底している
部屋に上がる際の手の除菌や持参スリッパの使用など、衛生対策の徹底がプロとしての信頼感に繋がっています。
また「汚れが飛び散らない配慮」もされており、狭い1Rでも安心して作業を見守れる環境を作っています。
【代表的な口コミ例】田中加奈子様(★5.0 / 2021年11月15日)
先日、エアコンクリーニングを依頼しました。ハウスクリーニング自体初めてでしたが、女性スタッフの方だったので事前の連絡の時点から安心してやりとり出来ました。
当日は5分前に自宅前に到着してくれて、部屋に上がる際も手を除菌され持参したスリッパを使われていたので衛生的な面でも安心しました。
エアコンは5年ぐらい使っていて初めてのクリーニングだったので、案の定カビが凄かったですが、テキパキと分解して高圧洗浄機でしっかり洗ってもらいました。汚れが飛び散らない配慮や、カーテンレールの上のホコリを拭いておいてくれるなど随所にきめ細やかな心配りを感じられました。
ミツモアで獲得できるハウスクリーニングの仕事と単価
ミツモアでは、単発のエアコン掃除から家全体を丸ごと綺麗にする大規模な依頼まで、幅広い仕事が動いています。
実際に成約した案件の具体例と金額を見ることで、自分が働く際の収益イメージをより具体的に膨らませてみてください。
| 仕事例 | 成約金額 |
|---|---|
| エアコン3台+換気扇クリーニング | 59,500円 |
| お風呂+換気扇+浴室乾燥機クリーニング | 33,000円 |
| ドラム式洗濯機+浴室クリーニング | 24,605円 |
| 水回り4点セット(キッチン・浴室・トイレ・洗面所) | 33,000円 |
| レンジフード+キッチンクリーニング | 30,500円 |
| 水回り2点セット+配管洗浄 | 31,000円 |
| タテ型洗濯機クリーニング(8kg以上) | 13,000円 |
| 2LDK引越し前ハウスクリーニング | 54,000円 |
| ワンルーム・1K:空室クリーニング | 14,000円 |
| 3DK空室クリーニング | 35,000円 |
仕事例①:エアコン3台+換気扇クリーニング
| 対応したプロ | クリーンα |
|---|---|
| 成約金額 | 59,500円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 栃木県 足利市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 壁掛け(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 15,000円 | 3 | 45,000円 |
| レンジフード型換気扇クリーニング | 8,000円 | 1 | 8,000円 |
| エアコン:室外機の洗浄 | 2,500円 | 3 | 7,500円 |
| 出張費(30km以上) | 1,000円 | – | 1,000円 |
| エアコンクリーニング:2台目以降の割引 | -1,000円 | 2 | -2,000円 |
【口コミ】佐々木様(★5.0)
本格的にエアコンを使用する時期が来る前に、と思いクリーニング業者さんを探していました。
エアコン3台と、ついでに換気扇の掃除もお願いしたのですが、女性2人で来てくださり、手際よく3時間足らずで終わりました。
子供部屋のエアコンは二段ベッドの上にあるため、移動させたりするのが大変だなあと思っていたのですが、事前のやり取りで現場の写真を見せて相談したところ、移動なしでできるとのことで安心しました。
当日の追加料金も一切なく、とても良心的だと思います。
ビフォーアフターを見せてくれたり、フィルターの相談に乗ってくれたり、説明や対応もとても丁寧でした。
次は浴室やトイレのクリーニングも、同じ業者さんにお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
仕事例②:お風呂+換気扇+浴室乾燥機クリーニング
| 対応したプロ | スズキクリーン |
|---|---|
| 成約金額 | 33,000円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 静岡県 焼津市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 浴室クリーニング | 15,000円 | 1 | 15,000円 |
| 換気扇クリーニング:レンジフード型 | 13,000円 | 1 | 13,000円 |
| 浴室:浴室乾燥機の分解洗浄 | 5,000円 | 1 | 5,000円 |
【口コミ】村松様(★5.0)
お風呂と換気扇、レンジフードをお願いしました。
自分じゃどうする事もできなくなった風呂場の
レールの石のような汚れもガラスのうろこも
とても丁寧に掃除してくれました!
お風呂もレンジフードもすごいぴかぴかです!!
ありがとうございました!
仕事例③:ドラム式洗濯機+浴室クリーニング
| 対応したプロ | HOUSECLEANING BELL’s |
|---|---|
| 成約金額 | 24,605円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 東京都 清瀬市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ドラム式洗濯機クリーニング | 15,000円 | 1 | 15,000円 |
| 浴室クリーニング | 9,900円 | 1 | 9,900円 |
| 駐車場料金 | 1,000円 | – | 1,000円 |
| 限定割引(5%) | -1,295円 | – | -1,295円 |
【口コミ】福地様(★5.0)
寒い中綺麗にしていただきありがとうございました。とても感じのよい女性の方で、安心してお任せできました。またお願いしたいと思いますので、宜しくお願いします。
仕事例④:水回り4点セット(キッチン・浴室・トイレ・洗面所)
| 対応したプロ | スズキクリーン |
|---|---|
| 成約金額 | 33,000円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| キッチンクリーニング(標準サイズ) | 13,000円 | 1 | 13,000円 |
| 浴室クリーニング | 9,000円 | 1 | 9,000円 |
| トイレクリーニング | 6,000円 | 1 | 6,000円 |
| 洗面所クリーニング | 5,000円 | 1 | 5,000円 |
【口コミ】しばた様(★5.0)
お世話になりました。とても、きれいにしていただき助かりました。料金もリーズナブルで、今回は姉の家の水回りセットで、次は自宅もリピートします。
仕事例⑤:レンジフード+キッチンクリーニング
| 対応したプロ | ひまわりの種 |
|---|---|
| 成約金額 | 30,500円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 群馬県 大泉町 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| レンジフード型換気扇クリーニング | 15,300円 | 1 | 15,300円 |
| キッチンクリーニング | 15,200円 | 1 | 15,200円 |
【口コミ】中瀬様(★5.0)
女性の方ひとりで作業していただきました。長時間かけて丁寧に仕上げていただいてありがとうございました。またお願いしたいと思います。
仕事例⑥:水回り2点セット+配管洗浄
| 対応したプロ | スズキクリーン |
|---|---|
| 成約金額 | 31,000円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 静岡県 磐田市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 2点セット | 17,000円 | 1 | 17,000円 |
| 浴室:風呂釜 (追い炊き配管) 洗浄 | 9,000円 | 1 | 9,000円 |
| 浴室:浴室乾燥機の分解洗浄 | 5,000円 | 1 | 5,000円 |
【口コミ】杉本様(★5.0)
キッチンの換気扇とお風呂場の掃除、配水管と浴室乾燥機の洗浄をお願いしました。
塚本さんという女性の方が来てくださいました。感じのよい方で話しやすく清潔感もあり安心してお掃除をお任せすることができました。
綺麗にしてくださりありがとうございました。
仕事例⑦:タテ型洗濯機クリーニング(8kg以上)
| 対応したプロ | HOUSECLEANING BELL’s |
|---|---|
| 成約金額 | 13,000円 |
| 評価 | ★4.0 |
| 地域 | 東京都 板橋区 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| タテ型洗濯機クリーニング | 11,000円 | 1 | 11,000円 |
| 洗濯容量8kg以上 | 2,000円 | 1 | 2,000円 |
【口コミ】柳沼様(★4.0)
先日はありがとうございました。とても丁寧にやっていただき満足しました。
仕事例⑧:2LDK引越し前ハウスクリーニング
| 対応したプロ | スズキクリーン |
|---|---|
| 成約金額 | 54,000円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 静岡県 掛川市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 2LDK:居住中 | 32,000円 | 1 | 32,000円 |
| エアコンクリーニング:壁掛け | 6,000円 | 3 | 18,000円 |
| 浴室:エプロン内高圧洗浄 | 4,000円 | 1 | 4,000円 |
| 浴室:鏡のコーティング | 2,000円 | 1 | 2,000円 |
| エアコンクリーニング:2台目以降の割引 | -1,000円 | 2 | -2,000円 |
【口コミ】テニスじじい様(★5.0)
引越しに伴いエアコン、風呂、キッチン、トイレ、フローリングの清掃をお願いしました。
普段そこまでエアコン使用していないものもカビが生えており身震いがしました。
これからも定期的なクリーニングをお願いしようと思いました。
清掃中も都度, 清掃具合を確認していただき隅々まで綺麗にしていただきました。
丁寧で細かい清掃に感動しつつ安心して任せられました。
これで心置きなく引越しすることができます。
遠くから本当にありがとうございました。
引越し先でも依頼します(笑)
仕事例⑨:ワンルーム・1K:空室クリーニング
| 対応したプロ | スズキクリーン |
|---|---|
| 成約金額 | 14,000円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K:空室 | 14,000円 | 1 | 14,000円 |
【口コミ】わか様(★5.0)
感激しました!たった3時間であそこまでキレイにしていただけるなんて(>人<;)事前の打ち合わせもスムーズで50平米くらいある広さでも5分程度で作業に取りかかる迅速さに脱帽です!またの機会があれば是非よろしくお願いいたします!
本日はありがとうございました。
仕事例⑩:3DK空室クリーニング
| 対応したプロ | スズキクリーン |
|---|---|
| 成約金額 | 35,000円 |
| 評価 | ★5.0 |
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
料金内訳
| サービス内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 3DK:空室 | 35,000円 | 1 | 35,000円 |
【口コミ】アルコ様(★5.0)
チャットのやり取りに丁寧に対応してくださり、とても気持ちが良かったです。
時間をかけて作業していただいたようで、非常に嬉しいです。またぜひ仕事をお願いしようと思います。
ハウスクリーニングで仕事を探す女性のよくある質問
ここまで見てきた女性ならではの強みを仕事に繋げるために、現場で働く女性が抱きやすい疑問と解決策を整理しました。
女性の強みを生かすコツは何ですか
お客さんに「女性だからこその安心感」を具体的に伝えることが、仕事を得るための大きなコツです。
ハウスクリーニングはプライベートな空間に足を踏み入れる仕事なので、お客さんは少なからず警戒心を抱いています。
特に一人暮らしの女性や高齢者の方は、同性が来てくれるだけで不安が和らぎます。
プロフィールで「女性スタッフが伺います」と明記したり、主婦目線の整理整頓アドバイスができることを具体的に伝えたりすることで、安心してもらうための看板が作れます。
【補足】選ばれるための付加価値
掃除の技術はプロとして当然求められますが、女性ならではの「物腰の柔らかさ」や「細かな気配り」が、最終的な満足度やリピート率を左右する大きな要因となります。
ハウスクリーニングにはどんな仕事がありますか
エアコン掃除や水回りのセット清掃といった一般的な内容に加え、整理整頓がセットになった依頼もあります。
一人暮らしの女性や共働きの忙しい家庭、話し相手を求める高齢者の方など、女性スタッフを必要としているお客さんは数多くいます。
掃除だけでなく、産前産後のサポートや整理収納のアドバイスといった、暮らしに寄り添った仕事が選べるのも女性プロの特徴です。自分の得意な家事経験をそのままサービスとして提供できます。
どうやって仕事を探せばいいですか
ミツモアのようなマッチングサイトは、自分で仕事単価を設定でき、利益が出しやすいためおすすめです。
自分で価格を決めて直接契約を結ぶことが、納得できる収入を得るための確実な道筋です。
マッチングサイトなら営業に走り回る手間を省きつつ、自分の強みをプロフィールで自由にアピールできます。最初は実績(口コミ)を集めることに集中し、信頼の看板を育てていく方法が効率的です。
ミツモアならハウスクリーニングで女性の強みを生かせる
ミツモアは女性スタッフを希望するお客さんと直接繋がれる仕組みがあるため、自分の強みを最大限に活かして納得のいく単価で仕事を受けられます。
何重もの下請け構造では利益が手元に残りませんが、ミツモアならお客さんと直接契約を結ぶことが可能です。
営業の時間を減らしつつ、女性ならではの「安心感」や「きめ細かさ」を求めているお客さんに絞ってアピールできます。自分のペースで働きながら、リピーターという資産を増やしていく選択肢として検討できます。
女性の強みをミツモアなら生かせる理由
ミツモアのプロフィール機能や口コミ機能を活用することで、言葉にしにくい「安心感」や「丁寧な対応」を具体的な信頼の看板としてお客さんに伝えられます。
プロフィールに「女性スタッフが伺います」と明記しておけば、女性の一人暮らしや高齢者世帯など、女性プロを必要とする層に直接情報を届けられます。
また、実際に作業したお客さんからの「丁寧だった」「話しやすかった」という口コミが積み重なることで、過度な売り込みをしなくても選ばれるようになります。
ハウスクリーニングと清掃業の国家資格・民間資格一覧!役立つおすすめの資格を状況別に紹介!
ハウスクリーニングと清掃業の国家資格・民間資格一覧!役立つおすすめの資格を状況別に紹介!
「資格がないと仕事が取れないのではないか」「どの資格が本当に役立つのか分からない…」
単に「有名な資格を片っ端から取る」だけでは稼げるようになりません。市場のニーズに合わせて資格を選ぶことで、プロとしての信頼と収入を手に入れることができます。
国家・民間資格の一覧、状況別のおすすめ資格、資格取得のステップまで詳しく解説します。
この記事の要約
- ハウスクリーニングは資格なしでも開業可能ですが、ビル清掃や病院清掃では清掃作業監督者などの資格が法律上必須。狙う市場に合わせて資格を使い分けることがポイント
- 未経験者は「実務経験を積む→1つ目の資格取得→専門的な資格をさらに取得」の3ステップで進めるのが効率的
- ミツモアなどのマッチングサイトで現場経験と口コミを積み上げながら資格取得を並行することが稼ぐための確実な道筋
ハウスクリーニングと清掃業で資格の持つ意味が違う理由
ハウスクリーニングでは資格はお客さんに安心してもらうためのものですが、ビルなどの清掃業では法律を守って仕事を続けるための前提条件になります。
- ハウスクリーニングは資格が信頼の証明になる
- 清掃業は資格が登録要件や法令遵守に直結する
ハウスクリーニングは資格が信頼の証明になる
個人宅を相手にする場合、資格は「この人なら大丈夫だ」とお客さんに信じてもらうための強力な看板になります。
ハウスクリーニングの商売を始める際、絶対に持っていなければならない資格はありません。税務署に書類を出すだけで誰でもプロを名乗れますが、商売を始めるハードルが低いためにトラブルが多いのも現状です。
洗剤の知識がないために壁の色を変えてしまったり、分解に慣れていないせいでエアコンを壊してしまったりする業者が後を絶ちません。
こうしたトラブルが多いからこそ、お客さんは「安さ」よりも「安心」を求めています。資格を持っていることは「プロとしての自覚がある」という証拠になり、お客さんに安心してもらえる材料になります。
出典:J-Net21(中小機構)「消費者アンケート調査」
清掃業は資格が登録要件や法令遵守に直結する
ビルメンテナンスを始めとする清掃業の世界では、資格がないとそもそも会社として登録できず、入札などの土俵にも上がれません。
| 資格の名前 | 法律上の役割 |
|---|---|
| 清掃作業監督者 | 清掃業の登録に必ず必要 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 面積の広いビルの管理に必須 |
| 病院清掃受託責任者 | 病院清掃の認定を受けるための条件 |
大きな建物の管理を行うには、法律によって有資格者を置くことが決まっています。清掃会社が都道府県に登録を受ける際も、特定の国家資格を持つ人を専任で置かなければなりません。
資格を持つ人がいないと、会社としてのライセンスが維持できない仕組みになっています。
また、病院や貯水槽の清掃などはリスクが高いため、頼む側が「有資格者を現場に置くこと」を契約の条件にすることが多いです。清掃業では、資格は個人のためだけでなく「会社が仕事を請けるための必須アイテム」としての性質が強くなります。
そのため、会社が費用を出してでも職人さんに資格を取らせる傾向があります。
【補足】登録取り消しのリスク
資格を持っている人が辞めてしまい、代わりの人が見つからない場合、清掃業としての登録が取り消される恐れがあります。仕事ができなくなる大きな問題になるため、有資格者を確保しておくことは経営上の守りとしても欠かせません。
資格がなくてもできる仕事と資格がないと難しい仕事【参考】
自分がどの現場を狙うかによって、資格が今すぐ必要か、後回しでいいのかが決まります。
資格がなくてもすぐに始められる仕事
- 在宅のキッチンや浴室のクリーニング
- 家庭用エアコンのクリーニング
- アパート退去後の空室清掃
- 家事代行としての定期的なクリーニング
資格や研修が実質的に欠かせない仕事(主に法人向け)
- 病院の清掃(感染対策の知識が必須)
- マンションなどの貯水槽清掃
- 役所や大企業のビル清掃
- 排水管の高圧洗浄
家の中の掃除やエアコン洗浄、空室清掃などは、道具と技術があれば今日からでも始められます。特に空室清掃などは「安くて早い」ことが重視されるため、資格よりも現場を回す力が求められます。
一方で、病院の清掃は厳しいルールがあるため、資格がないと契約を結ぶことすら難しいのが現状です。また貯水槽の清掃などは、法律で決まった研修を受けていない人が作業をすると違反になる場合があります。
このように、狙う仕事によっては資格がなければスタートラインに立てないこともあります。
【こんな人におすすめ】市場選びの判断基準
まずは自分の力で稼ぎたい人: 資格は後からでOK。マッチングサイトなどで実績を積むのが先決です。
大きな会社や病院から仕事をもらいたい人: 資格は必須。最初から国家資格を狙って準備を始めましょう。
ハウスクリーニング・清掃業の国家資格一覧
国家資格は信頼性が高く、事業の看板として強力です。主要な国家資格を詳しく解説します。
ハウスクリーニング技能士
ハウスクリーニング技能士は、住宅の清掃に関する唯一の国家資格であり、個人のお客さんに「プロの技術」を証明する最高の看板になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益社団法人全国ハウスクリーニング協会 |
| 費用 | 46,800円(学科11,400円+実技35,400円) |
| 取り方 | 学科と実技の試験をクリア(7つの課題・時間制限あり)、年1回の試験(9月学科・10〜11月実技) |
| 受験資格 | 1級(実務経験3年以上)、2級(実務経験2年以上)、3級(制限なし) |
実技試験ではレンジフードの洗浄を28分以内に終わらせる必要があり、制限時間を1秒でも過ぎると即失格になる厳しい基準です。
国家資格として名刺やサイトに記載できるため、主婦層や高齢者のお客さんへの安心感が格段に高まります。
出典:公益社団法人全国ハウスクリーニング協会「受検案内」
ビルクリーニング技能士
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 中央職業能力開発協会 |
| 費用 | 受験級や実施都道府県により異なる(標準的には学科・実技で3〜4万円程度) |
| 取り方 | 学科と実技の試験をクリア(ポリッシャー操作、カーペット洗浄、ガラス清掃など) |
| 受験資格 | 実務経験必要(級により異なる) |
ビルクリーニング技能士は、大型施設やビルの清掃を請け負う際に重視される資格です。
1級を取れば、後で紹介する「清掃作業監督者」の講習を実務経験なしで受けられます。公共施設の清掃の入札では、ビルクリーニング技能士がいることで技術点として加算されることも多く、法人案件を狙う業者には欠かせません。
出典:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング技能士」
建築物環境衛生管理技術者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター |
| 費用 | 17,900円 |
| 取り方 | 国家試験(年1回)、合格率は例年20%前後 |
| 受験資格 | 特定建築物における2年以上の実務経験(清掃、空調、給排水など) |
建築物環境衛生管理技術者は「ビル管理士」とも呼ばれ、面積が3,000平方メートルを超える大きな建物の管理に必要となる国家資格です。
大規模なビルでは建築物環境衛生管理技術者を責任者として置くことが法律で義務付けられており、企業によっては月額1万円から3万円程度の資格手当が支給される場合があります。
清掃だけでなく、空気や水の管理、ネズミや害虫の防除など、建物全体の衛生を守る幅広い知識が求められます。
出典:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター「建築物環境衛生管理技術者」
清掃作業監督者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター |
| 費用 | 新規講習42,000円(テキスト代含む)、再講習25,000円 |
| 取り方 | 2日間(計14.5時間)の講習を受けて修了する |
| 受講資格 | ビルクリーニング技能士1級または建築物環境衛生管理技術者の資格保有者 |
清掃作業監督者は、清掃業として都道府県の登録を受けるために必ず置かなければならない、現場を束ねるリーダーのための資格です。
清掃作業監督者の講習を受けるには、ビルクリーニング技能士1級または建築物環境衛生管理技術者のいずれかを持っている必要があります。新規講習の費用は42,000円で、テキスト代も含まれています。
建築物清掃業の登録要件として置くことが義務付けられており、会社として大きな建物の仕事を請け負うための免許のような役割を果たします。
出典:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター「清掃作業監督者講習会(新規)」
2025年12月時点の情報を基に作成しています。資格の費用・受講要件・試験内容は変更される場合がありますので、受験・受講前に必ず各認定機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
ハウスクリーニング・清掃業の民間資格一覧
- ハウスクリーニング士
- 清掃マイスター
- エアコンクリーニング士
- 整理収納アドバイザー
- クリンネスト
- ハウスクリーニングアドバイザー
- 整理収納清掃(3S)コーディネーター
- 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)
- 病院清掃受託責任者
- 貯水槽清掃作業監督者
- 排水管清掃作業監督者
民間資格は、特定の技術や知識に特化したものが多く、短期間で取れるものも豊富です。
国家資格に比べて受験資格のハードルが低く、専門分野でのスキルアップやサービスの差別化に役立ちます。主要な民間資格をご紹介します。
ハウスクリーニング士
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | NPO法人日本ハウスクリーニング協会 |
| 費用 | 49,500円(税込)(受講料44,000円+入学金5,500円) |
| 取り方 | 東京都知事認定の通信訓練コース(1年)を修了し、修了試験に合格する |
| 受講資格 | 2年以上の実務経験と事業主の推薦が必要 |
ハウスクリーニング士は、NPO法人日本ハウスクリーニング協会が認定する資格で、実務経験者が商売を始めるための基礎固めに適しています。
資格を取るには2年以上のハウスクリーニング実務経験と事業主の推薦が必要ですが、東京都知事認定の職業訓練として体系的に清掃技術を学べます。
日本ハウスクリーニング協会の通信訓練コースを修了すれば、国家資格であるハウスクリーニング技能士の学科試験が免除される場合もあります。現場に出る前の自信作りや、正しい知識の習得に有効な資格です。
【ポイント】学科試験免除のメリット
通信訓練コースを修了すると、国家資格であるハウスクリーニング技能士試験の学科が免除されます。実技試験に専念できるため、国家資格取得のハードルを下げる効果があります。
出典:公益社団法人全国ハウスクリーニング協会「2025年度ハウスクリーニング通信訓練コース受講者募集案内」
清掃マイスター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 一般社団法人日本清掃収納協会 |
| 費用 | 2級:19,800円(税込)(受講料・テキスト代・認定料込)、1級:42,900円(税込) |
| 取り方 | 2級は1日(3時間程度)の認定講座を受講、1級は2級取得後に5時間講習を受講(実習含む) |
| 受験資格 | なし(誰でも2級講座を受講可能)※1級受講には2級取得が必要 |
清掃マイスターは、掃除の基本から効率的な進め方までを1日で学べるため、初心者が最初の一歩として取るのに向いています。
日本清掃収納協会が実施する講座で、片付けと掃除を組み合わせた手法を学べる点が特徴です。
受講料が手頃で1日で取れるため、従業員への基礎教育に活用できます。短期間で名刺に書ける肩書きが手に入ります。
出典:日本清掃収納協会
エアコンクリーニング士
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 一般社団法人日本エアコンクリーニング協会(JACA) |
| 費用 | 受験ルートにより異なる |
| 取り方 | 協会認定スクールで実技講習(エアコン分解・洗浄・組立の研修)を受講し、協会の検定試験(筆記・実技)に合格する |
| 受験資格 | なし(未経験者でも受講・受験可能) |
エアコンクリーニング士は、高い専門技術が必要なエアコン洗浄に特化しており、夏場の繁忙期にしっかり稼ぐための強みになります。
日本エアコンクリーニング協会が認定する資格で、最新のお掃除機能付き機種などの分解や組み立てを学べます。
エアコンの構造は複雑で、知識がないと故障させてしまう恐れがあります。複雑な構造のエアコンでも故障リスクを抑えてクリーニングできる技術が身につき、他社が敬遠するような機種の仕事も自信を持って受注できるようになります。
資格取得には大きく分けて協会の会員として活動する方法と専門スクールを受講する方法の2パターンがあります。
1. 協会会員ルート
日本エアコンクリーニング協会の会員として1年間(366日以上)活動し、知識と技術を磨いた後に検定試験を受けるルートです。
入会金(5,000円) + 会費(8,000円×12ヶ月) + 受検料(24,000円) = 合計 125,000円
2. スクール受講ルート(短期集中型)
JACAエアコンクリーニングスクールにて、実技を中心に短期間で習得するコースです。
- 独立開業総合コース(27万円):座学からお掃除機能付き、天カセまで幅広く学習
- お掃除機能付きコース(24万円):主要メーカー7社の複雑な分解・組立に特化
出典:日本エアコンクリーニング協会「エアコンクリーニング専門スクール・JACAエアコンクリーニングスクール」
整理収納アドバイザー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | NPO法人ハウスキーピング協会 |
| 費用 | 2級:23,600~24,700円程度(税込、テキスト代・認定料込み)、1級:総額約96,800円(準1級講座約41,800円+1次試験22,000円+2次試験23,100円等) |
| 取り方 | 2級は1日(5時間)講習、1級は2級取得後に準1級講座受講→1次試験(筆記)合格→2次試験(実技・面接)合格で取得 |
| 受験資格 | 1級受験には2級取得が必要 |
整理収納アドバイザーは、片付けのプロであることを示せる資格で、掃除とセットでお客さんに提案することで仕事の単価を上げられます。
プロとして活動できる1級を取れば、掃除の前にまず部屋を片付けてほしいというお客さんの悩みに応えられます。
整理収納の知識があれば、掃除しやすい環境作りを提案でき、リピート率の向上も期待できます。2級は23,600円から取得可能です。協会によれば「2級取得者は21万人を超える」(2025年時点)人気資格で、ハウスクリーニング業との相乗効果も高いとされています。
【ポイント】片付けとのセット提案
掃除だけでなく片付けも引き受けることで、清掃作業とは別の作業単価を設定できます。一人のお客さんからいただく合計金額を上げやすく、競合他社との差別化にも繋がります。
出典:ハウスキーピング協会「整理収納アドバイザー」
クリンネスト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | NPO法人ハウスキーピング協会 |
| 費用 | 2級:25,300円(税込、教材費込み)、1級:33,000円(通信講座・道具なし)~44,000円(道具セット付き)(税込) |
| 取り方 | 2級は1日の認定講座(オンラインまたは対面、標準6時間)を受講、1級は通信講座(動画学習+課題提出)に合格 |
| 受験資格 | 1級受験には2級取得が必要 |
クリンネストは、プロの掃除術を家庭向けに分かりやすく教えるスキルが身につき、家事代行や定期清掃の契約を取りやすくします。
効率的な掃除の進め方を学べるため、定期的な訪問掃除の品質が安定します。
プロの視点を論理的に伝える力が養われ、お客さんとの信頼関係を深める助けになります。主婦層や家事代行スタッフに人気があり、短期間で取れる点も魅力です。1級講座では最短10日程度で資格取得も可能とされています。
【ポイント】スタッフ研修にも最適
クリンネスト資格で学ぶ内容は、日常清掃のムリ・ムダを省く工夫や時短テクニックが中心です。家事代行サービスのスタッフ研修教材として導入する企業もあります。掃除が苦手な新人でも体系立てて学べるので、サービス品質の均一化と底上げに寄与します。
出典:ハウスキーピング協会「クリンネスト資格のながれ」
ハウスクリーニングアドバイザー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 日本生活環境支援協会 |
| 費用 | 受験料:10,000円(税込)、通信講座(任意):59,800円(税込) |
| 取り方 | 在宅受験(70%以上の正答で合格)、実技試験なし |
| 受験資格 | なし |
ハウスクリーニングアドバイザーは、洗剤の成分や道具の知識を深められる資格で、在宅での受験ができるため忙しい方でも取りやすいです。
試験は筆記(マークシート)のみで、70%以上の評価で合格となります。
実技試験がないため技術の証明としてはやや限定的ですが、清掃の専門知識があることの裏付けとなり、お客さんへの説明に説得力が増します。名刺に記載することで、知識豊富なプロという印象を強められます。講師業やライター活動など、現場以外の仕事に広げたい人にも適しています。
【ポイント】資格と通信講座のセット
試験だけなら1万円で取得可能ですが、JLESA指定の通信教育を利用すると学習と資格取得がセットになっています。例えば諒設計アーキテクトラーニング社の「W資格講座」では、本資格と「クリーニングインストラクター」の2資格を1ヶ月程度で同時取得でき、課題提出で試験が免除されるコースも用意されています。忙しい人でも短期間で資格を得られるよう工夫されたプログラムです。
出典:日本生活環境支援協会「ハウスクリーニングアドバイザー」
整理収納清掃(3S)コーディネーター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 一般社団法人日本整理収納協会 |
| 費用 | 3級:17,600円、2級:29,700円、1級:60,500円(各税込、教材・認定料込み)※3級~1級まで合計107,800円(一括申込で約102,410円) |
| 取り方 | 3級は3時間の講習受講、2級は4時間の講習受講、1級は6.5時間(2日間程度)の講習+実習受講。全て講習修了により認定(試験なし) |
| 受験資格 | 上位級受講には下位級の取得が必要(3級→2級→1級の順にステップアップ) |
整理収納清掃コーディネーターは、家の整理から掃除まで一貫して引き受ける能力の裏付けとなり、大規模な現場の管理に役立ちます。
物を整理する力と掃除する力の両方が身につくため、高齢者世帯や引越前後の丸ごと清掃で喜ばれます。
幅広い悩みに応えられるようになり、一軒丸ごとのような大きな仕事に繋がりやすくなります。現場での段取りもスムーズになります。
【ポイント】売上アップに効果的
3Sコーディネーター資格者は「片付けも掃除もできる」ため、例えば遺品整理で荷物を分類・整理した後に住居を清掃したり、オフィスの引越時に不要品処分から清掃まで請け負ったりと、ワンストップサービスが提供できるため、売上アップにも効果的です。
出典:日本整理収納協会「整理収納清掃(3S)コーディネータ講座」
建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 |
| 費用 | 協会員:約60,000円、非会員:約100,000円(テキスト代含む、税込) |
| 取り方 | 全国ビルメン協会主催の講習(オンライン講義約5時間+集合講習1.5日+修了考査)を受講し、修了考査および課題提出に合格する |
| 受講資格 | 次のいずれかの資格保持者に限る:ビルクリーニング技能士1級または単一等級/清掃作業監督者/建築物環境衛生管理技術者/統括管理者 |
建築物清掃管理評価資格者は、ビルの掃除が正しく行われているかをチェックするプロ向けの資格で、法人営業の信頼性を高めます。
インスペクターとも呼ばれ、清掃現場の品質を客観的に評価する役割を担います。
受講には清掃業界の上位資格(技能士1級・監督者など)の保有が条件となり、清掃現場の実務経験とマネジメント知識を持つプロフェッショナル向けの資格です。個人事業主というよりは、会社として法人向けの仕事を本格的に広げる段階で必要になる資格です。スタッフの管理や品質の点検を行う際に、専門家としての視点が活かせます。
出典:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)新規講習」
病院清掃受託責任者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター |
| 費用 | 新規講習:非会員41,800円/協会員28,600円(税込、オンライン申請時)※郵送申請の場合:非会員45,100円・協会員31,900円、再講習:非会員37,950円/協会員26,400円 |
| 取り方 | 3日間の講習(eラーニング学科+集合講習)と修了試験の全課程修了 |
| 受講資格 | 医療機関を含む清掃業務の実務経験3年以上(うち病院清掃経験6か月以上) |
病院清掃受託責任者は、医療現場特有の厳しいルールを知っている裏付けになり、病院清掃を請け負うための必須条件となります。
医療関連サービスマークの認定を受けるために必要な資格で、院内感染を防ぐための高度な知識を学びます。
一度契約すれば安定した収入になる病院案件を狙うなら、必ず取るべき資格です。4年に1度の再講習が義務付けられています。
出典:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「病院清掃受託責任者(新規講習)」
貯水槽清掃作業監督者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター |
| 費用 | 新規講習:62,000円(非課税、教材費込)、再講習:39,000円(非課税) |
| 取り方 | 4日間(計29.5時間)の講習を受けて修了考査に合格 |
| 受講資格 | 高校卒業後2年以上または5年以上の貯水槽清掃実務経験など |
貯水槽清掃作業監督者は、マンションの飲料水タンクを掃除する人が受けるべき法定講習で、受けていない人は作業ができません。
飲み水の安全を守るための講習で、作業員は受講することが法令で義務付けられています。
未受講者が作業を行うと法令違反となり、行政処分の対象になる恐れがあります。高単価な設備系の仕事に入るための前提条件になります。
【ポイント】名称の補足
正式には「貯水槽清掃作業監督者講習会」と呼ばれます。「監督者」とありますが、一人現場の小規模事業者でも資格を持っていれば自ら監督者兼作業者として登録可能です(例えばビル管理技術者免状を持っている場合も監督者登録が可能)。
出典:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター「貯水槽清掃作業監督者講習会(新規)」
排水管清掃作業監督者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関 | 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター |
| 費用 | 新規講習:49,500円~53,000円程度(4日間、主催団体により異なる)、再講習:39,000円 |
| 取り方 | 指定の講習(4日間・計30時間程度)を受けて修了考査に合格 |
| 受講資格 | なし(排水管清掃業の登録要件として「排水管清掃作業監督者」有資格者の配置が必要) |
排水管清掃作業監督者の講習を受ければ、高圧洗浄機を使った掃除の知識が身につき、水漏れトラブルを防ぐ技術があることを示せます。
排水管の詰まりや臭いを解決する仕事は需要が高く、定期的な清掃メニューとして有効です。
専門的な機材を扱うため、講習で得た知識が現場での事故防止に役立ちます。マンション管理組合との取引では、資格の有無が契約条件になる場合もあります。
【ポイント】メンテナンスの需要
排水管は放置すると油脂や石鹸カスで詰まり、悪臭や逆流事故の原因になります。マンションでは1~2年毎の排水管洗浄が義務付けられているケースもあります。資格を持ち高圧洗浄の技術を習得しておけば、定期契約による安定した収入を見込める分野です。また資格講習で学ぶ安全対策知識により、機械作業時の水漏れ・破損事故を未然に防ぐことができ、信頼性の高いサービス提供に繋がります。
2025年12月時点の情報を基に作成しています。資格の費用・受講要件・試験内容は変更される場合がありますので、受験・受講前に必ず各認定機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
ハウスクリーニングで取るべき資格【状況別】
資格は闇雲に取ればよいものではなく、今の仕事の状況や目指したい方向に合わせて選ぶことで、効率よく売り上げを伸ばせます。
独立・開業の看板になる資格一覧
開業したばかりで実績がまだない時期は、お客さんに安心してもらうための「看板」となる資格を持つことが重要です。
| 資格の名前 | 理由や効果 |
|---|---|
| ハウスクリーニング技能士 | 唯一の国家資格で、お客さんの信頼が格段に上がります |
| ハウスクリーニング士 | 認知度が高く、損害保険の加入などの特典もあります |
| 清掃マイスター | 短期間で取れて、名刺に肩書きを載せられます |
実績や口コミがまだない段階では、資格はお客さんが選ぶ時の大事な判断基準になります。
特に「厚生労働省認定」と言えるハウスクリーニング技能士は、主婦の方や高齢のお客さんからの信頼が非常に厚くなります。資格がないまま商売を始めると、集客の面で不利な戦いを強いられることもあるため、まずは民間資格でも良いので一つは肩書きを用意するのが定石です。
関連記事:自動集客方式の導入で月間成約件数が10倍に!安心料金制で現場も経理もお金の管理が楽に!
単価アップ・差別化につながる資格一覧
決まった掃除メニューだけでなく、専門技術や片付けをセットで提案できる資格があれば、仕事の単価を上げられます。
| 資格の名前 | 狙える効果や市場 |
|---|---|
| エアコンクリーニング士 | 高単価なお掃除機能付き機種の受注に繋がります |
| 整理収納アドバイザー | 片付け代行のセット提案で客単価を上げられます |
| クリンネスト | 家事代行に近い定期清掃の契約を取りやすくなります |
エアコンクリーニングは、お掃除機能付きの機種なら1台1.5万円から2万円ほどを狙える高単価なメニューです。難しい機種の分解技術があれば、他社が断る案件も独占して受けられるようになります。
また整理収納の資格があれば、掃除の前に部屋を片付けるサービスを提案できるようになり、清掃とは別の時間単価でお客さんからいただく合計金額を底上げできます。
関連記事:地域密着型を目指すハウスクリーニング店が「自動集客方式」を活用。毎月約30件成約の快進撃
法人案件・特殊清掃向けの資格一覧
会社との契約やマンションの設備を掃除する現場では、特定の資格を持っていることが仕事を受けるための条件になります。
| 資格の名前 | 必要となる場面 |
|---|---|
| ビルクリーニング技能士 | 清掃会社の下請けや現場責任者になる時に必要です |
| 病院清掃受託責任者 | クリニックや病院の定期清掃を受ける時に必須です |
| 貯水槽清掃作業従事者 | 管理組合や不動産会社から仕事を受ける時に必要です |
法人のお客さんを相手にする場合は、資格は「持っていて当たり前」のパスポートのような存在です。
特に病院清掃は院内感染を防ぐなどの専門知識が求められるため、資格がないと契約を結べないことがほとんどです。マンションの貯水槽や排水管の掃除は単価が高く、一度契約すれば定期的な収入源になります。経営を安定させたい場合には、資格取得が有力な選択肢となります。
【実践のコツ】法人取引とリスク管理
設備系の掃除や病院の清掃は、事故や感染のリスクが伴います。有資格者が作業を指揮することで、頼む側であるビルオーナーや管理会社も安心してお任せできる環境が整います。
ハウスクリーニング未経験者の資格取得ステップ
資格は「取ってから始める」のではなく、現場で経験を積みながら必要に応じて手に入れていくのが効率的です。
- STEP1:実務経験を積む
- STEP2:資格を1つ取る
- STEP3:伸ばしたい分野に合わせて新しい資格を取る
STEP1:実務経験を積む
最初は資格にこだわらず、まずは現場に出て「汚れを落とす経験」を積むことが何よりも大切です。
国家資格であるハウスクリーニング技能士などの受験には、数年の実務経験が必要となります。座学で洗剤の仕組みを学ぶより、実際の現場で「どの汚れにどの洗剤が効いたか」を肌で感じる方が、職人としての成長は格段に早まります。
最初は利益を気にせず、マッチングサイトなどで簡単な案件を受けたり、先輩業者の手伝い(応援)に入ったりして実績を作りましょう。
| 経験を積む方法 | 得られるメリット |
|---|---|
| マッチングサイトへの登録 | お客さんとの接点や口コミが作れます |
| 先輩業者の応援に入る | プロの段取りや技術を間近で見られます |
| 自宅や知人宅での練習 | 事故を気にせず色々な洗剤を試せます |
STEP2:資格を1つ取る
半年から1年ほど現場を経験してお客さんの対応に慣れてきたら、自分の腕を裏付けるための資格を1つ手に入れましょう。
現場での実績が増えてきたタイミングで資格を取ると、名刺やプロフィールの見栄えが良くなり、成約率が目に見えて上がります。
最初は短期間で取れる「ハウスクリーニング士」などの民間資格や、「ハウスクリーニング技能士3級」が狙い目です。資格を持つことで「一定の基準をクリアしたプロ」として認められ、相場より高い料金設定でも選ばれるようになります。
STEP3:伸ばしたい分野に合わせて新しい資格を取る
以降は、自分の得意な分野や、さらに売上を伸ばしたい方向性に合わせて専門的な資格を追加していきましょう。
例えば、個人宅の主婦層をメインにするなら「整理収納アドバイザー」を取って片付けメニューを増やすのが有効です。
一方で、エアコン掃除を極めて稼ぎたいなら「エアコンクリーニング士」などの実技講習を受けて、難しい機種にも対応できる力を身につけるべきです。このように、自分の商売の強みに合わせた資格を足していくことで、リピート率や客単価をさらに高めていくことができます。
| 事業の方向性 | 追加すべき資格の例 |
|---|---|
| 在宅・主婦層メイン | 整理収納アドバイザー、クリンネスト |
| エアコン掃除特化 | エアコンクリーニング士 |
| 法人・管理会社メイン | ビルクリーニング技能士、排水管清掃 |
【注意】資格の「コレクション」にならないこと
資格をたくさん持っていることと、稼げることは別問題です。自分の仕事に本当に必要かどうかを見極め、取った資格をどう集客に活かすかを常に考える必要があります。
ハウスクリーニングで資格を取るより重要なこと
資格はあくまで仕事を受けるための「入口」であり、実際に稼ぎ続けるためには現場での腕前やお客さんとの信頼関係が欠かせません。
- 口コミと評価の積み上げ
- 集客方法の確立
- 見積もり対応力
口コミと評価の積み上げ
今の時代、ハウスクリーニングで最強の武器になるのは、難しい資格の名前よりも「実際に利用した人の高い評価」です。
ネットで業者を探すお客さんは、資格名よりも「どんな人が来るのか」「本当に綺麗になるのか」を口コミで判断します。高い評価が100件並んでいる状態は、どんな立派な証書よりも強力な「信頼の証明書」になります。
資格はあくまで受注のきっかけを広げる道具と考え、現場で感動を与えて良い口コミを書いてもらう活動を地道に続ける必要があります。
実際の口コミには、以下のように「評価の通りだった」という声が多く寄せられます。
過去に一度も掃除をしてこなかった購入から6年経過した頑固な油汚れ付の我が家のエアコン。。。本当に丁寧かつ親切に作業をしてくださいました。こちらのサイトの口コミ通りでした!!
お客さんは事前の口コミを信じて依頼しており、その期待を裏切らない仕事が次の指名に繋がります。
関連記事:口コミ効果とは?
集客方法の確立
どれだけ立派な資格を並べても、自分たちの存在がお客さんに知られなければ、売上はいつまで経ってもゼロのままです。
資格取得に時間をかけるのと同じくらい、ネットやチラシでお客さんに自分たちを見つけてもらう仕組み作りが重要です。
ミツモアのようなマッチングサイトや、Googleマップでの表示(MEO対策)、SNSでの発信など、複数のルートを持っておく必要があります。「資格を取れば客が来る」というのは間違いで、「資格を武器にして自分からお客さんを呼びに行く」のが商売の基本です。
実際に、営業が苦手な職人さんでも、自動でお客さんと繋がるマッチングサイト「ミツモア」の仕組みを活用して成功している事例があります。
関連記事:自動集客方式の導入で月間成約件数が10倍に!安心料金制で現場も経理もお金の管理が楽に!
見積もり対応力
問い合わせへの返信の早さや、見積もりの内容を分かりやすく説明する力が、仕事が決まるかどうかの最後の決め手になります。
個人宅のお客さんは「知らない人を家に入れる」ことに不安を感じています。そのため、返信が遅いだけで「この人は不誠実かもしれない」と判断されてしまいます。
反対に、返信が早く、追加料金の有無などを事前に細かく説明できれば、資格の有無に関わらず信頼を勝ち取れます。無理な売り込みをせず、お客さんのためを思ったアドバイスをすることが、確実な受注に繋がります。
ハウスクリーニングの資格に関するよくある質問
ハウスクリーニングや清掃業の資格について、現場でよく聞かれる疑問をまとめました。
- 無資格でハウスクリーニングをすると違法ですか
- 国家資格は必ず取らないといけませんか
- フランチャイズに加盟すれば資格は不要ですか
- 主婦や副業でも取れる資格はありますか
- 資格を取れば仕事は増えますか
無資格でハウスクリーニングをすると違法ですか
一般的な家庭の掃除を請け負うだけであれば、資格を持っていなくても法律違反にはなりません。
ハウスクリーニングは特別な免許がいらない自由な商売だからです。ただし、マンションの飲み水タンクを洗う貯水槽清掃や、大きなビルの管理業務を会社として請ける場合は、法律に基づいた登録や有資格者の配置が必要になります。
仕事の範囲を広げる際には、どの作業に資格が欠かせないのかを事前に確認しておく必要があります。
| 掃除の種類 | 資格の必要性 |
|---|---|
| 一般家庭の掃除 | 資格がなくても可能 |
| エアコン洗浄 | 資格がなくても可能 |
| 飲み水タンク清掃 | 研修や資格が必須 |
| 病院の専門清掃 | 資格が実質的に必須 |
国家資格は必ず取らないといけませんか
商売を続ける上で必須ではありませんが、適正な料金で長く稼ぎ続けたいのであれば取得を強くおすすめします。
誰でも始められる商売だからこそ、国家資格はライバルとの違いを一目で伝えるための強力な道具になるからです。
ハウスクリーニング技能士などの国家資格があれば、安い業者と比較された時でも「うちは国に認められた技術があります」と自信を持って説明できます。将来的に会社を大きくしたり、役所の仕事に応募したりする場面でも、国家資格は必ず役に立ちます。
【補足】ハウスクリーニング技能士の難易度
唯一の国家資格であるハウスクリーニング技能士は、1級から3級まであります。実技試験ではレンジフードの洗浄などを制限時間内に行う必要があり、現場で培ったスピードと正確さが試されます。
フランチャイズに加盟すれば資格は不要ですか
フランチャイズ本部の知名度があるため、開業してすぐに個人の資格が求められる場面は少ないです。
理由は、本部の看板でお客さんからの信用を最初から得られるからです。ただし、毎月の売上から数パーセントから数十パーセントのロイヤリティを本部に払い続けることになります。
多額のコストをかけて看板を借りるか、自分で資格を取って実力を証明し、利益をしっかり手元に残すかは、自分の経営スタイルに合わせて決める必要があります。
| 開業の形 | 信用を得る方法 |
|---|---|
| フランチャイズ | 本部の看板や名前で信用を得る |
| 個人での独立 | 資格や口コミで自分の信用を作る |
ハウスクリーニングで仕事を取るならミツモア
ハウスクリーニングで稼ぎ続けるには、資格で得た信頼を「現場での実績」や「お客さんに見つけてもらう仕組み」と組み合わせることが最も重要です。
本記事では、市場ごとの資格の役割や、未経験からプロを目指すための現実的な手順を解説してきました。本当の意味で商売を成功させるためのポイントは、以下の3点に集約されます。
- 市場に合わせた資格選び:個人向けは「信頼獲得」、法人向けは「事業登録」と、狙う相手によって目的を使い分けることが大切です。
- 資格取得のステップ:いきなり資格取得に走るのではなく、まずは現場で実績を作り、後から資格で信頼を補強する流れが最も効率的です。
- 資格より大切なのは実務の質:最後はお客さんからの口コミや、返信の早さ、そして何より丁寧な仕事ぶりが成約の決め手になります。
資格を武器として最大限に活かすためには、自分たちの存在を多くのお客さんに知ってもらう「集客の仕組み」が必要です。ミツモアを活用すれば、取得した資格をアピールしながら、効率よく仕事の依頼を受けられます。
ハウスクリーニングの効果的な営業方法は?テレアポ・飛び込み営業用トークも紹介
ハウスクリーニングの効果的な営業方法は?テレアポ・飛び込み営業用のトークも紹介
ハウスクリーニングで独立しても、「とにかく数をこなす」という営業だけでは成約は望めません。
資金も時間も限られた一人親方や個人事業主でも、正しいターゲット選定と仕組み化を通じ、安定して仕事を獲得する営業のコツがあります。
法人・個人別の具体的な営業手法、効果的な営業用のトークスクリプトを解説します。
この記事の要約
- テレアポや飛び込み営業は、相手の困りごとを解決する提案と継続的な接触が成功の鍵
- マッチングサイトを活用して、営業の手間を減らしながら成約数を大幅に伸ばした事業者の実例があります
ハウスクリーニング営業先の種類
ハウスクリーニングの営業先は、「法人顧客」と、「個人顧客」の2つに大きく分かれます。
法人顧客
法人顧客は一度契約すると定期的な発注が見込めるため、経営の基盤を安定させるために不可欠です。
不動産管理会社
不動産管理会社は入退去に伴う空室清掃を定期的に依頼するため、年間を通じて安定した仕事量を確保できます。
管理会社は複数の清掃業者を抱えている場合が多いです。まずは「サブ業者」として入り込み、実績を積んで主力業者への昇格を目指す戦略が現実的となります。
2月から3月の引越シーズンは依頼が急増するため、繁忙期のサポートを提案すると契約に繋がりやすいです。
工務店・リフォーム店
工務店やリフォーム店と関係を築くことで、工事完了後の仕上げクリーニングの案件を取ることができます。
新築の引き渡し前やリフォーム後の清掃は、施工品質を引き立てる重要な工程です。
工務店は引き渡し日を厳守する業界であるため、納期遵守や急な日程変更への柔軟な対応が信頼を得る決め手となります。
個人顧客
個人のお客さん向けの営業は、仕事の品質がそのまま次の口コミや紹介に繋がりやすいのが大きな強みです。
現代では共働き世帯や高齢者世帯が増えており、自分たちでは落としきれないエアコンのカビや浴室の水垢などを、お金を払ってでもプロに頼みたいというニーズが広がっています。
市場調査データからも、今後の需要拡大が期待できることが分かります。
【補足】ハウスクリーニングの潜在需要
J-Net21の調査(2025年版)によると、現在の利用率は7.0%ですが、今後の利用意向を示す人は29.4%に達しています。潜在市場は現在の4倍以上あると推計されています。
出典:J-Net21「ハウスクリーニング業」
ハウスクリーニングの営業で失敗する理由
営業で成果が出ない背景には、法人・個人の顧客がそれぞれ求める「本当の悩み」に寄り添えず、自社の売り込みばかりが先行しているという現状があります。
- 顧客のニーズを正確に把握できていない
- 自社の強みを明確に打ち出せていない
- 継続的なフォローができていない
顧客のニーズを正確に把握できていない
法人顧客が求める「確実性」や個人顧客が抱く「家の中に他人を入れる不安」など顧客ニーズを理解できていないことが、成約を逃す最大の原因です。
不動産管理会社などの法人は、入退去が重なる繁忙期に「確実に納期を守ってくれること」や「急な依頼に対応できる柔軟性」を最優先に判断します。
一方で個人のお客さんは、破損や仕上がりの雑さに対して強い不安を抱いており、作業前の丁寧な説明や養生の徹底といった安心感を求めています。
相手の立場によって重視するポイントが異なるため、相手の悩みの核心を突かない的外れな提案は、どれだけ熱心に行っても選ばれることはありません。
【補足】消費者トラブルの増加
国民生活センターによると、作業後の破損や色落ちといったトラブル相談が増えています。業界全体の信頼性が問われている現状では、作業前の丁寧な説明やクリーニング後の写真撮影といった対策を講じているかどうかが、お客さんが業者を選ぶ際の重要な基準となります。
出典:国民生活センター「ハウスクリーニングでのトラブル」
自社の強みを明確に打ち出せていない
他社との違いを客観的な数字や実績で示せないと、最終的に「価格の安さ」だけで比べられる消耗戦に陥ってしまいます。
特に法人営業では、損害賠償保険の加入有無や、ハウスクリーニング技能士などの資格の有無が、業者の信頼性を測る最低限の基準となります。
これらを明確に打ち出せないと、単なる「安売り業者」と見なされ、利益の出ない厳しい条件での仕事を強いられることになります。
個人向けでも、エコ洗剤の使用や女性スタッフの同行といった「具体的なメリット」を言葉にできなければ、数ある業者の中に埋もれてしまうのが現状です。
継続的なフォローができていない
一度の訪問や作業で連絡を絶ってしまうことは、安定した収益源となるリピート案件や紹介の機会を放棄することにもなり、もったいないです。
不動産管理会社や工務店などの法人は、一度使ってみて問題がなければ次も頼みたいと考えますが、業者の側からも定期的に顔を出さなければ、次第に忘れられてしまうこともあります。
ハウスクリーニングの営業方法【法人向け】
- テレアポ
- 飛び込み営業
- マッチングサイト(B to B)
法人向けの営業では、相手の課題に合わせた提案を行い、粘り強く接触を重ねることが契約に繋がります。
テレアポ
テレアポは事前に準備した台本に沿って相手の困りごとを解決する提案を行うことで、効率よく面談の約束を取り付けられます。
不動産管理会社や工務店へ電話をかける際は、相手が忙しい時間帯を避けることが重要です。受付を突破した後は具体的なメリットを伝えます。
| 業種 | 繋がりやすい時間帯 |
|---|---|
| 不動産管理会社 | 10:00〜11:00、13:00〜15:00 |
| 工務店 | 8:00前後、17:00以降 |
【補足】信頼を築く接触回数
中小企業庁の調査によれば、契約は初回提案後の5回目の接触後が最も多いというデータがあります。一度の電話で諦めず、定期的に連絡を重ねる姿勢が、工務店との太いパイプを作る鍵となります。
出典:J-Net21「ハウスクリーニング業の開業ガイド」
飛び込み営業
飛び込み営業は直接顔を合わせて熱意を伝えられるため、地域密着で信頼を築きたい場合に非常に有効な手段です。
まずは清潔感のある身だしなみを整え、第一印象を良くすることに集中します。
担当者に会えたら、退去後の急な依頼にも対応できる柔軟性や、施工品質を引き立てる仕上げ技術をアピールします。
すぐに仕事に繋がらなくても、名刺や資料を丁寧に渡して顔を覚えてもらうことが大切です。
同じエリアを月に一度のペースで半年ほど繰り返し訪問する「定期巡回」を行うと、困ったときに思い出してもらえる確率が上がります。
【実践のコツ】資料の渡し方
担当者に会えなかった場合でも、「資料だけでもお渡しいただけますか」と受付で低姿勢にお願いしましょう。
マッチングサイト(B to B)
法人向けのマッチングサイトは営業の手間を大幅に減らしながら、仕事を探している業者と依頼したい会社を効率よく結びつけてくれる方法です。
建設業界向けのマッチングプラットフォームや企業間取引サイトでは、不動産管理会社や工務店が協力業者を探しています。
プロフィールに対応エリアや保有資格、過去の施工実績を詳しく記載することで、条件に合う案件の打診を受けやすくなります。
サイト経由で信頼関係を築けば、継続的な発注や大型案件の紹介に繋がる可能性が高まります。
【実践のコツ】法人向けサイトの活用
法人案件では「実績」と「対応力」が重視されます。小規模な案件から着実にこなして評価を積み上げ、急な依頼にも柔軟に対応できる姿勢を示すことで、信頼される協力業者として定着できます。
ハウスクリーニングの営業方法【個人向け】
- チラシ・ポスティング
- ホームページ
- Googleビジネスプロフィール
- マッチングサイト(B to C)
個人のお客さんから直接仕事をもらうには、チラシ配布やネット集客などの複数のやり方を試して地域の知名度を上げることが重要です。
チラシ・ポスティング
チラシは地域を絞ってお客さんに直接アピールできるため、ネットを使わない高齢者層などにも有効な手段となります。
反響率は0.01~0.3%と低めですが、引越し時期の3~4月や大掃除前の年末に配ることで需要を捉えやすくなります。
富裕層が多いエリアや、築10年以上が経過した一戸建てが多い地域へ集中して配ることが反響を呼ぶコツです。
チラシを見た人が3秒で内容を理解できるよう、以下の要素を必ず盛り込んでください。
| 必須要素 | 目的 |
|---|---|
| キャッチコピー | 注目を集める |
| 料金の明示 | 安心感を与える |
| 作業前後の写真 | 仕上がりをイメージさせる |
| お客さんの声 | 信頼を高める |
【実践のコツ】配布のタイミング
同じ地域に月1回のペースで3ヶ月ほど繰り返し配ることで認知度が上がり、反響率が向上する傾向があります。「またあの清掃屋さんのチラシだ」と思ってもらうことが大切です。
ホームページ
自社のホームページを作ることは24時間休まず働く営業マンを雇うのと同じであり、ネットで業者を探すお客さんからの信頼を勝ち取る基盤となります。
サービスの詳細や料金だけでなく、職人さんの顔写真や作業へのこだわりを載せることで、顧客の抱える「見知らぬ人を家に入れる不安」を解消し、申し込みのハードルを下げられます。
「地域名+ハウスクリーニング」で検索されたときに表示されるようなSEO対策を行うことが大切ですが、効果が出るまでには時間がかかるため、中長期的な営業方法として位置付けておくとよいでしょう。
Googleビジネスプロフィール
Googleビジネスプロフィールの運用は、地元の人が近所で清掃業者を探した際に無料で自社を表示させて集客に繋げられる非常に効果的な方法です。
Googleマップの検索結果で上位3社に入ることができれば、自分から売り込みに行かなくても依頼が舞い込む状態を作れます。
事例写真を定期的に投稿したり、定休日や営業時間を正確に載せたりすることが重要です。
地道な更新を続けることで、広告費をかけずに安定して集客できる強力な窓口になります。
【実践のコツ】口コミへの返信
お客さんからもらった口コミには、24時間以内に丁寧な返信を心がけましょう。誠実な対応が公開されることで、それを見た他のお客さんも「ここなら安心だ」と感じて依頼に繋がります。
マッチングサイト(B to C)
マッチングサイトとは、ハウスクリーニングを依頼したいお客さんと、仕事を受けたい事業者を結びつけるインターネット上のプラットフォームです。
代表的なサイトには「くらしのマーケット」「ミツモア」「ユアマイスター」などがあり、それぞれ機能や特徴が異なります。
サイトによって掲載料金の体系、集客力、使いやすさに違いがあるため、自社の状況に合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。
ミツモアの自動応募機能
数あるマッチングサイトの中でも、ミツモアは「自動応募システム」に大きな強みがあります。
自動応募システムとは、「対応エリア」「サービス内容」「希望価格帯」などの条件を事前に設定しておくと、その条件に合致する依頼が入ったときに自動的に見積もりを送信してくれる機能です。
この仕組みにより、現場作業中や夜間、休日でも自動的に営業活動が続くため、チャンスを逃さず効率的に案件を獲得できます。
実際にミツモアを利用する事業者からは「自動応募システムをオンにしてみたら、非常にたくさんの見積もり依頼が入ってきて正直驚きました」といった声が寄せられています。
【実践のコツ】「選ばれる見積もり」のコツ
実は一番安い見積もりが選ばれるわけではありません。ミツモアのデータでは、中程度の価格帯で、かつお客さんの予算に配慮した丁寧な提案が最も成約しやすいという結果が出ています。プロとお客さんが対等な立場で互いの条件を見ながら交渉できる仕組みが、双方の納得感を高めています。
関連記事:勝てる見積もりとは?
ハウスクリーニングの新規開拓で使える営業トーク
営業トークでは、相手の忙しさに配慮しつつ「今ある困りごとを助ける予備の業者」という立ち位置で提案することがアポイント獲得の近道です。
- 不動産管理会社向け
- 工務店・リフォーム店向け
不動産管理会社向け
不動産管理会社へのテレアポは、すでに決まった業者がいることを前提に、繁忙期や急ぎの案件をサポートする「サブの業者」としての役割を提案するのが最もスムーズです。
導入
「お忙しいところ失礼します。〇〇(エリア名)で空室清掃を行っております△△(屋号や名前)です。賃貸物件の退去後清掃でお役に立てればと思いお電話しました」
本題
「すでに決まった業者様がいらっしゃると存じますが、引越シーズンなどの繁忙期に、どうしても手が足りなくなることはございませんか?急な退去や特殊な清掃が必要な際、柔軟に動ける体制を整えています」
クロージング
「一度、名刺交換と資料をお届けだけでもさせていただけないでしょうか。来週の火曜日か水曜日の午後、ご都合いかがですか?」
【実践のコツ】断られた時の切り返し
「今は間に合っている」と言われたら、「承知しました。では、既存の業者さんが動けない時の予備として、名刺だけでもお届けさせてください」と伝えます。予備の連絡先として認識してもらうことで、将来の依頼に繋げます。
工務店・リフォーム店向け
工務店やリフォーム店向けには、施工後の最終仕上げを担当することで、施主の満足度をさらに向上させ、大工さんの手間を減らせるメリットを強調します。
導入
「〇〇(名前)と申します。新築やリフォーム後の引き渡し前清掃について、何かお手伝いできないかと思いましてご連絡しました」
本題
「当方のプロの仕上げを提供することで、お施主様が新居に入った瞬間の喜びを最大化し、御社の施工品質をより引き立てるお手伝いが可能です」
クロージング
「大型案件や、人手が不足している時の協力先として、一度ご挨拶させていただけませんか?施工事例の資料をお持ちします。
ハウスクリーニングで営業の手間なく仕事を獲得した事例
ホットスタッフ

ホットスタッフさんは、手動の営業から自動応募システムへ切り替えたことで、月間の成約件数を10倍にまで増やしました。
以前は別の集客サイトを利用していましたが、費用に見合う成果が出ず、営業力不足により受注が安定しないことが悩みでした。
ミツモアの「自動応募システム」を導入した結果、エアコンクリーニングだけで150台を超える受注を達成しています。
クレジットカード決済による「安心の料金制」も取り入れ、現場での現金のやり取りや未回収のリスクをなくしたことで、経営の基盤を固めることにも成功しました。
関連記事:月間成約10倍を実現!営業ゼロで受注が埋まる仕組み
ホームベース

業界歴18年のホームベースさんは、長年の経験という強みに「返信の速さ」と「口コミへの対応」を掛け合わせることで、月に300件近い成約も見込めるほどの成果を出しています。
自動応募システムで営業の時間を削減し、お客さんからの反応に対して即座に応答することに注力。
70件以上の口コミ一つひとつに丁寧に返信し、誠実な人柄を伝えることで、新規のお客さんからの信頼を獲得しています。
豊富な経験に裏打ちされた技術力と、デジタルの効率的な仕組みを融合させたことが成功の要因です。
関連記事:業界歴18年のプロが月三桁成約に迫る理由
ハウスクリーニングの営業でよくある質問
テレアポ・飛び込み営業は今でも有効ですか
地域に根ざした商売を行う上では、直接の対話で信頼を築けるテレアポや飛び込みは依然として有力な手段です。
対面での営業は人柄を直接伝えやすく、地元の企業やお客さんとの結びつきを強める効果があります。
営業が苦手な場合は代行サービスを使う方法や、GoogleビジネスプロフィールなどのWeb集客を並行して負担を減らす工夫も有効です。
台本と資料を揃えて1件ずつ経験を積むことで、徐々に成約のコツを掴めるようになります。
法人営業と個人営業、どちらを優先すべきですか
安定収入を確保したいなら法人営業を優先し、柔軟なスケジュール管理と高単価を狙うなら個人営業に注力する、という使い分けが基本です。
法人営業は一度契約すれば継続的な発注が見込める反面、単価交渉が厳しく利益率は低めです。
個人営業は単発案件が中心ですが、丁寧な仕事をすればリピートや紹介に繋がりやすく、価格設定の自由度も高くなります。
理想は法人で売上の下支えを作りながら、個人案件で利益率を高めるバランス型です。
【実践のコツ】両立の戦略
法人の定期契約で固定収入を月15〜20万円確保し、残りの稼働日を個人案件に充てる配分が現実的です。個人案件はマッチングサイトの自動応募で効率化すれば、法人営業の時間を圧迫しません。
見積もりを出しても選ばれません。成約率を上げるコツは?
最安値を狙うのではなく、お客さんの予算に配慮しながら「なぜこの価格なのか」を丁寧に説明することが成約率向上の鍵です。
ミツモアのデータでは、最安値ではなく中程度の価格帯で、具体的な作業内容や使用する洗剤、所要時間などを明記した見積もりが最も選ばれています。
また、返信の速さも重要で、依頼後24時間以内に見積もりを送ることで成約率が大幅に向上することも分かっています。
ハウスクリーニングで営業の手間をかけたくないならミツモア
ハウスクリーニングで安定して仕事を獲得するには、法人・個人それぞれに適した営業手法を理解し、自社の状況に合わせて複数のチャネルを組み合わせることが重要です。
法人向けには、テレアポや飛び込み営業で直接信頼関係を築くアプローチが有効です。初回提案後も5回程度の接触を重ねることで成約率が高まります。
個人向けには、チラシ配布やGoogleビジネスプロフィール、マッチングサイトなど、複数の窓口を用意して認知度を高める戦略が効果的です。
営業で失敗しないための3つのポイントもおさらいしましょう。
- 顧客のニーズを正確に把握する:法人なら「繁忙期の人手不足」、個人なら「自分では落とせない汚れ」など、相手の具体的な困りごとをヒアリングして提案に活かす
- 自社の強みを明確に打ち出す:エコ洗剤、女性スタッフ、資格保有など、価格以外で選ばれる理由を分かりやすく伝える
- 継続的なフォローを行う:作業後のお礼状や定期的なメンテナンス連絡で、リピートと紹介を生み出す仕組みを作る
営業の手間を減らしたいならマッチングサイト「ミツモア」の活用を
現場作業で忙しい一人親方や個人事業主の方には、自動的に営業活動が進むマッチングサイトの活用が特におすすめです。
中でもミツモアの「自動応募システム」は、事前に設定した条件に合う依頼へ自動で見積もりを送信できるため、作業中もチャンスを逃しません。
実際に導入した事業者からは「成約数が10倍に増えた」といった成果も報告されています。
ハウスクリーニングの仕事は底辺?きつい理由と廃業率、辞める前に試すべき働き方
ハウスクリーニングの仕事は底辺?きつい理由と廃業率、辞める前に試すべき働き方
ハウスクリーニングは、きつい肉体労働や価格競争が原因で、志半ばで仕事を辞める人が後を絶たない厳しい業界です。
他の業態と比較して、ハウスクリーニングを含む「生活関連サービス業」は開廃業の入れ替わりが非常に激しいこともわかっています。
開廃業率の高さは業界が抱える構造的な問題によるものがほとんどです。
集客を自動化する仕組みを整えれば、負担を減らしながら安定して稼ぐ道は必ず見つかります。
無理に現場を詰め込む働き方から抜け出し、プロの技術に見合った報酬を得るための具体的な方法を詳しく解説します。
この記事の要約
- ハウスクリーニングは肉体的負担や価格競争が激しく、開廃業率が高い業界です
- しかし専門知識を要する高度な仕事であり、共働き世帯や高齢化社会の進展によって今後も高い需要が見込まれる価値ある仕事でもあります
- マッチングサイトを活用した集客の自動化を実践することで、安定した収益を確保した事業者の事例もあります
ハウスクリーニングの仕事がきつい理由
ハウスクリーニングの現場がきついと言われる背景には、主に以下の5つの理由があります。
- 力仕事や手作業が多く肉体的に辛い
- 薄利多売の構造から脱却できない
- 季節による需要の変化で収入が安定しないこと
- 顧客への対応で精神的なストレスがかかること
- 身近に相談できる相手がいなくて孤独を感じやすいこと
力仕事や手作業が多く肉体的に辛い
ハウスクリーニングは無理な体勢での作業や重い機材の運搬が続くため、腰痛の発生率が高い仕事です。
現場では中腰や膝をつく姿勢が長時間続くため、身体へのダメージが蓄積しやすくなります。
エアコンの分解洗浄や浴室のカビ取りでは不自然な姿勢を長時間取らざるを得ないことも。
加えて夏場の屋根裏付近での作業は熱中症の危険があり、冬場は冷たい水で手が荒れるなど、一年を通じて身体を酷使する職業でもあります。
薄利多売の構造から脱却できない
薄利多売の構造から抜け出せない職人さんが増えています。
顧客は、価格で業者を決めることもよくあるため、見積もりを下げないと仕事が取れない悪循環に陥ります。
顧客との取引きで手数料が生じる場合、洗剤代やガソリン代など経費を差し引くと、職人さんの手元に残る利益はごくわずかになることも。
十分な収入を確保するためには1日に何件も現場を回る必要があり、結果として薄利多売の構造から抜け出せない方もいます。
季節変動で収入が安定しない
エアコン掃除の依頼が集中する夏場に対して秋や冬は注文が激減するため、月ごとの売り上げが大きく変動して経営を圧迫します。
ハウスクリーニングの需要は季節に大きく左右されます。
5月から8月の繁忙期は休みなしで働くほど忙しくなりますが、10月や11月の閑散期は予定が全く埋まらない日も出てきます。
売り上げが安定しない状態では、毎月の固定費を払うことさえ不安になり、精神的な余裕もなくなります。
年間の収支を平均して管理する習慣がないと、閑散期に資金繰りが苦しくなって廃業を考える職人さんも多いです。
クレーム対応の精神的ストレスがかかる
顧客の期待に応えなければならないプレッシャーや、作業後の細かな指摘への対応が積み重なり、メンタル面での疲れが深刻になります。
ハウスクリーニングは顧客の大切な財産を預かるため、常に家財を傷つけないよう細心の注意を払う緊張感が伴います。
作業中にずっと横で監視されたり、以前の業者と比較されたりする状況は強いストレスになります。
汚れが完全に落ちない場合に「納得できない」と言われるトラブルも避けられません。
対人関係の悩みが長引くと、仕事そのものが嫌になってしまう大きな原因となります。
相談相手が見つかりづらく一人で問題を抱えこんでしまう
個人事業主として一人で全ての業務をこなす職人さんが多いため、現場でのトラブルや経営の悩みを誰にも打ち明けられず孤独になりやすいです。
特に一人親方として動いていると、現場で予想外の故障が起きても自分一人で判断して責任を取らなければなりません。
同業者とのつながりがない環境では、技術的な工夫や適正な価格設定についての情報を得る機会も少なくなります。
孤独な状況下で「きつい」という感情ばかりが膨らみ、解決策が見つからないまま一人で悩み続けてしまう構造があります。
ハウスクリーニング業界の廃業率
ハウスクリーニングは、全産業の中でも業者の入れ替わりが非常に激しい分野です。
統計データに基づいた業界の現状を解説します。
年間廃業率
中小企業庁が公表したデータによると、ハウスクリーニングが含まれる「生活関連サービス業,娯楽業」の開業率は6.2%、廃業率は4.8%となっています。
全産業の平均は開業率4.4%、廃業率3.5%です。
新しく始める人が多い一方で、事業を辞めてしまう人も多い「多産多死」の傾向がはっきりと出ています。
特に従業員を雇わない個人事業主の場合、雇用保険の統計には現れない入れ替わりがさらに多いと考えられるため、現場の競争は数字以上に激しいのが現状です。
出典:中小企業庁「2020年版小規模企業白書」
廃業する原因
安定して仕事を得る仕組みがないことや、安売り競争で手元に利益が残らなくなることが廃業を招く最大の理由です。
ハウスクリーニングは特別な資格がなくても道具を揃えれば始められるため、価格を下げることで注文を取ろうとする新人が次々と現れます。
独自の強みを持たないまま集客サイトの価格順表示で勝負をすると、売り上げから手数料や洗剤代、ガソリン代を引いた後に、自分の生活費が確保できなくなります。
閑散期の資金管理を誤ったり、移動の効率が悪くて現場の件数をこなせなかったりするビジネス設計の甘さが、短期間で事業を畳む結果につながります。
関連記事:ハウスクリーニング仕事がない
生き残る事業者の特徴
厳しい競争を勝ち抜いている人は、価格の安さではなく、専門技術や対応の丁寧さで「選ばれる理由」を確立しています。
安定して経営を続けている事業者は、エアコンの分解洗浄や洗濯機クリーニングなど、高い専門性が求められるメニューを主軸に置いています。
例えば、K’s ACTの神田和英さんは、まだライバルが少なかった洗濯機クリーニングに専門特化したことで、単価を下げて仕事を取る消耗戦から抜け出すことに成功しました。
集客サイトで顧客との出会いを増やしつつ、最終的には予定の8割を直接のリピート依頼で埋める仕組みを作ることが、利益を出し続けるための鍵となります。
関連記事:K’s ACT 神田和英さんの決断
ハウスクリーニングの仕事は底辺ではない理由
ハウスクリーニングは高度な専門性と社会的な需要を兼ね備えた、将来性のある職業です。
決してハウスクリーニングは底辺の仕事ではない理由を解説します。
専門技術が必要な高度な仕事
ハウスクリーニングのお仕事は、洗剤の化学反応や素材の特性への深い理解が求められる、職人の技能が光る仕事です。
床掃除や窓拭きといった単純な作業はロボットに置き換わる可能性があります。
一方で、エアコンの内部洗浄や浴室のカビ取りといった専門的な技術が必要な作業は、今後も人の手による対応が求められます。
洗剤を正しく使い分ける化学的な知識や、家財を傷めない精密な技術を持つプロの価値は、機械には代えられません。
高齢化社会で需要が拡大している
共働き世帯の増加や社会の高齢化により、プロに掃除を頼みたいという家庭は着実に増えています。
2018年の調査では、ハウスクリーニングの市場規模は前の年と比べて12.3%増え、約1,820億円にまで成長しました。
家事代行を含むサービスへの関心は高く、現在は利用していないものの「今後は利用したい」と考えている人は3割近くに達します。
生活を支えるサービスとして社会に定着しており、今後も安定した需要が見込める分野です。
出典:日本経済新聞「ハウスクリーニング市場調査」
出典:J-Net21(中小機構)「消費者アンケート調査」
顧客から直接感謝される価値ある仕事
自分の技術で顧客の困りごとを解決し、対面で「ありがとう」と言ってもらえる体験は、仕事への誇りにつながります。
ただの「掃除屋」としてではなく、暮らしを快適にするアドバイザーとしての役割を果たすことで、顧客との信頼関係はより深まります。
長年の汚れが落ちた瞬間に見せる顧客の驚きや笑顔は、現場で働く職人さんにとって大きなやりがいです。
誰かの役に立っていることを直接肌で感じられる点は、この仕事ならではの魅力となります。
ハウスクリーニングの仕事を辞める判断ポイント
今の仕事がきついと感じたときは、身体の状態と、働き方を変える具体的な改善策が残っているかどうかで今後を判断すべきです。
ハウスクリーニングを続けるか辞めるかの判断材料は、以下の2つに集約されます。
- 健康に深刻な影響が出ている場合
- 改善策を試す余地がまだ残っている場合
健康に深刻な影響が出ている場合
腰痛や膝の痛みが慢性化して日常生活に支障が出ているなら、無理をせず休養や退職を検討する必要があります。
ハウスクリーニングは身体が資本の仕事であり、一度壊すと取り返しのつかないことになります。
朝起きるのが辛かったり、夜も痛みで眠れなかったりする状態は、身体が発している限界のサインです。
無理に作業を続けて深刻な後遺症を残すよりも、まずは治療に専念することを優先してください。
心身の不調は判断力を鈍らせるため、健康を害してまで現場に立ち続けることは避けるべきです。
改善策を試す余地がまだ残っている場合
集客や単価の見直しなど、現状を打開する具体的な戦略をまだ試していないのであれば、廃業を決めるのは早いかもしれません。
ハウスクリーニングがきついと感じる原因の多くは、職人さんの能力不足ではなく、集客不足や低単価といった業界の構造的な問題にあります。
マッチングサイトを活用して営業の手間を減らしたり、専門技術に特化して単価を上げたりすることで、現在の苦境を解決できる可能性があります。
独立初期の月収目標や成約率を高める具体的な手順を再確認し、戦略次第で状況が変えられるかどうかを冷静に見極めることが大切です。
ハウスクリーニングの仕事を楽にする具体的な方法
ハウスクリーニングの仕事を無理なく続けるためには、以下の5つの対策を組み合わせて今の働き方を変えていくのが現実的です。
- 単価を上げて労働時間を減らす
- マッチングサイトで営業時間を削減する
- 案件の数ではなく単価を重視する
- リピート客を増やして集客を安定化させる
- 腰痛と体力消耗を防ぐ
単価を上げて労働時間を減らす
洗濯機クリーニングなどの専門技術に特化すれば、少ない作業件数でも十分な利益を確保できるようになります。
「何でもやる業者」から「特定の家電に強いプロ」へと立場を変えることが、価格競争から抜け出す近道です。
実際に、ドラム式洗濯機のハウスクリーニングに特化した業者は、閑散期でも安定した依頼を獲得し、年間300台以上の実績を積んでいます。
専門性が高まれば1件あたりの作業時間も短縮でき、身体の負担を抑えながら売り上げを伸ばせます。
関連記事:価格競争から脱出した専門特化戦略
マッチングサイトで営業時間を削減する
マッチングサイトを活用すればチラシ配りや対面営業といった手間を省いて現場作業に集中できます。
自分でホームページを作ったり広告を出し続けたりしなくても、サイト自体が持つ集客力によって依頼が集まるため、営業活動に不慣れな人でも仕事を確保しやすくなります。
中でもミツモアは、忙しい職人さんの負担を減らす機能が充実しています。
例えば「自動応募」の機能を使えば、あらかじめ設定した条件に合う依頼に対してシステムが自動で見積もりを送ってくれるため、現場で手を動かしている間も営業活動が止まりません。
自分の強みを短く伝える「キャッチコピー機能」や、他社との違いを可視化する「特長タグ機能」を設定するだけで、効率的に売り込みができます。
3件以上の口コミを集めると成約率が3倍に高まるというデータや、スマホでの早い返信によって成約率が2.6倍まで伸びるという実績もあり、営業に費やす時間を最小限に抑えながら収入を安定させられます。
関連記事:口コミ効果とは?
関連記事:ミツモアはスマホ依頼が6割。30分以内の返信で成約率2.6倍!
案件の数ではなく単価を重視する
相場よりも高い単価を設定し、1件あたりの利益を最大化することが、過酷な労働から抜け出しハウスクリーニングで稼ぎ続けるための鉄則です。
市場には多くの業者が存在し、標準的な価格で勝負するとどうしても件数を詰め込む「薄利多売」の働き方になってしまいます。
まずは、ミツモアの成約データに基づいた一般的なハウスクリーニングの料金相場を確認してください。
| 品目 | 料金相場 |
|---|---|
| 壁掛けエアコンクリーニング | 7,000円~8,500円/台 |
| 壁掛け(お掃除機能付き)エアコンクリーニング | 11,550円~13,860円/台 |
| 浴室クリーニング | 12,000円~15,000円 |
| ドラム式洗濯機クリーニング | 25,000円~28,500円 |
※参考:ミツモア(2024年1月~12月の成約データをもとに算出)
壁掛けエアコンの中央値は約7,980円ですが、利益を確保して仕事を楽にするためには、標準価格へ専門資格や丁寧な作業といった付加価値を乗せ、相場以上の単価で受注する戦略が必要です。
成功している業者は「専門資格を持つプロ」としての価値を伝え、価格競争に巻き込まれない適正な高単価を実現しています。
安易な値下げは身体を壊す原因になるため、作業の品質を高く保ちつつ、自分に見合った対価を受け取ることが重要です。
リピート客を増やして集客を安定化させる
ハウスクリーニングの作業後に顧客自身で行えるお手入れ方法を伝えることで、信頼関係が深まり、次回の指名に繋がります。
新規の顧客を集める費用はリピート客の5倍かかると言われており、予定の8割を既存の顧客で埋めることが経営を安定させる鍵です。
実際の口コミでも、作業後のメンテナンス方法まで丁寧に教えてくれる職人さんは高く評価されています。
一度の作業で「この人にまた頼みたい」と思ってもらえれば、集客の悩みから解放され、心にゆとりを持って働けるようになります。
腰痛と体力消耗を防ぐ
腰を痛めない動き方を身につけ、便利な道具を積極的に使うことで、健康を損なわずに仕事を続けられます。
ハウスクリーニングでは作業中の姿勢が原因で腰痛を抱えやすいため、日々のケアを怠らないことが重要です。
軽いコードレス掃除機や伸縮ポールなどの機材を揃えれば、手作業の疲れも大幅に減らせます。
ミツモアできつさを乗り越えたハウスクリーニング事業者の事例
HOME BASE

HOME BASEの白石さんは、18年の経験をプロフィールで丁寧に見えるようにし、自動応募を使いこなすことで営業の負担を減らしながら月100件近い成約を実現しました。
課題・背景
18年もの長い間、ハウスクリーニングの現場で腕を磨いてきた白石さんですが、ネットでの集客には苦戦していました。
対面なら伝わる自分の良さも、ネット上ではうまく伝わらず、見積もりをたくさん出してもなかなか仕事が決まらない日々が続いていました。
成果・取り組み
白石さんは、18年の実績や今まで対応してきた現場の様子をプロフィールに詳しく書き込みました。
加えて、ミツモアの自動応募システムを導入したことで、依頼が届いた瞬間に対応できる体制を作りました。
成功のポイント
ベテランならではの深い知識を言葉にして顧客に安心感を与えつつ、返信の早さを組み合わせたことが成功の鍵です。
経験という武器をネットで見えるようにしたことで、営業の手間をかけずに安定して仕事が舞い込むようになりました。
関連記事:自動応募で月三桁成約に迫るハウスクリーニングのプロが語る、ミツモアが顧客から選ばれる理由
K’s ACT

K’s ACTの神田さんは、洗濯機クリーニングの専門家になる道を選んだことで、体力を削る安売りの競争から抜け出すことができました。
課題・背景
独立したばかりの頃は、何でも引き受ける便利屋のようなスタイルで活動していました。
しかし、それでは他社との違いが出せず、結局は値段を下げるしかない厳しい戦いに疲れ果てていました。
成果・取り組み
神田さんは、まだライバルが少なかった洗濯機クリーニングに絞って勝負することを決めました。
メーカーごとの分解方法や汚れの落とし方を徹底的に勉強し、専門家としての腕を磨き続けました。
成功のポイント
「洗濯機のことなら神田さん」と言われるまで専門性を高めたことが一番の理由です。
専門特化したことで価格競争に巻き込まれなくなり、年間300台以上の依頼を安定して受ける働き方を確立しました。
関連記事:年に300台以上の洗濯機クリーニングを手がけるプロに聞いたミツモア活用のコツ
ReLife合同会社

ReLife合同会社の酢藤さんは、30分以内の素早い返信と顧客への丁寧な説明を仕組み化したことで、月に50件もの成約を安定して続けています。
課題・背景
一人で現場の作業も営業もこなしていたため、「営業に力を入れると作業ができない、作業を優先すると次の仕事が取れない」という板挟みの悩みを抱えていました。
成果・取り組み
問い合わせには必ず30分以内に返信することを自分に課し、事前の写真確認などで現場の状況を正確に掴む工夫をしました。
安易な値引きをせず、なぜその金額が必要なのかを顧客に納得してもらうコミュニケーションを徹底しました。
成功のポイント
現場作業以外のやり取りを効率よく進める「仕組み」を作ったことが、少ない労力で高い成約率を保つ秘訣です。
この仕組みによって300件近い口コミが集まり、今では無理なく経営を続けられる土台ができています。
関連記事:月50件成約のトップクラスプロが語る、ミツモアでビジネスを成功に導く5つの要素とは?
ハウスクリーニングの仕事のきつさに関するよくある質問
ハウスクリーニングの現場で働く皆さんが抱く不安や疑問について、以下の4つの項目で回答します。
- 正社員と個人事業主のきつさの違い
- 長く続けられる年齢の目安
- 身体を守るための具体的な予防策
- 仲間とつながるためのコミュニティ
正社員と個人事業主はどちらがきついですか
会社のルールに縛られる不自由さを取るか、集客や収入の全てを自分一人で背負う重圧を取るかによって、きつさの種類が異なります。
個人事業主は売り上げが自分次第ですが、集客や経理も自分で行う必要があるため、作業以外の負担が重くなります。
一方で正社員は給料こそ安定しますが、会社が決めた過酷なスケジュールや人間関係に悩まされる場面が多いです。
自分の性格や大切にしたい価値観に合わせて、どちらの環境が自分に向いているかを見極める必要があります。
何歳まで続けられる仕事ですか
体力に合わせて仕事の量や内容を調整できる環境を整えれば、60代以降も現役のプロとして活躍し続けられます。
若い頃と同じように現場を詰め込む働き方では限界が来ますが、単価の高い案件に絞るなどの工夫をすれば、年齢を重ねても無理なく働けます。
実際に20年以上続けている職人は、体力勝負の現場から「居住空間の助言者」へと立場を変えることで、長く現役を続けています。
年齢とともに技術を磨き、身体に負担をかけない「効率的な働き方」へ移行することが長く続ける鍵です。
体を壊さないための対策はありますか
無理な体勢を避ける動作の基本を守り、作業管理と健康管理を徹底することが、身体を守るために不可欠です。
厚生労働省の職場における腰痛予防対策指針では、膝を曲げて荷物を持つことや、こまめな休憩、そして6ヶ月に1回の健康診断を推奨しています。
軽いコードレス掃除機や伸縮ポールなどの便利な機材を揃えることで、手作業による疲れも大幅に減らせます。
作業後にはお風呂で筋肉をほぐしたり、ストレッチを日課にしたりすることで、疲労を翌日に残さない習慣も効果的です。
出典:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」
同業者と交流できる場所はありますか
SNSなどのオンライン上での交流や、仕事の現場で出会う職人仲間とのやり取りが、孤独感を解消するための貴重な場になります。
一人での作業が多いハウスクリーニングでは、同じ悩みを持つ仲間との情報交換が心の支えになります。
マッチングサイトのコミュニティやSNSでの発信を通じて、技術の相談や現場の裏話ができるつながりを作ると、精神的な負担を軽くできます。
一人で問題を抱え込まず、外部との接点を持つことで、新しい仕事のヒントが見つかることも多いです。
ハウスクリーニングで仕事を取るならミツモア
ハウスクリーニングでのお仕事のきつさを乗り越えるためには「正しい姿勢と道具で身体を守ること」「安売りを避けて単価を上げること」そして「営業を仕組み化すること」が欠かせません。
こうした課題を解決する手段として、マッチングサイトは非常に有効です。
チラシ配りや電話営業に歩き回る必要がなくなり、ネット上で効率よく自分に合った顧客と出会えるようになります。
中でもミツモアは、現場で忙しく働く職人さんの負担を減らす機能が充実しています。
自身の強みを短く表現できる「キャッチコピー機能」や、専門資格などの強みを一目で伝える「特長タグ機能」を整えるだけで、価格の安さだけで選ばれる消耗戦から抜け出すことができます。
こうした仕組みを使って実績を積み、無理な売り込みをしない安定した経営基盤も手に入れた事業者がミツモアにたくさんいます。
正しい戦略でマッチングサイトを使いこなせば、「きつい割に稼げない」という状況を確実に打破できるはずです。
ハウスクリーニングのおすすめフランチャイズ(FC)10選を一覧比較!自身にあったフランチャイズの選び方も解説
ハウスクリーニングのおすすめフランチャイズ(FC)10選を一覧比較!自身にあったフランチャイズの選び方も解説
ハウスクリーニングのフランチャイズは、ロイヤリティの仕組みや開業資金がフランチャイズごとに大きく異なります。「有名ブランドなら安心」「研修があるから大丈夫」という判断だけでは、加盟後に想定外の費用負担や契約の縛りで失敗するリスクがあります。
しかし、法定開示情報22項目、ロイヤリティ、資金計画の3点を押さえれば、誰でも失敗を防げます。
この記事では、おそうじ本舗など主要10社のロイヤリティの比較から、開業費用、安定した収益化を実現する成功パターンまで解説します。
記事の要約
- おそうじ本舗など主要10社のロイヤリティは月額3.3万円〜10万円の固定型と売上の15〜30%の歩合型に分かれる
- 開業資金は80〜250万円が目安で、運転資金として30〜100万円も必要
- フランチャイズに加盟せず年間200件超の成約、複数企業との年間契約獲得に成功した事例もミツモアに存在
ハウスクリーニングのフランチャイズの選び方
自分の状況に合ったタイプを選ぶ
ハウスクリーニングのフランチャイズは、本部の規模や支援内容によって特徴が大きく異なります。自分の経験・資金・求める支援レベルに合ったタイプを選ぶことが成功の第一歩です。
ロイヤリティの仕組みで選ぶ
ロイヤリティは毎月の固定費に直結するため、最も重要な選択基準です。大きく分けて「固定型」「歩合型」「ゼロ円型」の3タイプがあります。
- 固定型(月3〜10万円):売上に関係なく毎月一定額を支払う。売上が伸びても負担が増えないため、高収益を目指す人に適している
- 歩合型(売上の15〜30%):売上に応じて支払額が変動。開業初期は負担が軽いが、売上が伸びると支払額も増加。開業初期の負担を抑えたい人、段階的に売上を伸ばしたい人に適している
- ゼロ円型:加盟金・ロイヤリティ不要だが、本部からの案件紹介に依存する形態が多い。開業資金を最小限に抑えたい人、本部からの案件紹介を活用したい人に適している
事業の特化型で選ぶ
標準的なハウスクリーニング以外に、特定分野に特化したフランチャイズもあります。
- 環境配慮型:エシカルノーマルのように化学薬品を使わないエコ清掃に特化し、健康志向の顧客をターゲットにしている。リピート率100%という高い顧客満足度が特徴
- 不動産特化型:FULLHOUSEのように退去立会いと原状回復工事に特化。BtoB中心のため安定性が高く、副業から始められる立会いプランも用意されている
- 法人特化型:ダイキチカバーオールのようにオフィスビルや商業施設などの法人案件に強く、安定収入を見込める
最終判断前の5つのチェックポイント
ここまでで自分に合ったタイプが見えてきたら、以下の5点を必ず確認しましょう。どのタイプのフランチャイズでも共通して重要な項目です。
- 法定開示情報22項目の確認
- 本部の集客支援体制の見極め
- ロイヤリティの詳細条件の確認
- 契約解除時および競業避止条項の確認
- 既存加盟店の実績数値の確認
1. 法定開示情報22項目を必ず確認する
法定開示情報22項目とは、中小小売商業振興法で定められた、フランチャイズ本部が契約前に加盟希望者へ開示すべき情報です。商標登録状況、加盟店数と閉店店舗数の推移、研修内容、ロイヤリティの仕組み、競業避止条項、契約期間・更新・解約条件などが含まれます。
中小企業庁が本部の開示状況を継続的に調査しており、十分な情報開示を行っていない本部との契約はトラブルの原因となります。契約前に情報を一つひとつ確認することで、「聞いていなかった」「想定と違った」という事態を防げます。
特に注意すべき項目は以下の4点です。
- 加盟店数と閉店店舗数の推移:閉店店舗数が増加している本部は支援体制や収益性に問題がある可能性
- ロイヤリティの仕組みと金額:売上連動型か定額型かで収益性が大きく変わる
- 競業避止条項の内容:契約終了後に同業種での開業が制限される期間と範囲を確認
- 契約解除条件:中途解約時の違約金や条件を明確に理解しておく
契約トラブルの多くは、本部の売上予測と実績の乖離に起因します。中小企業庁は、契約前に弁護士や中小企業診断士など専門家への相談を推奨しています。
出典:中小企業庁「フランチャイズ事業」
出典:中小企業庁「フランチャイズ事業を始めるにあたって」パンフレット
2. 本部の集客支援体制を見極める
本部の集客支援は加盟後の売上に直結するため、ブランドの知名度だけでなく実務レベルでの支援内容を確認することが不可欠です。
全国展開する大手ブランドでも、開業予定エリアでの実績が少なければ期待した集客効果は得られません。本部に「開業予定エリアの加盟店数」「エリア内での月間問い合わせ件数」を具体的な数値で確認しましょう。
集客支援で確認すべき項目は以下の4点です。
- 公式サイトからの顧客送客:本部サイト経由での顧客紹介の有無
- Web集客支援:予約システム、SEO対策、SNS運用支援の有無
- 広告分担金:ロイヤリティとは別の広告費負担義務の有無
- 地域密着型販促支援:チラシテンプレートや販促物の提供有無
3. ロイヤリティの詳細条件を確認する
ロイヤリティの「金額」だけでなく、「含まれるサービス内容」「支払時期」も確認が必要です。
- ロイヤリティに含まれるサービス:集客支援、システム利用料、研修費などが含まれるか、別途請求されるか
- 支払時期:月初一括払いか、売上確定後の後払いか
- 減額・猶予制度:開業初期や売上不振時の減額・猶予制度の有無
- 値上げ条項:将来的なロイヤリティ値上げの可能性
損益分岐点の計算も重要です。月間売上がいくらになればロイヤリティを支払っても十分な利益が残るのか、複数のシナリオで試算しておきましょう。
関連記事:フランチャイズロイヤリティ相場
4. 契約解除時と競業避止条項を確認する
契約解除条件と競業避止条項は将来の事業継続や方向転換の可否に大きく影響するため、契約前の確認が不可欠です。
契約解除について確認すべき項目は以下の4点です。
- 契約期間:2〜5年が一般的だが本部により異なる
- 中途解約の可否:解約可能条件が限定されている場合が多く、本部の契約違反時などが該当
- 違約金額:残契約期間に応じた違約金や固定額の違約金が設定
- 更新条件:自動更新か、更新料の支払いが必要か
競業避止条項については、契約終了後に同業種での開業が制限される期間と範囲を確認します。期間は1〜3年程度、範囲は半径○km以内などと設定されています。競業避止条項が過度に厳しい場合、フランチャイズ離脱後にハウスクリーニング事業を継続することが困難になります。
公正取引委員会は「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」で、優越的地位の濫用を規制しています。不当な商品購入の強制、一方的な契約変更などが該当します。公正な契約関係を保てる本部であるかも判断材料です。
出典:公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
5. 既存加盟店の実績数値を確認する
既存加盟店の売上実績や継続率は、本部の支援体制の質を判断する客観的な指標となります。
本部に確認すべき実績数値は以下の4点です。
- 加盟店の平均売上と中央値:平均値だけでなく中央値も確認することで実態に近い数値を把握できる
- 加盟店継続率:開業後1年、3年、5年時点での継続率
- 閉店理由の内訳:売上不振、オーナー都合、契約満了など
- 成功事例と失敗事例:両方を開示している本部は信頼性が高いと判断できる
公式発表情報だけでなく、インターネット上のレビューサイトやSNSで既存加盟店の評判を調べることも有効です。投稿時期に注目し、最新の口コミを優先的に確認しましょう。数年前の情報では現在の本部体制や支援内容と異なる可能性があるためです。
本部に「既存オーナーとの面談機会」を依頼することも選択肢です。直接質問することで、契約書に記載されていない実務上の注意点や地域特性に関する情報を得られます。
ハウスクリーニングのフランチャイズをロイヤリティで比較
ハウスクリーニングのフランチャイズをロイヤリティで比較すると、月額3.3万円固定のハウスコンシェルジュから、加盟金・保証金・ロイヤリティ全て0円のカジタクまで大きな差があります。
主要フランチャイズ各社について、公式発表情報に基づき加盟金とロイヤリティを紹介します。加盟金は公式ページに具体的な記載がないフランチャイズもあり、その場合は要問い合わせと記載しています。
| フランチャイズ名 | 加盟金(税込) | ロイヤリティ(税込) |
|---|---|---|
| おそうじ本舗 | 33万円 | 11万円/月 |
| おそうじ革命 | 要問い合わせ | 6.6万円/月 |
| おそうじ名人 | 20万円 | 売上の15% |
| 家工房 | 143万円 | 4.4万円/月+システム料1.1万円 |
| ダイキチカバーオール | 要問い合わせ | 売上の17.3% |
| FULLHOUSE | 110万円 | 8.8万円または11万円/月 |
| エシカルノーマル | 44万円 | 4.4万円/月 |
| ハウスコンシェルジュ | 132万円 | 3.3万円/月 |
| カジタク | 0円※ | 0円 |
| 日本おそうじ代行 | 39.6万円 | 6.8万円/月 |
※カジタクは、別途、研修費、資材費(洗剤・制服など)が必要になります。
おそうじ本舗
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 33万円(税込) |
| ロイヤリティ | 月額11万円(税込・固定) |
| 開業資金 | 約420万円(税込) |
| 研修内容・期間 | 24日間(実技・座学) |
| 集客・案件紹介 | 本部からの案件紹介・集客支援あり |
| 向いている人 | 知名度の高いブランドで安定集客したい人 |
おそうじ本舗は全国1,765店舗以上を展開する業界最大手で、高い知名度による集客力が最大の強みです。
加盟金は33万円、ロイヤリティは月額11万円です。別途、広告分担金として月4.4万円などが毎月発生します。24日間の研修プログラムでは、清掃技術から営業手法まで学べます。開業後も半年後研修やスーパーバイザーによるフォローが用意されています。
広告分担金を含む本部による販促・集客支援があり、本部からの案件紹介を通じて顧客に認知されやすい点が特徴です。ブランド力を重視し、安定した集客を求める方におすすめです。
おそうじ革命
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 公式ページに記載なし(要問い合わせ) |
| ロイヤリティ | 月額6.6万円(税込・固定) |
| 開業資金 | 公式ページに総額記載なし |
| 研修内容・期間 | 約50日間(業界最長クラス) |
| 集客・案件紹介 | 本部からの案件紹介・集客支援あり |
| 向いている人 | 定額ロイヤリティで売上を伸ばしたい人 |
おそうじ革命は月額6.6万円の完全定額ロイヤリティと約50日間の充実した研修が特徴で、未経験者でも技術を習得しやすい環境です。
開業資金には加盟金が含まれますが、金額は公式ページに記載がないため要問い合わせです。売上が伸びてもロイヤリティが増えない定額制のため、高収益を目指すオーナーに適しています。開業後はWeb集客支援や技術動画の共有など、継続的な支援体制も充実しています。本部からの案件紹介も可能です。
少額資金で開業したい方や、定額制で収益を最大化したい方におすすめです。
おそうじ名人
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | 代理店契約 |
| 加盟金 | 20万円 |
| ロイヤリティ | 売上の15%(代理店フィー) |
| 開業資金 | 約80万円〜 |
| 研修内容・期間 | 14日間+現場同行研修 |
| 集客・案件紹介 | 本部からの案件紹介あり |
| 向いている人 | 営業せず少額資金で独立したい人 |
おそうじ名人は代理店方式を採用しており、売上の15%を代理店フィー(ロイヤリティ)として支払います。
加盟金20万円、研修費30万円、初期商材費30万円で、開業資金は約80万円からです。契約形態は代理店契約で、契約期間は1年ごとに更新します。
約14日間の開業前研修で清掃技術と接客マナーを習得し、先輩代理店との同行OJT(現場研修)で実務を学べます。開業後は定期研修や相談窓口があり、本部からの顧客紹介により営業活動が不要な点が特徴です。融資支援や代理店同士の情報交換の場も用意されています。
少額資金で開業したい方や、本部からの案件紹介で営業活動を最小限に抑えたい方に適しています。
家工房
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 143万円(税込) |
| ロイヤリティ | 月額4.4万円(税込) |
| 開業資金 | 約287万円(税込) |
| 研修内容・期間 | 約10日間(技術・接客) |
| 集客・案件紹介 | 本部支援あり(地域密着型) |
| 向いている人 | 地域密着で長期的に事業を育てたい人 |
※別途:システム利用料 月1.1万円(税込)
家工房は住まいの御用聞き型ビジネスモデルで、月額4.4万円のロイヤリティに加え、システム利用料1.1万円が毎月発生します。
加盟金は143万円で、開業資金の総額は約287万円です。地域密着型営業でリピート率を高めやすく、顧客単価を上げやすい点が特徴です。
地域密着型事業を目指す方に適しています。
出典:家工房
ダイキチカバーオール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 公式ページに記載なし |
| ロイヤリティ | 売上の17.3% |
| 開業資金 | 公式ページに総額記載なし |
| 研修内容・期間 | 初期研修あり(期間非公開) |
| 集客・案件紹介 | 本部からの法人案件紹介あり |
| 向いている人 | 法人向け安定案件を重視したい人 |
ダイキチカバーオールは売上の17.3%という歩合制ロイヤリティで、法人向け清掃案件に強みを持つフランチャイズです。
加盟金は公式ページに記載がないため要問い合わせです。オフィスビルや商業施設など法人契約を獲得できれば、定期的かつ安定した収益を構築できます。法人案件は単発の個人宅清掃と比べて継続性があり、閑散期でも収入を維持しやすい利点があります。
ロイヤリティ率が高いため、売上が伸びるほど本部への支払いも増える点に注意が必要です。法人営業に自信があり、大口契約を獲得したい方に適しています。
出典:ダイキチカバーオール
FULLHOUSE
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 110万円(税込) |
| ロイヤリティ | 月額8.8万円または11万円(税込・固定) |
| 開業資金 | 約154〜198万円(税込) |
| 研修内容・期間 | 初期研修あり |
| 集客・案件紹介 | 本部支援あり |
| 向いている人 | 退去立会いや原状回復工事で収益化したい人 |
FULLHOUSEは退去立会いと原状回復工事に特化したフランチャイズで、立会いプランと実技プランの2種類から選択できます。
加盟金は110万円で、ロイヤリティは立会いプランが月8.8万円、実技プランが月11万円です。研修費は44〜88万円で、研修日数により異なります。立会いプランはPC1台で開始でき、作業時間も1〜2時間程度のため、副業からスタート可能です。実技プランでは清掃・クロス工事・床工事を習得でき、利益率は最大90%です。
契約期間は3年で、店舗不要で自宅をオフィスにできます。BtoBビジネスのため安定性が高く、業界初の営業代行をはじめとした本部支援が充実しています。
副業から始めて月収20万円プラスしたい方や、不動産関連事業で独立したい方に適しています。
出典:FULLHOUSE
エシカルノーマル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 44万円(税込) |
| ロイヤリティ | 月額4.4万円(税込・固定) |
| 開業資金 | 約253万円(工具・車両費別途) |
| 研修内容・期間 | 初期研修あり(期間非公開) |
| 集客・案件紹介 | 本部支援あり |
| 向いている人 | 環境配慮型サービスで差別化したい人 |
エシカルノーマルは環境と健康への配慮を徹底した、化学薬品不使用のエコ清掃特化型フランチャイズです。
加盟金は44万円、研修費176万円、保証金10万円などで、開業資金は約253万円(工具・車両費別途)です。ロイヤリティは月額4.4万円の定額制です。契約期間は3年です。
劇薬を一切使わない独自開発洗剤を使用しており、高齢者や小さな子ども、ペットがいる家庭、アトピーや喘息などの症状がある方がいる家庭から高い支持を得ています。顧客リピート率は100%で、口コミによる新規顧客獲得がしやすい点が特徴です。
有料会員制度と定期清掃プランで、閑散期でも収入が安定します。病院、高齢者施設、幼稚園、飲食店などの法人顧客にも対応できます。
環境意識の高い顧客層をターゲットにしたい方や、健康配慮を重視した持続可能な経営を目指す方に適しています。
出典:エシカルノーマル
ハウスコンシェルジュ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 132万円(税込) |
| ロイヤリティ | 月額3.3万円(税込・固定) |
| 開業資金 | 約294万円(税込) |
| 研修内容・期間 | 約10日間 |
| 集客・案件紹介 | 本部支援あり |
| 向いている人 | ロイヤリティを抑えて利益率を重視したい人 |
ハウスコンシェルジュは月額3.3万円という業界最安クラスのロイヤリティで、売上が伸びるほど利益を確保しやすい仕組みです。
加盟金は132万円で、開業資金の総額は約294万円です。10日間の研修プログラムで清掃技術を学べます。ロイヤリティ負担を最小限に抑え、利益率を最大化したい方に適しています。
出典:ハウスコンシェルジュ
カジタク
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | 業務委託型パートナー |
| 加盟金 | 0円 |
| ロイヤリティ | 0円 |
| 開業資金 | 約15万円(研修費・資材費) |
| 研修内容・期間 | 技術研修あり(期間非公開) |
| 集客・案件紹介 | 本部からの案件紹介あり |
| 向いている人 | 本部からの案件紹介に依存しても問題ない人 |
カジタクはイオングループ運営の業務委託型パートナー制度で、加盟金・ロイヤリティが0円である代わりに、本部からの案件紹介に依存する仕組みです。
開業資金として研修費と資材費で約15万円が必要です。毎月のロイヤリティは不要ですが、案件は本部経由の紹介が中心となるため、自社での集客や価格設定の自由度は制限されます。イオンブランドの信頼性を活かした集客力がある一方、案件量や収益性は本部の方針に左右されやすい点に注意が必要です。
初期費用を最小限に抑えたい方や、本部の案件紹介に依存する形で事業を始めたい方に適しています。
出典:カジタク
日本おそうじ代行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業形態 | フランチャイズ契約 |
| 加盟金 | 39.6万円 |
| ロイヤリティ | 月額6.8万円(固定) |
| 開業資金 | 約120万円 |
| 研修内容・期間 | 初期研修あり |
| 集客・案件紹介 | 本部からの案件紹介あり |
| 向いている人 | 副業から小規模に始めたい人 |
※別途:広告分担金 月2万円など
日本おそうじ代行は複数のプランを用意しており、働き方に応じて選択できる点が特徴です。
加盟金は39.6万円、研修費は39.6万円で、開業資金は約120万円です。ロイヤリティは月額6.8万円で、別途広告分担金として月2万円などが発生します。全国展開しており、本部からの案件紹介も期待できます。
売上がロイヤリティを下回る月は、ロイヤリティと広告分担金を免除または返金する保証制度があり、開業リスクを軽減できます。
副業として始めたい方や、少額資金で開業して徐々に事業を拡大したい方に適しています。
出典:日本おそうじ代行
※本記事の情報は2025年12月時点の各社公式ページに基づいています。最新の加盟条件や費用は、各社の公式フランチャイズ募集ページで必ずご確認ください。
ハウスクリーニングのフランチャイズで独立・開業する費用
ハウスクリーニングのフランチャイズで独立・開業するには、初期費用80〜250万円、運転資金として3ヶ月分の経費30〜100万円程度が必要です。
初期費用の内訳と相場
ハウスクリーニング開業時の初期費用は80〜250万円が相場で、加盟金、保証金、研修費、資材費の4項目で構成されます。
各項目の相場は以下のとおりです。
| 費目 | 相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 加盟金 | 10〜90万円 | ブランド使用料・ノウハウ提供の対価。一度限りの支払い |
| 保証金 | 10〜30万円 | 債務不履行時に備えた預かり金。契約終了時に返還される場合が多い |
| 研修費 | 0〜150万円 | 技術研修・営業研修の費用。加盟金に含まれる本部もある |
| 資材費 | 40〜150万円 | 高圧洗浄機・ポリッシャー・洗剤など清掃機材一式 |
作業用車両を用意する場合、別途35〜80万円程度の車両代が発生します。バンなどが該当します。自家用車を使用できれば費用を抑えられます。
ハウスクリーニングは店舗が不要で自宅を事務所にできるため、飲食店や小売店のフランチャイズと比べて初期費用を抑えやすい特徴があります。
開業資金を見積もる際は「契約書に明記されていない追加料金」に注意が必要です。機材費に含まれる洗剤が最低限の量で追加購入が必須というパターンもあります。車両ラッピング費用、名刺・チラシなど販促物制作費、開業時損害保険料なども別途発生する場合があります。本部提示の「開業資金見込み」に、これらの費用が全て含まれているか確認が必要です。
毎月の運営費の内訳
毎月の運営費は一人運営の場合で15〜40万円程度が見込まれ、ロイヤリティ、消耗品費、広告費、車両維持費などで構成されます。
主な運営費の内訳は以下のとおりです。
| 費目 | 相場(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| ロイヤリティ | 3〜10万円(固定型)または売上の8〜20%(歩合型) | 本部への支払い |
| 消耗品・洗剤代 | 3〜5万円 | 作業量に応じて変動 |
| 広告宣伝費 | 2〜5万円 | チラシ・Web広告など |
| 車両維持費 | 2〜3万円 | ガソリン代・駐車場・車検など |
| 損害保険料 | 0.3〜0.5万円 | 賠償責任保険 |
| 通信費 | 0.5〜1万円 | 携帯電話・インターネット |
人件費は一人開業の場合はゼロですが、スタッフを雇用すると月20〜30万円程度の追加負担が発生します。
季節変動への対応も資金計画で見逃せないポイントです。ハウスクリーニングは年末や引越しシーズン(3〜4月)に需要が集中し、夏場や年明けは閑散期となります。繁忙期の売上を年間平均と考えてしまうと、閑散期に資金不足に陥るリスクがあります。月別に売上を予測し、売上が低い月でも固定費を賄える資金繰りを準備する必要があります。
運転資金として3ヶ月分の経費を用意する
開業後の3ヶ月間は売上が安定しないと想定し、運営費3ヶ月分と生活費3ヶ月分を運転資金として用意しておきます。
運営費3ヶ月分は50〜120万円程度です。開業直後は顧客基盤がなく集客に時間がかかります。チラシ配布やWeb広告を出してもすぐに成約に結びつくとは限りません。売上ゼロでもロイヤリティや車両維持費など固定費は発生し続けるため、余裕を持った資金計画が不可欠です。
資金調達の選択肢として、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などフランチャイズ開業者向けの低利融資制度があります。本部の融資支援がある場合は積極的に活用すると自己資金不足を補えます。事業計画書作成支援、金融機関紹介などが該当します。
自己資金と借入金のバランスは「自己資金3割以上」が望ましいとされています。全額借入で開業すると返済負担が重く、資金繰りが厳しくなるリスクが高まります。
関連記事:ハウスクリーニング独立
ハウスクリーニングのフランチャイズで成功するパターン
ハウスクリーニングのフランチャイズで成功するパターンには以下の3つがあります。
- 初期投資を早期回収するパターン
- リピーターを増やして安定収益を構築するパターン
- 法人契約を獲得して大規模成長するパターン
初期投資を早期回収するパターン
開業から6ヶ月〜1年以内に初期投資を売上で回収できれば、資金繰りの不安から解放され、事業成長に集中できます。
開業直後は最も資金繰りが厳しい時期です。ロイヤリティや車両維持費など固定費は毎月発生するのに対し、認知度がない状態では売上が安定しません。売上ゼロでも支出は続く期間をいかに短縮するかが早期回収の鍵となります。
開業してから集客を始めると、チラシ配布や広告出稿しても反応が出るまでに1〜2ヶ月かかります。その間も固定費は発生し続け、運転資金を圧迫します。一方、開業前から地域へのチラシ配布やSNS発信を始めておけば、開業初日から予約が入っている状態を作れます。
このパターンで成功する鍵は、開業前から準備し、開業初日から予約が入る状態を作ることです。
早期回収を実現するための実践ポイントは以下の4つです。
- 開業前マーケティング活動:開業日の1〜2ヶ月前から認知活動を始め、開業待機顧客を作ることで初月から売上を立てられる
- 開業キャンペーン:通常より1〜2割安い価格で提供し、まず顧客基盤を作る。初回利用ハードルを下げることで、口コミの種を早めに蒔ける
- 作業効率化:1件あたりの作業時間を短縮し、同じ労働時間でより多くの案件をこなす。売上は「単価×件数」で決まるため、件数を増やせば回収速度が上がる
- 紹介プログラム:「友人紹介で次回割引」など口コミを促す仕掛けを用意し、広告費をかけずに新規顧客を獲得できる
リピーターを増やして安定収益を構築するパターン
新規顧客獲得よりも既存顧客の再利用を重視することで、広告費を抑えながら収益を安定させることができます。
ハウスクリーニング事業で最もコストがかかるのは新規顧客獲得です。チラシ配布、Web広告、ポータルサイト手数料など、1人の新規顧客獲得には数千円から1万円以上の費用がかかります。一方、リピーターは広告費ゼロで再利用してくれるため、粗利益率が大幅に向上します。
さらにリピーターは口コミで新規顧客を連れてきてくれます。「この人に頼めば間違いない」という信頼があるため、紹介顧客も成約率が高く、価格交渉も少ない傾向があります。リピーターを増やすことで「広告費を減らしながら売上を安定させる」という好循環を生み出します。
このパターンで成功する鍵は、技術力だけでなく顧客対応の質を高めることです。
成功しているオーナーに共通するのは、時間厳守・礼儀正しい対応、作業工程の説明、作業後のフォロー連絡といった、顧客との信頼関係構築を重視した姿勢です。一度限りの取引ではなく継続的な関係を築くことで、安定した収益基盤を作れます。
リピート率を高める具体的な方法として、顧客管理システムの活用が有効です。顧客の利用履歴を記録しておき、次回訪問時に「前回は○○でしたが、今回はいかがですか」と声をかけることで、顧客満足度が上がります。前回の作業内容、要望、家族構成などを記録しておきます。
定期連絡や季節挨拶、清掃タイミングのリマインドなど、継続的にコミュニケーションをとることで、「清掃といえばこの人」という存在になれます。エアコンクリーニングなら年1回、水回り清掃なら半年に1回など、適切なタイミングで連絡することで、顧客の他社流出を防げます。
法人契約を獲得して大規模成長するパターン
個人宅向けサービスから徐々に法人向けビジネスへシフトすることで、月間売上を数十万円から数百万円規模に拡大できます。
個人宅清掃は1件あたりの単価が1〜3万円程度ですが、法人契約は月額で数十万円から数百万円規模になることもあります。オフィスビルの定期清掃、不動産管理会社との空室清掃契約、民泊施設の清掃代行などは、一度契約すれば毎月安定した収入が見込めます。
さらに重要なのが閑散期リスクの回避です。個人宅清掃は年末や引越しシーズンに需要が集中し、夏場や年明けは仕事が減ります。閑散期でも法人契約があれば毎月一定の収入が入るため、資金繰りが安定します。従業員を雇用している場合、閑散期でも給与支払いが必要なため、法人契約による安定収入は経営を支える柱となります。
このパターンで成功する鍵は、個人宅清掃から始めて実績を積み、徐々に法人営業を拡大していく段階的アプローチです。
法人営業を成功させるポイントは以下の4つです。
- 実績の積み重ね:まず個人宅や小規模事業者での実績を作り、施工事例として活用する。法人は信頼性を重視するため、実績がないと契約できない
- 紹介の活用:取引のある不動産会社や建設会社に「清掃も対応できます」と伝える。既に信頼関係があれば、新規営業よりも契約につながりやすい
- 体制整備:法人契約では「損害保険の補償額」「従業員教育体制」を求められることが多く、企業として信頼できる体制を整えることが契約の前提となる
- 継続的な営業:年に1件でも大口契約を獲得できれば収入は大きく増えるため、地道な営業を継続する。法人営業は成約まで時間がかかるが、一度契約すれば長期的な収益源となる
サービスの多角化として、ハウスクリーニングと別事業を組み合わせる成功パターンもあります。既に事業を持っている人が清掃フランチャイズに加盟し、既存顧客に清掃サービスも提供することで利益率を上げられます。既に顧客基盤があるため新規営業が不要で、複数サービスを提供することにより顧客単価を上げられます。
ハウスクリーニングのフランチャイズで失敗するパターン
ハウスクリーニングのフランチャイズで失敗するパターンには以下の4つがあります。
- 集客費用に見合う売上を得られない
- 資金計画が甘く運転資金が底をつく
- 技術不足でクレームが発生する
- 契約条件を十分に確認せずミスマッチが起きる
関連記事:ハウスクリーニング仕事がない
集客費用に見合う売上を得られない
チラシ配布やWeb広告に費用をかけても、十分な問い合わせや契約につながらず、赤字が続くケースがあります。
このパターンで失敗する最大の原因は、「本部の看板があれば自動的に仕事が来る」という思い込みです。
都市部では競合他社も多く、顧客を取り合う状況で想定どおりに案件を獲得できないケースも珍しくありません。ポスティングをしても、今すぐハウスクリーニングを必要としていない家庭には響かず、空振りに終わることもあります。
集客での失敗を防ぐための対策は以下の4つです。
- ターゲットの明確化:「共働き世帯」「高齢者世帯」「賃貸退去前の単身者」など具体的なペルソナを設定する
- 複数チャネルの併用:チラシ、Web広告、地域掲示板、不動産会社への営業など、複数の接点を持つことでリスクを分散できる
- 利用ハードルの引き下げ:「無料相談会」「お試し価格キャンペーン」で認知を優先する
- 市場調査の徹底:開業予定エリアの競合状況や潜在需要を事前に調査する。新築マンション入居時期、子育て世帯数などを確認する
資金計画が甘く運転資金が底をつく
楽観的な売上予測で開業した結果、想定より売上が低く、数ヶ月で資金が枯渇してしまうケースがあります。
このパターンで失敗する原因は、「フランチャイズだから安心」と油断し、最悪ケースを想定していないことです。
ロイヤリティや広告分担金など毎月の固定支出があるため、売上が想定より低いと数ヶ月で資金が底をつきます。設備投資や車両購入費用のローン返済が重荷になるケースも少なくありません。
資金繰りのポイントは以下の4つです。
- 複数シナリオでのシミュレーション:最悪ケースでも半年〜1年は耐えられる資金を用意する
- キャッシュフロー計算書の作成:毎月の現金残高を把握し、3ヶ月先まで予測する
- 入金・出金サイクルの理解:法人顧客の場合、請求から入金まで1〜2ヶ月かかることもある
- 緊急時の予備資金の用意:機材故障や大口顧客との契約終了など、予期しない事態に備え、100万円程度を別口座に用意する
本部に「売上不振時のロイヤリティ減額・猶予制度」があるかも確認すべきポイントです。一部のフランチャイズでは、開業初期や災害時にロイヤリティを一時減額する制度を設けています。
技術不足でクレームが発生する
清掃スキルが不十分なまま開業すると、顧客の家財を傷つけるなどのトラブルで信用を失ってしまいます。
ハウスクリーニングは専門的なスキルを必要とする仕事です。強力な洗剤の扱いを間違えれば床が変色します。エアコンの分解清掃手順を間違えれば故障の原因となります。弁償や謝罪で信用を失うと、口コミで悪評が広がり、集客にも悪影響を与えます。
このパターンで失敗する原因は、研修期間を軽視し、技術習得が不十分なまま営業を始めることです。
技術面でのトラブルを防ぐための対策は以下の4つです。
- 基本に忠実な作業:本部マニュアル通りに作業し、標準的な品質とスピードを身につける
- 事前確認の徹底:顧客宅の素材を確認し、洗剤使用可否や養生必要性をチェックリスト化する。床材、壁材などを確認する
- 継続的な学習:開業後も自主的に清掃講習に参加したり、先輩オーナーへ同行研修を依頼する
- 損害保険への加入:万一の事故に備え、賠償責任保険に必ず加入する。補償額は最低1,000万円以上を推奨
契約条件を十分に確認せずミスマッチが起きる
契約前の確認不足により、「想定より本部の縛りがきつかった」「営業エリアが狭くて十分に営業できない」といった不満が後から出てきます。
価格決定権や使用洗剤の種類まで細かく制限され独自の工夫ができない、営業エリアの人口が少なく市場が小さかった、中途解約ができず撤退もできないなど、契約後に「想定と違った」と後悔するケースは少なくありません。
このパターンで失敗する原因は、契約書の詳細を読まず、口頭説明だけで契約してしまうことです。
契約書で重点的に確認すべき項目は以下の5点です。
- 契約期間と更新条件:自動更新か、更新料は必要か
- 中途解約条件と違約金:どんな場合に解約できるか、違約金はいくらか
- 営業エリア範囲と競業避止義務:他の清掃事業はできるか、契約終了後の制限期間
- 価格決定権:本部指定価格か、自由に決められるか
- 仕入先制限:洗剤や機材を本部以外から購入できるか
不明点は必ず文書で回答をもらい、口頭約束だけで済ませないことが大切です。契約前に弁護士や中小企業診断士など専門家にチェックを依頼することも選択肢となります。
ハウスクリーニングのフランチャイズでなくマッチングサイトで儲かるプロの事例
フランチャイズに加盟せず、マッチングサイト「ミツモア」を活用して成功しているハウスクリーニング事業者も存在します。
ミツモアはハウスクリーニングや引っ越しなど様々な生活サービスをオンラインで見積もりしてマッチングするサイトです。登録すると近隣エリアの顧客から清掃の見積もり依頼が届きます。顧客が依頼した内容に合った最大5社に自動で見積もりが届く仕組みのため、価格だけでなく口コミや実績を見て選んでもらえる点が特徴です。
料金は成果報酬型で成約した案件に応じて手数料を支払う仕組みです。広告への先行投資リスクを低く抑えられるため、開業直後で資金に余裕がないときでも活用しやすくなっています。
ミツモアを活用した事例では、月50件、年間200件を超える成約、月間400件を超える成約を達成した事業者がいます。
ReLife合同会社(大阪)

課題・背景
大阪でハウスクリーニング事業を展開するReLife合同会社は、口コミや地域での紹介案件に依存しており、営業範囲が限定的という課題を抱えていました。営業の間口を広げるためにWeb集客の導入を検討し、登録から利用開始までスムーズで、かつ集客力のあるプラットフォームを探していました。
実践内容・成果
ミツモアに登録後、1年以内に月50件の安定成約を実現しています。
ReLife合同会社は現場で「相手の立場になる」ことを大切にしており、訪問前に顧客の好みや生活環境を調べて会話の糸口を準備する取り組みを行っています。作業中は「今から流しますね」と工程を説明しながら進めることで、顧客に安心感を提供しています。価格設定では5社の中で「上から2番目」を狙い、適正価格を保ちながらプロフェッショナルとしての価値を伝える方針です。
その結果、300件以上のレビューを獲得し、苦情はほぼゼロという実績を維持しながら、安定した収益基盤を築いています。
成功の鍵
ReLife合同会社の成功の本質は、単なる「作業」ではなく「仕事」として向き合う姿勢にあります。事前準備で顧客を深く理解し、現場でのコミュニケーションを大切にしたことが、高評価とリピーター獲得につながっています。
関連記事:月50件成約のトップクラスプロが語る、ミツモアでビジネスを成功に導く5つの要素とは?
ラ・セグーロ(静岡)

課題・背景
静岡県袋井市でハウスクリーニング事業を営むラ・セグーロは、日系ブラジル人の兄妹で運営しています。Web集客を活用して事業を成長させたいと考えていましたが、複数の大手集客サイトがある中でどこが本当に効果があるのか判断できない状況でした。地方都市において価格競争に巻き込まれず、自社の特徴を活かした営業ができるかどうかが課題となっていました。
実践内容・成果
ミツモアを本格的に活用した結果、年間200件を超える成約を達成しています。
ラ・セグーロはエアコンクリーニングに2,000円分の防カビコーティングを無料で付けることで「他社にない価値」を提供する方針を採用しています。また、日本人とブラジル人のハーフという背景を活かし、親しみやすいメッセージで個性的な訴求を展開しています。静岡エリアで放送されたミツモアのテレビCMの反響も大きく、顧客の多くが「CM見ました」と反応しています。
その結果、70件を超えるレビューを獲得し、複数企業との年間契約も実現しています。
成功の鍵
価格競争を避けて明確な付加価値を提供したことにあります。ミツモアは見積もりが最大5社に限られるため、「価格だけでなく仕事への評価や実績を見て選んでいただける」と評価しています。ターゲット顧客層を明確にし、そのニーズに合わせたサービスを徹底したことが、高評価とリピーター獲得につながっています。
関連記事:ミツモアで集客し、独立後、ハウスクリーニング事業を急成長させたプロのサクセスストーリー
アイ・コーポレーション(全国28拠点)
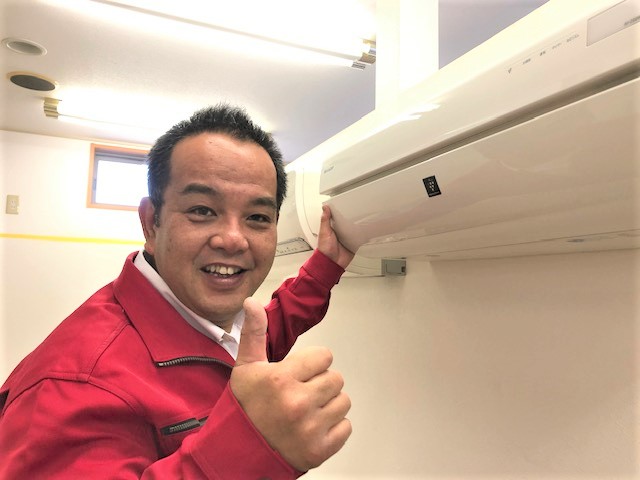
課題・背景
アイ・コーポレーションは関東・関西・九州・沖縄に28拠点を展開し、年間14万台を超えるエアコンクリーニングを手がける大規模企業です。フランチャイズではなく直営で複数拠点を展開することを選択し、品質を統一しながら「エアコンクリーニングという文化を広く伝えたい」という思いを持っていました。できるだけ価格ハードルを下げ、より多くの人が気軽に利用できるサービスにすることが課題となっていました。
実践内容・成果
ミツモアを活用した結果、月間400件を超える成約を実現しています。
ミツモアの自動応募システムについて「事業者側は手間がかからず、顧客側は最大5件に絞って比較できるため選びやすい。双方にメリットがある」と評価しています。各地域にトレーニングセンターを設置して人材を育成し、技術力を高めながら企業努力で価格を抑えています。ミツモアの顧客は室外機クリーニングもあわせてオプションで選ぶ方が多く、知識や理解が深い傾向があります。
その結果、レビュー数は1,500件を超え、東京都内エアコンクリーニングおすすめ人気ランキング1位という評価も獲得しています。
成功の鍵
直営運営で品質を統一し、価格競争力も保ったことにあります。企業理念は「お客様のお役に立ちたい」であり、口コミの全てのご意見に目を通し、厳しい評価も目をそらさずしっかり受け止める姿勢を貫いています。エアコンクリーニングを「特別な出費」から「日常的なメンテナンス」へと位置づけを変える価格設定が、継続的な顧客獲得と市場拡大を実現しています。
関連記事:【フジテレビ newsイット!取材】月間成約250件!最大5社から見積もりが届くミツモアは依頼者が比較して選びやすく、事業者にもメリットになっています
ハウスクリーニングのフランチャイズに関するよくある質問
未経験でもハウスクリーニングのフランチャイズで独立できますか
未経験でも独立は可能です。ハウスクリーニングのフランチャイズオーナーになる方の9割以上は業界未経験からスタートしており、各本部が初心者向けに研修制度を整えています。
おそうじ本舗では24日間、おそうじ革命では約50日間の研修プログラムが用意されています。清掃技術から営業ノウハウまで体系的に学べます。開業後も本部スーパーバイザーによる支援やオーナー同士の情報交換会を通じて継続的にスキルアップできる環境があります。
未経験から成功するには「素直に学ぶ姿勢」と「継続的な学習」が不可欠です。研修で学んだことを自己流にアレンジするのは、基本を完全にマスターしてからにすべきです。
フランチャイズ加盟後の年収はどれくらい期待できますか
年収は地域や営業努力で幅がありますが、年収500万円前後を目指す方が多く、開業1年目から年収1,000万円超を達成するパターンもあります。
フランチャイズ比較サイトの見込みでは、おそうじ本舗加盟店の年収は400〜500万円、ダスキンなら300〜600万円程度とされています。
収入を予測する際は「稼働日数」と「1日あたりの売上」を現実的に見積もることが大切です。月間売上100万円を目指すなら1日平均5万円×20日稼働が必要です。1件3万円の案件なら1日2件弱の受注が必要です。
開業にあたり資格や許可は必要ですか
特に国家資格や許可は不要です。開業届を提出すれば誰でもハウスクリーニング事業を始められます。
業務上で取得が推奨される資格として、ビル清掃に役立つ「ビルクリーニング技能士」や、民間資格の「ハウスクリーニング士」「エアコンクリーニング士」などがあります。資格取得は差別化や自己研鑽に有効ですが、フランチャイズ本部の研修で十分なスキルを習得できるため必須ではありません。
開業時に必須なのは損害賠償保険への加入です。賠償責任保険が該当します。万一清掃中に設備を破損した場合に備え、多くの本部で保険加入を義務付けています。補償額は最低1,000万円以上を推奨します。
契約期間はどれくらいですか
フランチャイズの契約期間は本部により異なりますが、2〜5年が一般的です。
契約期間満了後は自動更新となる本部と、更新料を支払って契約を継続する本部があります。更新条件は契約前に必ず確認が必要です。更新料の有無、更新時の審査基準などが該当します。
契約期間中は本部のルールに従う義務があり、途中で「合わない」と感じても簡単には離脱できません。契約期間の長さと中途解約条件を踏まえ、慎重に加盟を判断する必要があります。
途中で解約できますか
中途解約は可能ですが、多くの場合違約金が発生し条件が厳しく設定されています。
中途解約できる条件は「本部の重大な契約違反」「不可抗力」などに限定されていることが多く、「想定より儲からない」という理由では認められないパターンがほとんどです。災害などが不可抗力に該当します。違約金は残契約期間に応じた金額や固定額が設定されており、数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
解約条件は契約書に記載されているため、契約前に違約金額と解約可能条件を必ず確認が必要です。納得できない条件があれば契約前に交渉するか、加盟を見送る判断も不可欠です。
ロイヤリティ以外に毎月かかる費用はありますか
ロイヤリティ以外にも広告分担金、システム利用料、消耗品購入費などの費用が発生する場合があります。
本部により追加費用の有無と金額は異なります。ロイヤリティが安くても別途広告分担金やシステム利用料が発生すればトータルコストは高くなります。広告分担金は月2〜5万円程度、システム利用料は月1〜2万円程度です。消耗品を本部から購入する義務がある場合、市販品より割高に設定されていることもあります。洗剤、道具類が該当します。
契約前に「ロイヤリティ以外に本部へ支払う費用」の全項目をリスト化し、年間総支払額を試算することが大切です。
本部とトラブルになったらどうすればいいですか
本部とトラブルになった場合、まず契約書の内容を確認し、弁護士や中小企業診断士など専門家に相談することが大切です。
相談先としては弁護士、中小企業診断士、商工会議所、中小企業庁、日本フランチャイズチェーン協会などがあります。フランチャイズ契約に詳しい法律事務所が該当します。
公正取引委員会は「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」で優越的地位の濫用を規制しています。不当な商品購入の強制、一方的な契約変更などが該当します。本部の行為が不当だと感じる場合は、公正取引委員会へ相談することも選択肢となります。
トラブルを事前に防ぐためには契約前の十分な確認と、不明点は文書で回答をもらうことが大切です。
ハウスクリーニングで利益を出すならミツモア
ハウスクリーニングで集客力を高めて利益を伸ばすには、マッチングプラットフォーム「ミツモア」の活用が有効です。
ミツモアはハウスクリーニングや引っ越しなど様々な生活サービスをオンラインで見積もりしてマッチングするプラットフォームです。登録すると近隣エリアの顧客からハウスクリーニングの見積もり依頼が届きます。AIが自動で見積もりを作成して提示する機能があり、見積もり業務の負担を大幅に軽減できます。
2024年時点で累計依頼件数が500万件を超え、登録事業者も全国で77,000社を超えるなど、急成長しています。開業したばかりで自社の知名度がなくてもミツモア上では「ハウスクリーニングを頼みたい顧客」が待っている状態のため、短期間で仕事を獲得できます。
料金は成果報酬型で成約した案件に応じて手数料を支払う仕組みです。広告への先行投資リスクを低く抑えられるため、開業直後で資金に余裕がないときでも活用しやすい特徴があります。
ミツモアを最大限活用するためのポイントは以下の3つです。
- プロフィールの充実:保有資格、対応エリア、得意な作業、実績写真などを詳しく記載する
- 迅速な返信:見積もり依頼が来たらできる限り早く返信する。理想は30分以内
- 口コミの積み重ね:丁寧な作業と気配りで高評価を積み重ね、プラットフォーム内での信頼度を高める
フランチャイズ本部の集客支援に加えてミツモアを併用すれば集客チャネルが広がり、売上増加・利益拡大に直結します。未経験で独立する方や広告に慣れていない方ほど、ミツモアを活用する価値は大きいと言えます。
- 1
- 2